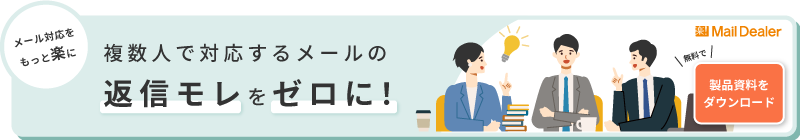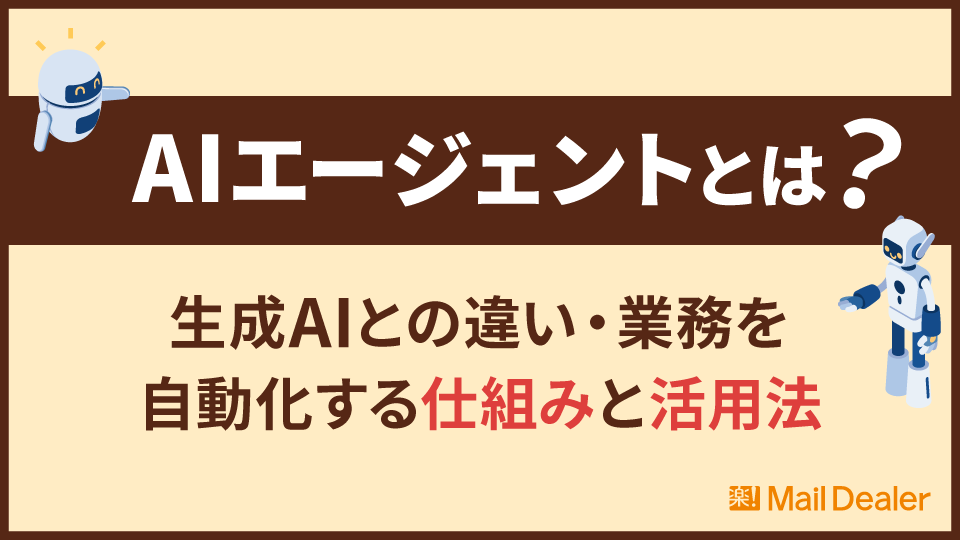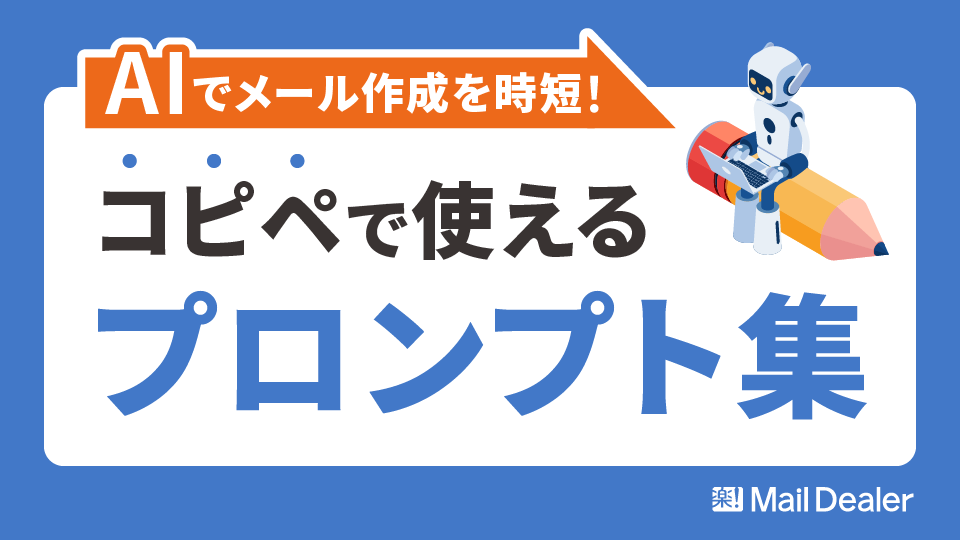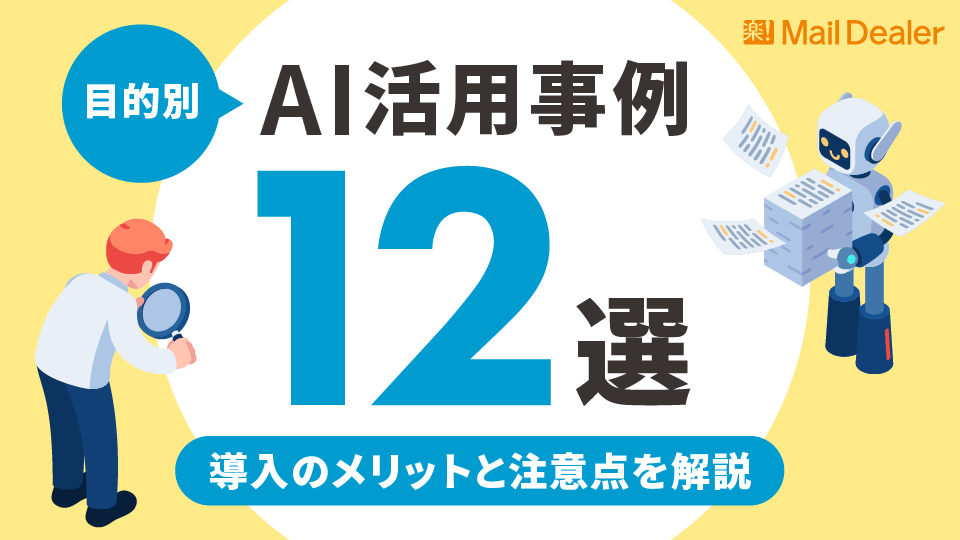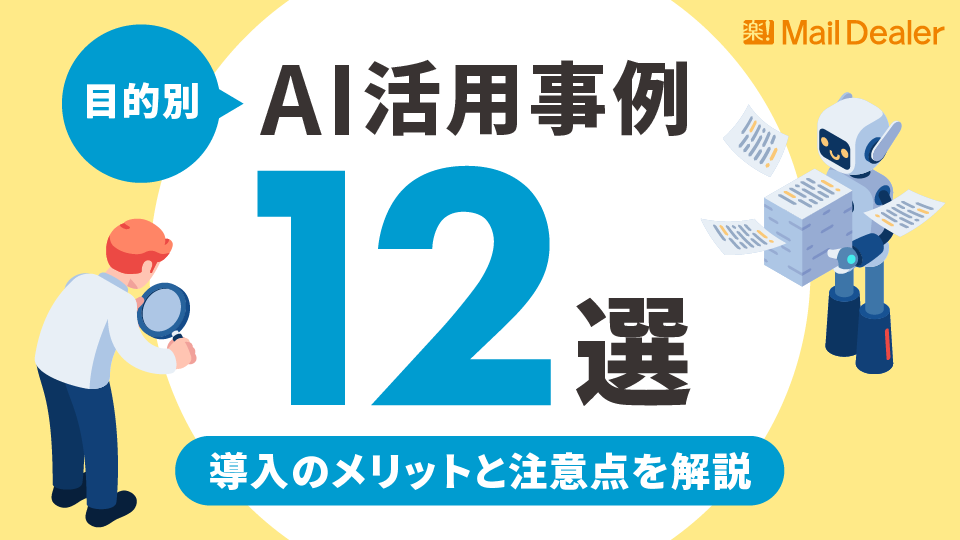
近年、AI(人工知能)の技術は大きく進化し、ビジネスの場においてもAI技術を導入している企業は増えています。
一方で「AIの活用が重要とは聞くけれど、自社でどう活用すればよいのか分からない」と、多くのビジネスパーソンがこのような悩みを抱えています。AIの可能性は無限大ですが、その活用法は業界や企業によって様々です。
本記事では「業務効率化」「売上向上」といった、あらゆるビジネスに共通する最新のAI活用事例を目的別に分類し、それぞれがもたらした具体的な成果数値を踏まえて紹介します。
貴社が抱える課題を解決するための、AI活用の具体的なヒントがきっと見つかります。AIの活用を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
AI(人工知能)とは?【今さら聞けない基礎知識】
AIとは、Artificial Intelligence(アーティフィシャル・インテリジェンス)を略した言葉で、日本語では「人工知能」と訳されます。
AIは研究者によって定義が異なるため、明確な定義はありません。本記事では、AIを一般的に提唱されている「人間の思考プロセスや知的な振る舞いを、コンピュータプログラムによって再現する技術の総称」と定義して記載していきます。
重要なのは、AIが単一の技術を指すのではなく、画像認識や自然言語処理など、様々な要素技術の集合体であるという点です。
AIにできることは、主に以下の5つです。
- 画像認識
- 自然言語処理
- 音声認識
- 最適化
- データの分析・予測
AIのビジネスにおける3つの役割
AIがビジネスシーンで果たす役割は、大きく以下の3つに分類できます。
- 代替(Automation)
- 拡張(Augmentation)
- 創出(Creation)
AIの役割をしっかり理解しておくことで、自社のどのような業務にAI導入が適しているのかがわかるようになります。
それぞれについて詳しく説明します。
代替(Automation)
AI活用における代替とは、これまで人間が手作業で行っていた、ルールにもとづいた定型業務をAIが肩代わりする役割のことです。
例えば、以下のような活用例が挙げられます。
- 毎月のデータ入力や請求書の発行
- 日報の作成
AIを代替で活用することで、人件費の削減やコスト削減となります。
拡張(Augmentation)
AI活用における拡張とは、人間の能力そのものを高め、より高度な判断や創造性を引き出す役割を指します。
例えば、以下のような活用例が挙げられます。
- 医師がAIによる画像診断支援を受けて見落としを防止する
- マーケターがAIの分析結果をもとに新たな戦略を立案する
AIを拡張として活用することで、人間の強力な「第二の脳」として機能させることができ、これまで不可能だったことの実現可能性を高めることができます。
創出(Creation)
AI活用における創出とは、既存のデータから学習し、まったく新しいアイデアやコンテンツを生み出す役割を指します。
また、近年登場した「生成AI」は、テキストや画像、音楽、動画など、多様なコンテンツを生成することができ、以下のようなイノベーションの源泉としての期待が高まっています。
- 新しい製品デザインの考案や広告コピーの生成
- 新薬開発などの研究開発における新たな発見の促進
このようにAIを創出として活用することで、人間では創造できなかった新しい製品やサービスが生まれ、企業として持続的に成長し続けることにつながるのです。
「生成AI」「機械学習」との関係性
AIについて話す際、「機械学習」や「生成AI」という言葉もよく登場します。これらは混合されがちですが、位置付けが異なります。AIの全体像をより明確に認識するためにも、それぞれの関係性を理解しておきましょう。
まず、AI(人工知能)は広い概念として位置付けられます。そして、AIの中に以下が含まれます。
機械学習(Machine Learning)
機械学習とは、AIを構成するための一つのアプローチであり、コンピューターがデータからパターンやルールを自ら学習する技術を指します。
学習したパターンやルールをもとに、新しいデータの分類や予測などを行うため、効率的なタスクの実行が可能です。
生成AI(Generative AI)
生成AIは、機械学習という概念の中にさらに含まれる、比較的新しい技術分野です。
学習したデータをもとに、まったく新しい文章や画像などのコンテンツを創り出すことに特化しています。代表的な例としては、OpenAIのGPTシリーズが挙げられます。
つまり、「生成AIは機械学習の一種であり、機械学習はAIを実現するための主要な技術の一つ」という関係になります。機械学習は学習が中心、生成AIは創造が中心と覚えておくとよいでしょう。
なぜ今AI活用が必須なのか?
現在、多くの企業がAI導入に積極的に取り組んでいます。その理由は、AIの活用が単なる業務効率化ツールではなく、企業の競争力を大きく向上させる可能性を秘めているからです。
AIの導入が企業にもたらすメリットを、以下の3つの視点から解説していきます。
- 生産性の抜本的向上と人的資本の最大化
- データドリブン経営への移行と高精度な意思決定
- 新たなビジネスモデルと顧客価値の創出
メリット1:生産性の抜本的向上と人的資本の最大化
AI導入のメリットは、単なる時間短縮やコスト削減だけにとどまりません。
データ入力や議事録の作成といった時間がかかる単純作業をAIが自動化することで、従業員は企画立案やお客様との対話といった、より創造的で付加価値の高い「人にしかできない仕事」に集中できるようになります。
AIと人間がそれぞれの得意なことを分担することで、組織全体の生産性を飛躍的に向上させることが可能です。
メリット2:データドリブン経営への移行と高精度な意思決定
ビジネスにおいてデータ活用は重要ですが、すべての企業に分析の専門家が所属しているわけではなく、外部の企業に分析を依頼するケースも少なくありません。
しかしAIは、売上や顧客データ、市場のトレンドといった大量の情報を、人間よりも早く、高い精度で分析できます。これにより、経営者が経験や勘だけに頼るのではなく、客観的なデータにもとづいて的確な意思決定(データドリブン経営)を行えるようになります。
さらに、売上予測にもとづいた在庫管理や、顧客の離脱予兆を検知して先回りした対策の意思決定をするなど、AIを活用することで先回りした施策を行うことができます。
メリット3:新たなビジネスモデルと顧客価値の創出
AIの導入は既存の業務を効率化するだけでなく、これまで存在しなかった新しいビジネスや顧客体験を生み出す原動力にもなります。
例えば、顧客一人ひとりの好みや状況に合わせて適切な商品やサービスを提案する「ハイパー・パーソナライゼーション」を実現したり、製品自体にAIを組み込んで使うほど賢くなる「スマート製品」を開発したりと、新しいビジネスモデルや顧客体験を創出することが可能です。
【目的別】ビジネス課題を解決する最新AI活用事例11選
ビジネスシーンでのAI活用事例を「課題・解決方法・効果」の観点から整理し、目的別に紹介します。
- 業務効率化・コスト削減
- 売上向上・マーケティング強化
- 顧客体験(CX)の向上
- リスク管理・品質向上
業務効率化・コスト削減の事例
事例1【経理】:AI-OCRによる請求書処理の自動化で処理時間を大幅に削減
手作業で行う請求書受領業務は、多くの経理部門にとって月末月初に業務が逼迫する原因となり、かつ人的ミスも発生しやすい業務です。この課題を解決する技術として、従来のOCR(光学的文字認識)にAIを搭載した「AI-OCR」の導入が急速に進んでいます。
| 課題 | 毎月、紙やPDFで大量に届く請求書の処理に、経理担当者が多くの時間を費やしている。さらに、手入力によるミスや、担当者による業務の属人化も課題である。 |
|---|---|
| 活用法 | AI-OCR技術を導入。請求書をスキャン・アップロードするだけで、AIが社名、請求日などの項目を自動で読み取り、データ化する。さらに、業務自動化ツールのRPAと連携させることで、会計システムへの転記までを自動化。 |
| 効果 | 手入力作業が減り、担当者は内容の最終確認などに集中すれば済むようになった。月初の処理業務が大幅に短縮されるなど、処理時間や人的ミスの削減に成功した。 |
事例2【物流】:AIによる配送ルート最適化で再配達率20%削減
配送業界の改善すべき課題の一つに、不在配送率の高さが挙げられます。AIの導入により状況に合わせて配送ルートを最適化することで、再配達率の削減が可能になった事例を紹介します。
| 課題 | 交通渋滞や配達時間の指定など、考慮すべき条件が複雑で、効率的な配送ルートを組むのが難しい。経験の浅いドライバーでは効率が上がらず、再配達も多発している。 |
|---|---|
| 活用法 | AIが交通状況、天候、各配達先の荷物量や時間指定などのデータをリアルタイムで分析し、効率的な配送ルートと順番をドライバーに指示する。 |
| 効果 | ドライバーの経験に関わらず、常に効率的なルートでの配達が可能になり、燃料費や労働時間が削減した。また、在宅率が高い時間帯を予測して配達することで、再配達率を20%削減した事例も報告されている。 |
売上向上・マーケティング強化の事例
事例3【マーケティング】:顧客データ分析による解約率予測と防止施策
既存顧客の解約を防止することは、企業の利益に大きく関わります。AIによる高精度なターゲティングによって、効果的な防止策を実行し、解約率の改善(リテンション向上)に成功した事例を紹介します。
| 課題 | サービスを解約してしまう顧客の傾向が分からず、有効な引き止め策が打てない。属性情報のみでキャンペーンを実施していたため、コストがかかっていた。 |
|---|---|
| 活用法 | 過去の顧客の購買履歴、サービスの利用頻度、ログイン情報、問い合わせ内容などのデータをAIに学習させる。AIが現在の顧客データを分析し、数カ月以内に解約する可能性が高い「離脱予備軍」をリストアップする。 |
| 効果 | 解約リスクの高い顧客にターゲットを絞り、特別なクーポンを配布したり、サポート担当者からフォローの連絡を入れたりするなど、先回りした施策を実行できた。顧客維持率(リテンションレート)の向上につながり、安定した収益基盤を築くことができた。 |
事例4【営業】:AIによる商談内容の自動要約とネクストアクション提案
営業業務の中には、営業活動の他にも商談後の報告業務や見積書の作成など、本来の業務以外の作業も発生します。AIを活用することで、本来の業務に注力できるようになり、業務効率を向上させた事例を紹介します。
| 課題 | 営業担当者が商談後の議事録作成や報告業務に追われ、本来の営業活動に集中できない。商談の質も担当者のスキルに依存する。 |
|---|---|
| 活用法 | オンライン商談ツールとAIを連携。商談中の会話をAIがリアルタイムでテキスト化し、商談終了後には要点をまとめた議事録を自動で作成する。さらに、会話内容から顧客の課題や関心事を抽出し、次に取るべきアクション(お礼メールの文面案、提案すべき追加資料など)を提案する。 |
| 効果 | 報告業務の時間を大幅に削減できるだけでなく、全営業担当者の商談内容がデータとして可視化され、組織全体の営業力向上に貢献した。 |
事例5【ECサイト】:パーソナライズされたレコメンド機能【CVR1.8倍向上】
自社商品の売上を向上させるには、効果的なECサイト運用が重要です。AIを導入することで、ユーザーデータに合わせた訴求表示ができ、購買率が向上した事例を紹介します。
| 課題 | すべてのユーザーに同じトップページやおすすめ商品を表示しているため、ユーザーの興味を惹きつけられず、購入に至らないケースが多い。 |
|---|---|
| 活用法 | AIがユーザーの閲覧履歴、購買パターン、カート投入情報などをリアルタイムで分析。トップページや商品ページ、メールマガジンなどに表示する商品を、そのユーザーの好みに合わせて一人ひとり最適化する。 |
| 効果 | 「自分向けにカスタマイズされたお店」のような体験を提供することで、ユーザーの購買意欲を高め、成約率(CVR)を1.8倍以上に向上させることに成功した。 |
顧客体験(CX)の向上の事例
事例6【コールセンター】:音声認識AIによる応対品質の自動評価
オペレーターの質は、顧客の満足度や企業イメージ、最終的には収益にまで影響のある重要な要素です。AIを導入することで、オペレーター業務の品質向上につながった事例を紹介します。
| 課題 | オペレーターの応対品質にばらつきがあり、スーパーバイザーがすべての通話をモニタリングして評価するのは物理的に不可能である。 |
|---|---|
| 活用法 | 顧客とオペレーターの会話をAIがリアルタイムで音声認識。オペレーターが丁寧な言葉遣いをしているか、必須案内事項を伝えているか、NGワードを使っていないかなどを自動でチェックし、応対品質をスコアリングする。 |
| 効果 | すべての応対が客観的な基準で評価されるため、オペレーターは具体的なフィードバックをもとにスキルアップができます。管理者は全体の応対品質をデータで把握し、的確な改善指導が可能に。 |
事例7【小売】:AIカメラによる顧客動線分析と店舗レイアウト改善
実店舗販売においても、AIを活用することで顧客の動向をデータ化・分析し、結果にもとづいて施策を打つことで購買率の向上につながった事例を紹介します。
| 課題 | 顧客が店内のどこを歩き、どの商品棚の前で立ち止まっているのか、正確なデータがなく、感覚で店舗レイアウトを決めてしまっている。 |
|---|---|
| 活用法 | 店内に設置したAIカメラで、個人を特定しない形で顧客の動きを分析。顧客が多く通るメイン動線や、長く滞在するエリア(ヒートマップ)を可視化する。 |
| 効果 | データにもとづき、注目度の高いエリアに売りたい商品を配置したり、顧客が回遊しやすいようにレイアウトを変更したりすることで、売上の向上と快適な買い物体験の両立を実現できた。 |
事例8【飲食】:AI搭載の配膳ロボットによる接客支援【従業員の歩行数削減】
コロナ禍の影響もあり、特にレストラン業態では外食需要の停滞からコスト削減の重要性が高まっています。AIロボットの導入により、従業員コストの削減と、接客の質の向上につながった事例を紹介します。
| 課題 | ホールスタッフの人手不足が深刻である。スタッフは料理の提供や片付けに追われ、顧客へのきめ細やかなサービスが提供できない。 |
|---|---|
| 活用法 | AIを搭載した自律走行型の配膳ロボットを導入。キッチンから客席への料理の提供や、空いた食器の回収を自動で行う。 |
| 効果 | スタッフが厨房と客席を往復する移動距離と時間が大幅に削減され、その分、注文を取ったり、顧客とのコミュニケーションを図ったりといった、より付加価値の高い接客に集中できるようになりました。 |
リスク管理・品質向上の事例
事例9【製造】:画像認識AIによる製品の外観検査自動化【検品精度の向上】
製造業において、外観チェックの自動化のため、AIの画像認識アルゴリズムを活用して、検品精度の向上につながった事例を紹介します。
| 課題 | 人間の目視による製品の外観検査では、集中力の低下による見逃しが発生したり、検査員の熟練度によって精度が左右されたりする。 |
|---|---|
| 活用法 | 生産ラインに高解像度カメラを設置。AIに大量の良品・不良品の画像を学習させ、製品がラインを通過する際に傷、汚れ、形状の異常などを瞬時に検知し、自動で仕分ける。 |
| 効果 | 人間の目では識別困難なμm(マイクロメートル)単位の微細な欠陥も24時間安定して検出可能になり、検品精度が99%以上に向上。検査工程の高速化と省人化も実現。 |
事例10【金融】:AIによるクレジットカードの不正利用検知
近年、クレジットカードの不正使用の手法は、多様化・高度化しています。AIの機械学習を利用することで、最新手口への柔軟な対応・対策が可能になった事例を紹介します。
| 課題 | クレジットカードの不正利用手口は日々巧妙化しており、従来のルールベースの検知システムでは対応が追いつかない。 |
|---|---|
| 活用法 | AIがカード利用者一人ひとりの過去の購買パターン(利用場所、金額、時間帯など)を学習。普段のパターンと著しく異なる利用(例:深夜の海外サイトでの高額決済)があった場合に、不正利用の可能性が高いと判断し、リアルタイムでアラートを発する。 |
| 効果 | 不正利用を早期に検知し、カード会社と利用者の被害を未然に防ぐ。検知精度も日々向上するため、新たな手口にも迅速に対応が可能。 |
事例11【インフラ】:ドローンとAIによるインフラ設備の劣化診断
インフラ設備の点検を人の手で行うには危険が伴い、人員コストもかかります。危険な場所の点検にAIを活用することで、安全かつ効率的に点検作業を行うことが可能になった事例を紹介します。
| 課題 | 橋やトンネル、送電鉄塔などのインフラ点検は、高所での危険な作業が伴い、多大な時間とコストがかかる。 |
|---|---|
| 活用法 | ドローンでインフラ設備の高解像度画像を撮影。その膨大な画像をAIが解析し、コンクリートのひび割れやサビといった劣化箇所を自動で特定・分類する。 |
| 効果 | 人が直接点検する必要がなくなり、作業の安全性と効率が向上。点検コストを大幅に削減できるとともに、劣化状況をデータとして蓄積し、計画的な修繕に役立てることも可能。 |
AI活用を成功に導くための3ステップ・ロードマップ
実際に、自社で導入を進めるための具体的なステップを、3段階のロードマップとして解説していきます。
以下の手順を踏むことで、失敗のリスクを最小限に抑え、着実に成果を出すことができます。
- ステップ1:目的の明確化と課題の特定
- ステップ2:スモールスタートによる費用対効果の検証(PoC)
- ステップ3:本格導入と継続的な改善(運用体制の構築)
それぞれのステップについて詳しく説明します。
ステップ1:目的の明確化と課題の特定
AI活用を成功させるには、まず「目的の明確化」が重要です。技術ありきではなく「自社のどの業務課題を解決したいのか」を起点に考えましょう。
例えば「経理部の請求書処理に毎月20時間かけている作業を5時間以内に短縮し、入力ミスをゼロにする」といった具合に、次の4点を具体的に言語化します。
- どの部署の業務か(Where)
- どの業務か(What)
- なぜ解決したいのか(Why)
- どのように・どれだけ改善したいか(How / How much)
これらを明確にすることで、AI導入の効果を最大化できます。
ステップ2:スモールスタートによる費用対効果の検証(PoC)
2つ目のステップは、本格導入前の試験運用です。目的が明確になったら、いきなり大規模に導入するのではなく、まずは影響の少ない範囲でスモールスタートします。
これをPoC(Proof of Concept:概念実証)と呼び、設定した課題が本当に解決できるか、費用対効果(ROI)は見合うかを本格導入の前に客観的なデータで検証する、極めて重要なステップです。
AI導入におけるPoCの進め方は主に以下の手順で行います。
- まずは、効果が測定しやすく、万が一失敗しても影響が少ない業務を選ぶ。
- 比較的低コストのSaaS型のAIツールなどを活用して試験的に運用する。
- PoCの結果をもとに、始めに定義した課題が解決できるのか、費用対効果(ROI)は見合うのかを、実際のデータで客観的に分析し、検証する。
ステップ3:本格導入と継続的な改善(運用体制の構築)
最後にPoCで有効性が確認できたら、その結果をもとに関連部署へ横展開するなど、本格導入を進めます。
効果的に業務で利用し続けるためにも、「導入して終わり」にしないことです。AIの性能を誰が管理し、どう改善していくのかという運用体制を構築し、継続的なメンテナンスを行うことで、AI活用の効果を最大化できます。
導入前に押さえるべきAI活用の注意点とリスク
AIは強力なツールですが、100%ミスをしないわけではありません。そのため、AIの特性を理解し、潜在的なリスクに備えることが、安全で効果的なAI活用の鍵となります。
AI活用の注意点と起こり得るリスク、その対策について、以下の点を確認しておきましょう。
- 技術的リスク(ハルシネーションなど)と対策
- セキュリティ・コンプライアンスリスクと対策
- 人材育成と社内ガイドラインによる対策
技術的リスク(ハルシネーションなど)と対策
ハルシネーション(幻覚)
特に生成AIにおいて、事実にもとづかない情報を、さも事実であるかのように作り出してしまうことがあります。この現象をハルシネーション(幻覚)といいます。
例えば以下のようなハルシネーションの例があります。
- 存在しない判例や論文を引用する
- 文脈からズレた文章を生成する
生成AIのハルシネーションは、学習データが間違っているから起きる、というわけではありません。
正しい情報を学習していても、AIは事実と異なる内容を自然な文章に織り交ぜて生成することがあります。そのため、意識して事実確認(ファクトチェック)をしないと、誤情報を見落としてしまう危険性があります。
ブラックボックス問題
AIがどのように学習し、なぜその結論に至ったのか、人間にはその思考プロセスが分からないような状態のことを、AIのブラックボックス問題といいます。間違いが発生しても原因がわからず、改善することが困難になります。
技術的リスクの対策
AIのアウトプットは「優秀なアシスタントが作成した第一稿」ととらえ、最終的な事実確認(ファクトチェック)や判断は必ず人間が行うという運用ルールを徹底することが不可欠です。
そのため、AIを利用するすべての従業員がハルシネーションという現象について理解を高め、利用する上でのガイドラインを作成しておくなどの対策が必要となります。
セキュリティ・コンプライアンスリスクと対策
情報漏洩
AIはユーザーとのやり取りから学習するツールのため、特にコンシューマー向けの無料サービスでは、入力した情報が他の人がAIに質問した際に使用され、情報が外部に漏洩するリスクがあります。
また、AIに入力した情報は、AIサービスの事業者のログとして残ります。そのため、事業者が外部からの攻撃を受けたり、情報を漏洩してしまった場合、入力したデータが外に漏れてしまう可能性があるのです。
著作権侵害
AIが生成した文章や画像が、他者の著作権を侵害してしまう可能性もゼロではありません。生成したコンテンツが、既存の著作物と酷似している場合や、学習段階に無許可で使用した場合は、法的な問題に発展するケースもあります。
特に、生成AIが既存の著作物を参考にして、類似のコンテンツを生成した場合、「依拠性」が高いとされ、著作権侵害の対象となる可能性があるのです。
セキュリティ・コンプライアンスリスクの対策
特に顧客の個人情報を扱う企業では、入力したデータが再学習に利用されず、セキュリティが担保された法人向けのAIサービスを選定しましょう。
また、社内の機密情報や個人情報を入力する際の明確なガイドラインを策定し、全従業員に注意喚起を行うとともに、AIの取扱について周知徹底を行うことが重要です。
人材育成と社内ガイドラインによる対策
AIは強力なツールですが、その真価を引き出すのはあくまで人間のスキルです。しかし多くの企業では専門人材が不足し、教育体制の構築も容易ではありません。
そのため、AIに適切な指示を出すスキル(プロンプトエンジニアリングなど)や、AIのアウトプットを批判的に評価し、「自分の思考で考える」ための能力を養うAIリテラシー教育を行うことが重要です。
同時に、情報漏洩などのリスクを管理し、全従業員が安全かつ公平にAIを活用するための利用ガイドラインを策定することも、導入を成功させるための両輪となります。
まとめ:AI活用の第一歩は「メール業務の変革」から
本記事では、AI活用の成功の鍵が「自社の課題解決」という明確な目的設定にあることを、事例や導入ステップを通じて解説しました。
そして、そのDXの第一歩として多くの企業が着手しやすく、かつ効果を実感しやすいのが「メールでの問い合わせ対応」の変革です。
この領域において、業務効率化とチーム全体の管理体制強化を同時に実現するのが、AI機能を搭載したメール共有・管理システム「メールディーラー」です。その主な機能を見ていきましょう。
基本機能:対応漏れ・二重返信をなくし、業務の土台を整える
「メールディーラー」は、チームのメール対応状況(未対応/対応中/完了)や担当者を、自動で「見える化」する仕組みを実現しています。
チームのメール対応状況を全員で可視化することで、「誰が」「どのメールに」「どこまで対応したか」が一目瞭然になります。
自動で更新される対応状況や、担当者情報をチーム全体にリアルタイムで共有できる点が大きな特徴です。チーム対応の課題である、対応漏れや二重対応を防止できます。
AI機能:クレーム検知と返信文作成で、対応の質と速度を向上
「メールディーラー」は、以下のような最新のAI機能が担当者の業務を強力にサポートします。
- リスク検知:クレームメールを検知する機能
- カスタム生成(2025年7月リリース):要点を入力するだけで返信メールを自動で生成する機能
- 自動生成(2025年10月リリース予定):FAQやナレッジをもとに自動で返信文を生成する機能
「メールディーラー」は、16年連続売上シェアNo.1を獲得し、すでに8,000社以上が導入しています。まずは無料でダウンロードできる資料で、その機能と効果をご確認ください。
※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス(以下「当社」といいます)または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。