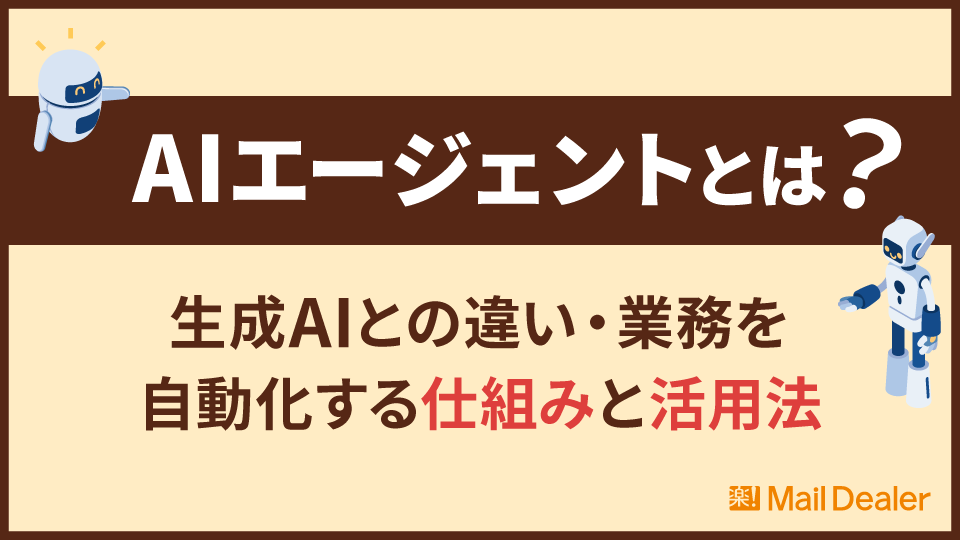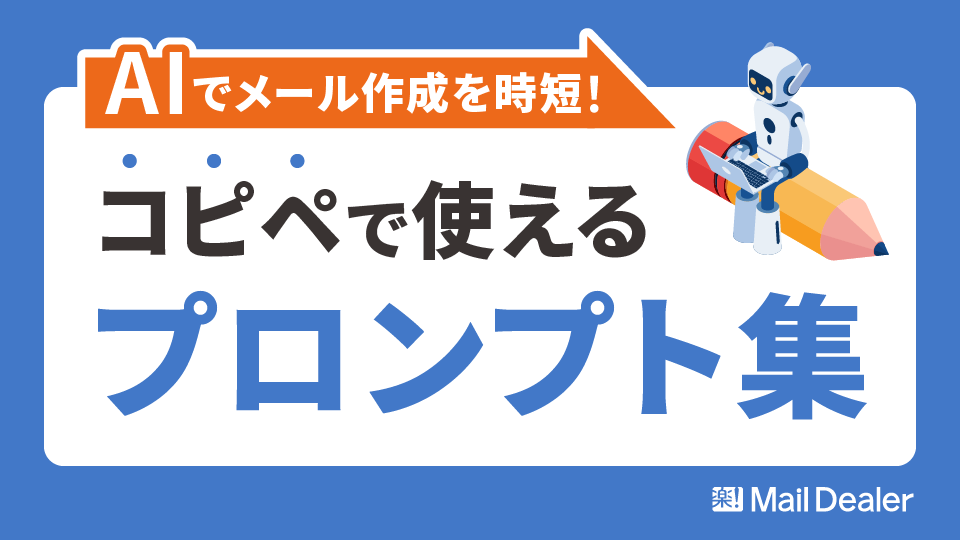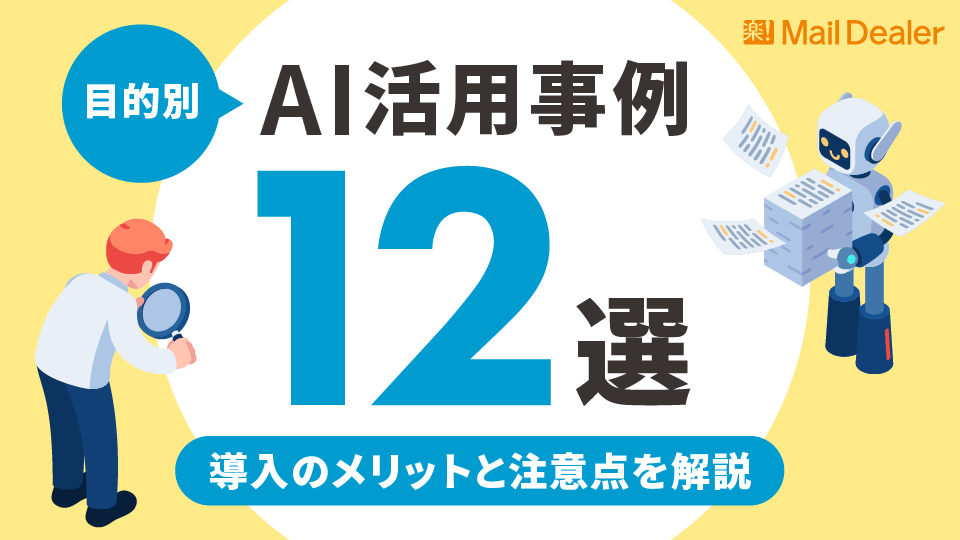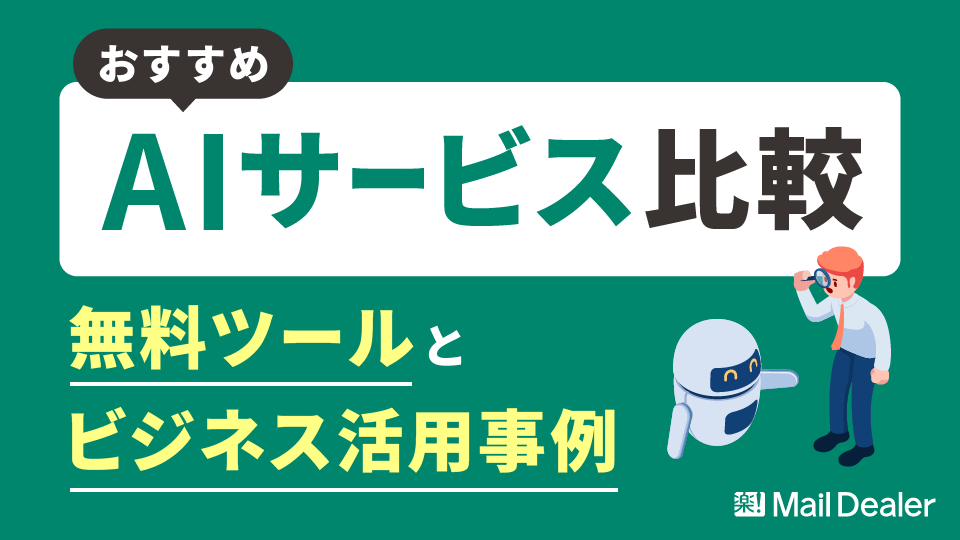
「AIサービスが便利だと聞くけれど、種類が多すぎて、どれが自分に合っているのか分からない」。そんな悩みを抱えていませんか?
そのため、「どのツールが自社の生産性を本当に向上させるのか」という戦略的な選定が求められています。
本記事では失敗しない選び方のポイントを解説し、文章生成など用途別に無料または有料ツールを比較します。
実際の企業活用事例も紹介していますので、自社に合ったAIサービスを選び、業務効率化を実現するための一歩としてご活用ください。
AIサービスとは?ビジネスを加速させる2つのタイプ
AIサービスとは、人工知能を活用してビジネスや個人の活動の業務効率化を支援するツールやシステムです。大きく分けて「生成AIサービス」と「特化型AIサービス」の2種類があります。
それぞれの特徴と役割を解説します。
創造性を拡張する「生成AIサービス」
生成AIとは、文章や画像、音楽、プログラムコードなど、まったく新しいコンテンツをゼロからつくり出すAIサービスです。特徴は、ユーザーがテキスト(プロンプト)で指示を与えるだけで、AIが自動的にコンテンツを生成する点です。
例えば、ビジネスにおいてアイデア出しやクリエイティブ制作、文書作成など、人間の創造性を広げるパートナーとして活用されています。本記事で紹介するAIサービスの多くが「生成AI」のタイプに含まれています。
業務を自動化する「特化型AIサービス」
特化型AIとは、特定のビジネス課題を解決するために設計された業務を自動化するAIサービスです。生成AIが「創造」を得意とするのに対し、特化型AIは「認識」や「予測」、「分類」といったタスク管理が得意です。
例えば、請求書の読み取りや工場の異常検知、将来の売上予測にもとづく在庫管理などに活用できます。さらに、特化型AIは生成AIと組み合わせると、より高度な業務自動化が期待できます。
失敗しないAIサービスの選び方の3ステップ
AIサービスは多様化しており、どのサービスが自社に合っているかを選択するのは困難です。
次に紹介する具体的な選定プロセスを押さえておくことで、以降の具体的なサービス紹介をより効率的に読み進められます。
ステップ1:目的を明確にする(何を作りたいか、解決したい課題は何か)
適切なAIサービスを選ぶうえで最大のポイントは、「AIで何ができるか」ではなく、「自分(自社)は何をしたいか」から考えることです。
目的が明確であれば、数あるサービスから検討すべき候補が自然と絞られ、導入後に「こんなはずではなかった」という失敗を避けられます。
目的の具体例は以下のようなものです。
- ブログ記事の草案を素早く作りたい
- 広告用の画像を低コストで大量に作りたい
- 社内問い合わせの対応工数を削減したい
これらの目的に対して、どのAIサービスが適切かどうかの検討が重要です。
ステップ2:無料プランやトライアルで操作性を試す
次に重要なステップは、「AIサービスの無料プランや期間限定のトライアルで操作性を試すこと」です。
公式サイトの機能一覧だけでは分からない、自社の業務との相性や「使い勝手」を確かめるために、このプロセスは欠かせません。
ステップ1で検討した目的に対して、どのAIサービスを使えば効果的に使えるか確認しましょう。
その際にチェックすべきポイントの具体例を挙げます。
- 操作画面は直感的でわかりやすいか
- 日本語の指示(プロンプト)への理解度は高いか
- 生成されるアウトプットの品質は目的にあっているか
操作性を試す際は、利用目的から事前に候補を2〜3つ程度に絞ると時間も短縮でき、効率的に選べます。
ステップ3:セキュリティと商用利用の可否を確認する
最後のステップは、検討するAIサービスの「セキュリティ」と「商用利用の可否」の確認であり、特に法人利用の際は、欠かせない要素です。確認するポイントをそれぞれ解説します。
「セキュリティ」については、入力した情報がAIの学習に再利用されないかを確認することが重要です。もし、顧客情報や社外秘の企画案などを入力してしまい、それがAIの学習データとして他社への回答に利用された場合、重大な情報漏洩インシデントにつながる危険性があります。法人向けのセキュリティプランや、入力データを学習から除外する設定(オプトアウト)が可能かどうかを確認しましょう。
「商用利用」は生成したコンテンツを自社の製品や広告などで利用できるかどうかを、利用規約での確認が必須です。宣伝目的でAIサービスを利用する際は、法的リスクや損失につながる恐れがあります。
特に無料ツールでは商用利用が制限されている場合があるため、注意が必要です。
【用途別】おすすめ生成AIサービス徹底比較
目的別に分類した主要なAIサービスを、それぞれの特徴、料金、主な利用シーンとともに比較して紹介します。
文章生成・要約AIサービス比較【5選】
このカテゴリで紹介するAIサービスは、記事作成やメール文案の作成、文章の要約などに強みがあります。
利用頻度の高いAIサービスが多く、ビジネスだけでなく個人利用でも活用できる点が魅力です。
ChatGPT:あらゆる用途に対応する万能対話型AI
ChatGPTはOpen AI社が開発した、世界で広く利用されている対話型AIです。非常に高い汎用性を持ち、あらゆるテキスト関連タスクに対応します。次のようなタスクに有効です。
- 質問応答
- 文章の作成や要約
- 翻訳
- アイデア出し
- ソースコード生成
ChatGPTには、無料で使えるプランと、高性能な生成AIが利用できる有料プランがあり、有料プランの料金は月額20ドルからです。(2025年8月現在)
初めてAIサービスを使う方や、1つのツールで幅広い用途に活用したい初心者や法人におすすめです。
Claude:長文読解と自然な文章生成が得意
ClaudeはAnthropic社が開発した、人間らしい自然な文章生成に定評があるAIサービスです。また、出力される文章が丁寧で、ビジネス用途にも活用できます。
一度に処理できるテキスト量が非常に多いため、論文や契約書などの長文の読解や要約で強みを発揮します。
料金プランは無料プランと月額20ドルからの有料プラン(Proプラン)です。(2025年8月現在)
Claudeは長い文章を扱う研究者や法務担当者、より自然な文章を求める方におすすめです。
Gemini:Googleサービスとの連携と最新情報への強み
GeminiはGoogle社が開発した対話型AIです。Google検索を通じて最新情報にアクセスできるため、時事性の高い質問に対応できます。
Googleドキュメントをはじめ、Google Workspaceとスムーズに連携できる点が特徴です。
料金は基本無料ですが、高機能版(Gemini Advanced)はGoogle Oneの有料プランに含まれています。(2025年8月現在)
Geminiは最新情報を扱う機会が多い人や、Googleサービスを日常的に利用している人におすすめのAIサービスです。
Notion AI:ドキュメント管理と一体化した文章作成支援
Notion AIは、Notionに組み込まれたAIアシスタント機能です。Notionのページ内で文章執筆や構成案の作成など、様々な作業を効率化できます。
特徴は、議事録の要約やタスクの洗い出しなど、文章作成とプロジェクト管理をシームレスに連携できることです。
料金は、各プランによって回数制限の有無が異なり、回数制限のない有料プランは月額24ドルから利用できます。(2025年8月現在)
Notion AIはNotionをチームで活用している企業や、ドキュメント作成の効率化を図りたい方におすすめです。
Copilot:Microsoft製品とのシームレスな連携が魅力
CopilotはMicrosoft社が提供するAIアシスタントで、WindowsやMicrosoft Edge、Microsoft 365アプリに統合されています。
Wordの文章作成やExcelのデータ分析、グラフ作成など、Office製品の操作をサポートし、作業効率を大きく高めます。
料金は、Web検索などに利用できる基本的な機能は無料です。一方、法人向けの「Copilot for Microsoft 365」は有料で、エンタープライズレベルのセキュリティとなっています。(2025年8月現在)
Copilotは、Windows環境で業務を行う、Microsoft製品を日常的に活用する個人や企業におすすめです。
画像生成・デザインAIサービス比較【5選】
次に紹介するのは、画像生成やデザイン作成など、ビジュアルコンテンツ制作を劇的に効率化する特化型AIサービスです。
例えば、広告バナーやSNS投稿画像、イラスト、プレゼン資料の挿絵作成などに利用されています。
Midjourney:芸術的で高品質な画像生成
Midjourneyはチャットアプリ「Discord」上で利用できる画像生成に特化したAIサービスです。
生成される画像の芸術性や品質はともに高く、フォトリアルな表現から幻想的なイラストまで、幅広いスタイルに対応しています。
料金は月額10ドルからの有料プランのみの提供です。(2025年8月現在)
Midjourneyは、クリエイターやデザイナー、広告業界関係者などの商用レベルの最高品質な画像を必要とするユーザーにおすすめです。
Stable Diffusion:無料で使えるオープンソースモデル
Stable Diffusionは、Stability AI社を中心に複数の組織が開発して、公開している無料で利用できるオープンソースの画像生成AIモデルです。
特定のキャラクターや画風を学習させた追加モデル(LoRAなど)が多く公開されています。
料金は無料プランと月額10ドルからの有料プランが提供されており、無料プランには生成回数に制限があります。(2025年8月現在)
カスタマイズ性が非常に高いため、利用にはある程度の技術的知識や高性能なパソコンが必要な場合があります。
Stable Diffusionは技術的知識を持ち、自分好みの画像を追求したいクリエイターにおすすめです。
Adobe Firefly:商用利用に強く安全
Adobe Fireflyは、Adobe社が提供する、クリエイティブ制作に特化した画像生成AIサービスです。
Adobe Stockの画像など、権利的問題ないデータのみを学習しているため、生成された画像は安全に商用利用ができます。
Adobe Creative Cloudの有料プランに含まれているほか、生成回数に制限がある無料プランもあります。(2025年8月現在)
Adobe Fireflyは企業のマーケティング担当者など、著作権に配慮しながら安全に商用利用したいユーザーにおすすめです。
DALL・E 3:ChatGPT内で使える手軽さと高精度を両立
DALL・E3は、Open AI社が提供する画像生成AIサービスで、ChatGPTの有料プランで利用できます。(2025年8月現在)
対話型AI内の会話の流れに沿って、自然に画像を生成できます。また、複雑で長い日本語のプロンプトに対する理解度も高く、意図した通りの画像が生成しやすくなっています。
DALL・E3は、ChatGPTを日常的に活用し、テキスト生成と画像生成を一つのツールでシームレスに行いたい人におすすめです。
Canva:デザインツールに組み込まれた簡単AI画像生成
Canvaは、Canva社が提供しているオンラインデザインツールとして知られていますが、AI画像生成機能「Magic Media」も搭載されています。
デザイン作成中に必要な画像を、テキストから生成できます。専門的な知識がなくても、プレゼン仕様やSNS投稿に適した画像生成が簡単です。
画像生成に回数制限がある無料プランがありますが、有料プランで利用回数を増やせます。(2025年8月現在)
Canvaの「Magic Media」は手軽に画像を生成したいビジネスパーソンにおすすめです。
音声・動画・音楽AIサービス比較【5選】
最後は、音声・動画・音楽に特化したAIサービスを紹介します。
動画のナレーション、BGM、広告映像など、これまで専門的なスキルや高価な機材が必要だったコンテンツ制作を誰でも手軽に行えます。
VOICEVOX:日本語に強い無料の音声合成
VOICEVOXは、日本語に特化した無料で使えるオープンソースの音声合成ソフトウェアです。
複数のキャラクターボイスが用意されており、声のトーンや抑揚、速度など細かく調整できます。また、生成した音声は、クレジット表記をすれば商用利用が可能です。
VOICEVOXは、動画やプレゼンテーションのナレーションを、無料で高品質に作成したい人におすすめのAIサービスです。(2025年8月現在)
Suno AI:テキストから楽曲を自動生成
Suno AIは、歌詞や曲のスタイルをテキストで入力するだけで、ボーカル付きのオリジナル楽曲を生成するAIサービスです。
作詞や作曲、編曲、歌唱までを簡単な指示でAIが自動で行います。日本語の歌詞にも対応しており、クオリティの高い楽曲を数十秒で生成可能です。
料金プランは、月額8ドルからの有料プランと、生成回数に制限のある無料プランの2種類があります。(2025年8月現在)
Suno AIは映像コンテンツのBGMや、SNS投稿用のオリジナル楽曲を手軽に作成したい人におすすめです。
Sora:テキストから高品質な動画を生成
SoraはOpen AI社、PikaはPika Labs社が開発したテキストや画像から高品質な動画を生成するAIサービスです。
Soraを利用するには有料プランのChatGPTに加入する必要がありますが、クオリティの高い現実のような滑らかな動画生成で注目されています。(2025年8月現在)
Soraは、映像制作の効率化やSNS向けコンテンツの強化を図りたいクリエイターにおすすめです。
HeyGen:AIアバターが話す多言語対応の動画作成
HeyGenは、入力したテキストをもとに、フォトリアルなAIアバターが話す動画を生成するAIサービスです。
100以上の言語に対応しており、作成した動画を異なる言語に吹き替える機能があります。そのため、プレゼンテーションや研修動画などを多言語展開する際に活用可能です。
料金は動画の生成時間に制限がある無料プランと、月額24ドルからの有料プランがあります。(2025年8月現在)
HeyGenはグローバル向けのコンテンツを作成したい企業や、顔出しせずに説明動画を作成したい人におすすめです。
Runway:動画の編集も可能な高機能動画生成AI
Runwayは動画生成だけでなく、AIを活用した高度な動画編集機能の両方を備えたプラットフォームです。
次のようなプロ向けの編集作業をAIがサポートします。
- テキストからの動画生成
- 動画内の特定のオブジェクトの消去
- スローモーション映像を生成
- 動画の背景の差し替え
料金は機能に制限がある無料プランと月額12ドルからの有料プランがあります。(2025年8月現在)
Runwayは動画クリエイターをはじめとした、AIを活用して動画編集のワークフロー全体を効率化したいプロフェッショナルにおすすめです。
【業務特化型】生成AI以外の主要AIサービス
生成AI以外にも、特定のビジネス課題を解決する強力なAIサービスが存在します。
ここでは、代表的な4つのカテゴリを紹介します。なお、メール業務において、AIを活用して効率化を図る「メールディーラー」がおすすめです。
「AIによるメール対応の品質を均一化」や「優先すべきメールをAIが判別して通知」など、AIを活用してメール業務効率を最大化できます。
AI-OCR:請求書や名刺のデータ化
AI-OCRは紙の書類やPDFの文字情報をカメラやスキャナで読み取り、編集可能なテキストデータに変換するサービスです。
請求書処理の自動化、契約書のデータ化、名刺管理の効率化など、手入力作業を大幅に削減します。
AIチャットボット:問い合わせ対応の自動化
AIチャットボットはWebサイトや社内ポータルに設置し、定型的な質問に24時間365日自動で応答するサービスです。
カスタマーサポートの工数削減や社内ヘルプデスクの効率化、見込み客への一次対応などに活用されています。日常的な問い合わせ対応の負担を減らしたい企業にとって、導入価値の高いツールです。
需要予測AI:売上や在庫管理
過去の販売実績や天候、イベント情報などのデータを分析し、将来の売上や来店客数を高い精度で予測するサービスです。
小売店の発注業務による在庫ロス削減、飲食店の来客数予測にもとづくスタッフ配置などに役立ちます。
売上予測や人員計画の精度を高めたい小売業・飲食業の事業者におすすめです。
異常検知AI:故障や不正の予兆検知
工場設備の稼働データ(振動、温度など)や、システムのログを常に監視し、異常なパターンを検知して管理者に通知するサービスです。
製造ラインの故障予知保全によるダウンタイム削減やクレジットカードの不正利用検知、サーバーダウンの防止に役立ちます。
製造業やIT部門、金融業界などで、システムの安定稼働とトラブルの未然防止を図りたい企業にとって、有効なソリューションです。
【実践編】AIサービスのビジネス活用事例4選
実際の企業がどのようにAIサービスを活用し、具体的な成果を上げているかを4つの事例で紹介します。
事例1【業務自動化】:メガバンクは問い合わせ対応や資料検索時間を削減
三菱UFJ銀行では、行内に膨大なマニュアルや規定が存在し、行員が必要な情報を探すのに時間がかかっていました。さらに、稟議書などの定型文書の作成も大きな負担となっていました。
解決策として、独自のAIアシスタントを導入。行員が質問を入力すると、AIが社内規定やマニュアルから適切な回答を検索して提示し、稟議書作成の支援機能も搭載されています。
その結果、問い合わせ対応や資料検索にかかる時間が大幅に短縮され、行員は顧客対応など、より付加価値の高い業務に集中できるようになりました。
参照元: MUFGが描くデジタルの未来地図(4)
事例2【マーケティング】:大手飲料メーカーはAIタレントをCMに起用
大手飲料メーカーの伊藤園は、CMの制作においてタレントのキャスティングや企画に多大なコストと時間がかかっていました。また、常に新しく話題性のあるマーケティング手法が求められていました。
そこで同社は、画像生成AIで作成したオリジナルのAIタレントを起用。人間のタレントと見分けがつかないほどの高いクオリティがSNSなどで大きな話題となり、製品の認知度向上とブランドイメージの刷新に大きく貢献しました。
キャスティングコストを削減しつつ、先進的な企業イメージを発信することに成功しています。
参照元:AIタレントを起用した「お~いお茶 カテキン緑茶」のTV-CM
事例3【顧客対応】:大手不動産はAIチャットボットで応答率を改善
大手不動産会社のOPEN HOUSEは、物件への問い合わせが営業時間外や休日に電話やメールで多数寄せられていました。しかし、即時対応が難しく、見込み客を取り逃す機会損失が発生。日中の担当者も同様の質問対応に追われていました。
解決策として、WebサイトにAIチャットボットを導入し、よくある定型的な質問に対し、AIが即座に自動で回答する仕組みを構築しました。
その結果、営業時間外の問い合わせにも対応が可能となり顧客満足度が向上。初期対応が自動化されたことで、営業担当者はより具体的な相談や内見案内に集中できるようになり、成約率の向上にもつながっています。
事例4【品質管理】:製造業はAI外観検査で検品精度を向上
製造業では、製品の外観検査を目視に頼っていたため、検査員の熟練度や疲労によって品質にバラつきが生じ、微細な不良品の見逃しが発生していました。
そこで、生産ラインに高解像度カメラと異常検知AIを導入。製品がラインを通過する際に不良品かを瞬時に判別するシステムを構築しました。
AIの導入により、人間の目では識別困難だった微細な欠陥を安定して検知できるようになり、品質の安定化とブランドの信頼性向上に大きく貢献しています。
AIサービス導入を成功させる4つのポイントと注意点
実際の活用事例で紹介した通り、AIサービスは強力なツールですが、導入するだけでは成果にはつながりません。
そこで、AI導入を成功に導くための重要なポイントと、事前に知っておくべき注意点を4つ解説します。
ポイント1:目的を明確にし、スモールスタートする
AI導入の成功には、技術の選定より先に「何を解決したいのか」を明確にすることが重要です。なぜなら、目的が定まっていないと、どのAIサービスが適切かを判断できず、導入効果を最大化できないからです。
また、導入時はいきなり大規模導入せず、一部の部署や特定の業務で試験的に実施する「スモールスタート」がおすすめです。
小さな範囲で効果を測定し、段階的に拡大すればリスクを抑えながら効率的に導入できます。
ポイント2:セキュリティと情報漏洩のリスクを管理する
AIサービスの法人利用で注意すべきなのは、セキュリティ対策です。機密情報や個人情報を入力した場合、AIの再学習に使われ、情報漏洩などのリスクにつながる可能性があるためです。
対策として、入力データがAIの学習に使われない法人向けプランの利用や、社内データの取り扱いに関する明確なルール作りが重要です。
適切な対策を行うことで、安全にAIサービスを活用できます。
ポイント3:著作権と商用利用のルールを確認する
生成AIが作成したコンテンツを商用利用する場合、利用規約の確認は非常に重要です。
なぜなら、生成物の著作権や使用権の扱いはAIサービスごとに異なり、無料プランと有料プランで利用条件が変わることもあるからです。
例えば、画像や音楽をマーケティングや商品に活用する際、著作権の取り扱いを誤ると法的なトラブルに発展する可能性があります。
安心してコンテンツを活用するためにも、利用規約を必ず確認して、商用利用が許可されているサービスを選びましょう。
ポイント4:社内ガイドラインの策定と人材育成を行う
会社でAIサービスを導入する際は、安全かつ効果的に活用するための社内ガイドラインが不可欠です。
なぜなら、ガイドラインが整備されていないと、情報漏洩や誤った使い方によるリスクが発生する可能性があるからです。
例えば、利用範囲や禁止事項、機密情報の取り扱いなどを明確に定める必要があります。
また、ガイドラインの整備だけでなく、社員のAIリテラシーを高めるための研修や、プロンプト活用のノウハウを共有する文化づくりといった人材育成も重要です。
これらの制度と教育の両方で整備することが、AIを安心して活用するための鍵となります。
チームのメール対応課題をAIサービスで解決するなら「メールディーラー」
本記事では、AIサービスの種類や失敗しない選び方や活用事例などを解説しました。重要なのは、自社の課題を明確にし、その解決に合うサービスを選択することです。
数あるAIサービスの中でも、特にチームでのメール問い合わせ対応に課題を抱えている企業におすすめなのが、AI機能を搭載したメール共有・管理システム「メールディーラー」です。
基本機能:返信漏れ・二重対応をなくし、対応業務の土台を整える
「メールディーラー」は、チームのメール対応状況を全員で可視化し、返信漏れや二重対応といったヒューマンエラーをシステムで防止します。
誰がどのメールに対応しているかが一目で分かるため、「このメール対応した?」といった無駄な確認作業がなくなり、情報共有をスムーズに行うことで、非効率なメール業務の生産性を向上させます。
AI機能:クレーム検知と返信文作成で、対応の速度と質を向上
メールの管理基盤を整えた上で、以下のような最新のAI機能が担当者の業務を強力にサポートします。
- リスク検知: AIがクレームの可能性が高いメールを自動で検知し、管理者にアラート通知。対応遅れによる二次クレーム化を防ぎます。
- カスタム生成: 担当者が入力した要点をもとに、AIが質の高い返信文案を自動生成。
- 自動生成(2025年10月リリース予定): 過去の対応履歴やFAQから、AIが最適な回答案を自動で提示。
まずは無料で効果を確認
17年連続売上シェアNo.1の「メールディーラー」は、チームの対応状況を可視化して返信漏れなどのミスを防ぐ管理基盤の上で、最新のAI機能が担当者の業務を強力にサポートします。
すでに9,000社以上の導入実績がありますので、まずは無料でダウンロードできる資料で、その機能と効果をご確認ください。
※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス(以下「当社」といいます)または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。