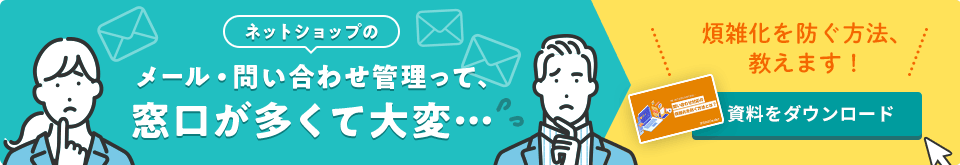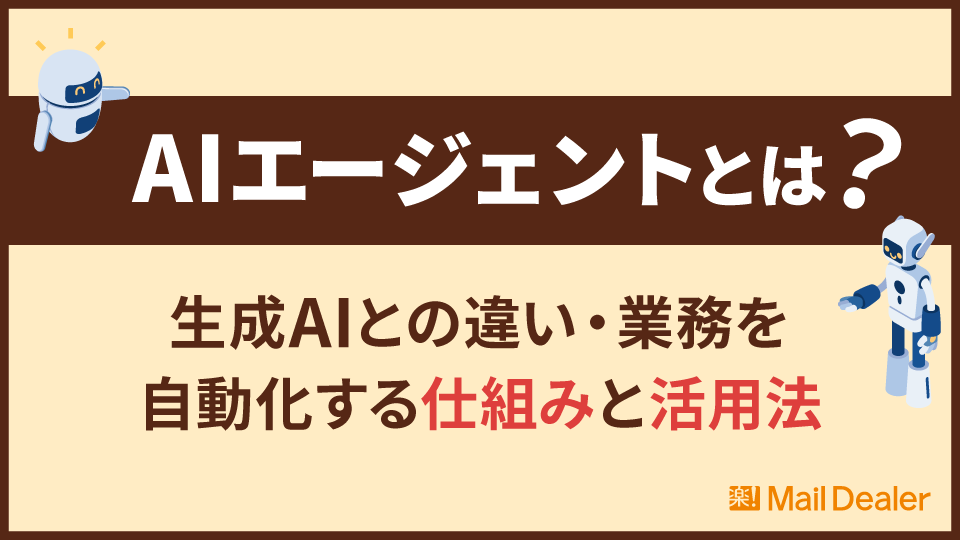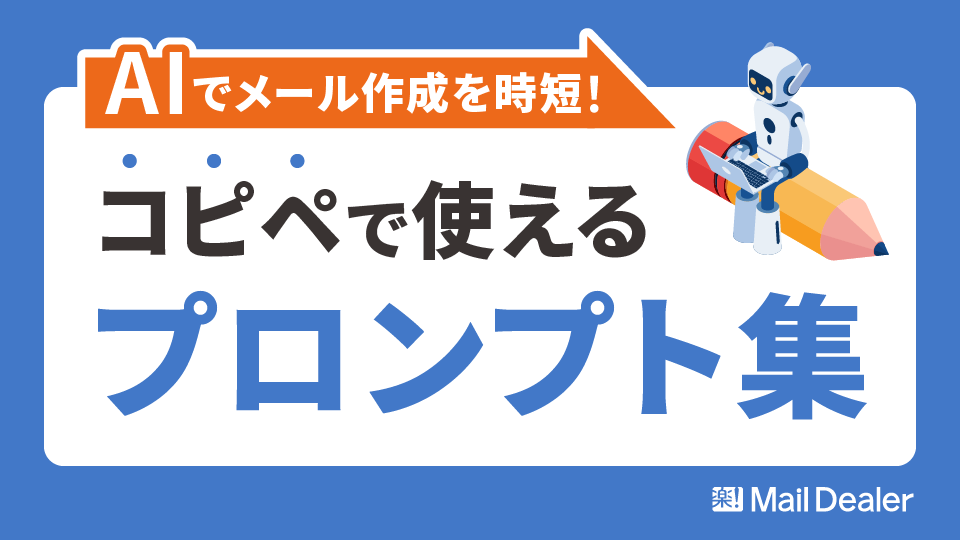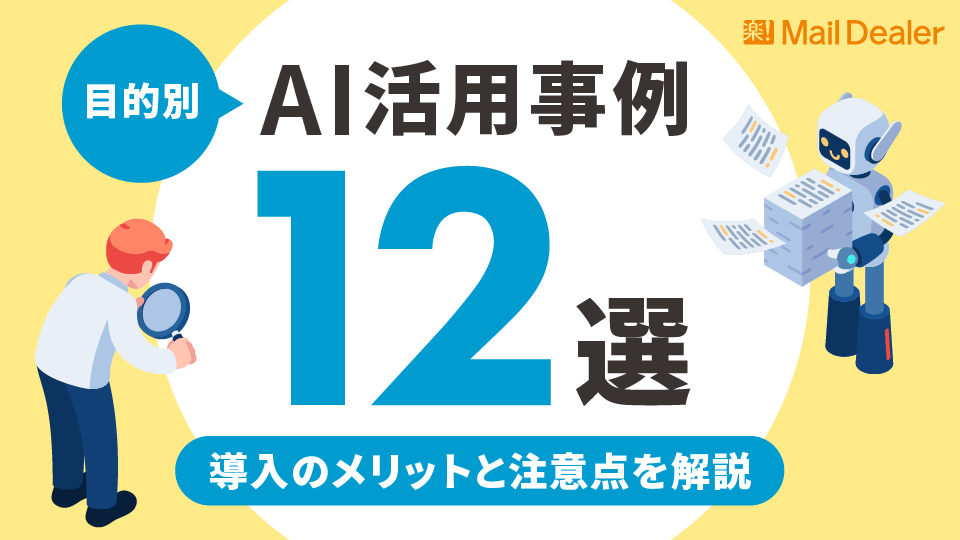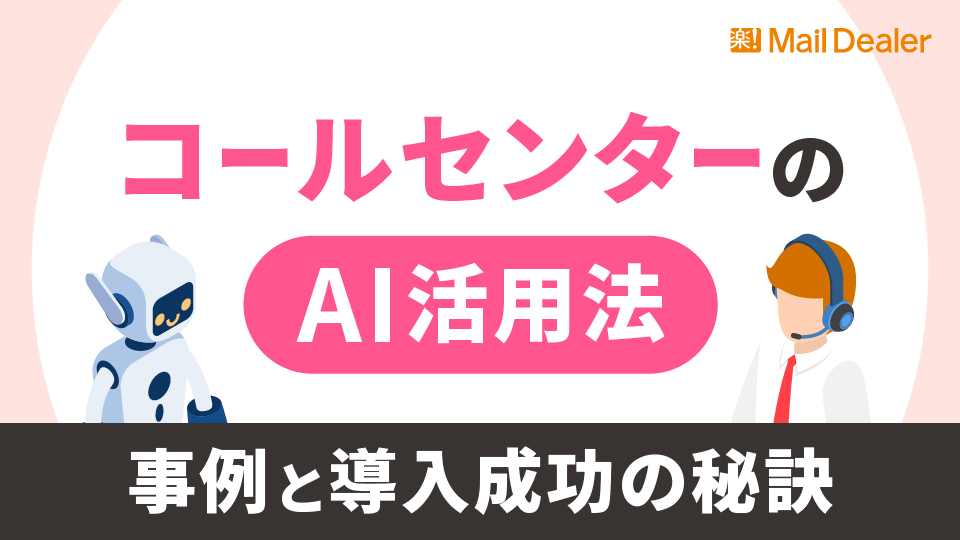
「オペレーターが定着しない」「問い合わせが増え続け、電話がつながらない」「応対品質にばらつきがある」
現在、コールセンターの現場では、これらの課題を解決する強力な一手として「コールセンターへのAI導入」が急速に進んでいる状況です。
本記事では、AIが具体的にどのような課題を解決するのか、最新の企業事例と共に、自社に合ったAIツールの選び方から導入手順、失敗しないためのチェックリストまで、必要な情報を網羅的に解説します。
コールセンターが抱える4つの課題とAIが求められる背景
多くの企業がコールセンターの運営において、共通の課題に直面しています。なぜ今、これほどまでにAIの活用が求められているのでしょうか。
まずは、多くの管理者が頭を悩ませる4つの共通課題と、AIが解決策として注目される背景を解説します。
課題1:慢性的な人手不足と高い離職率
コールセンターが抱える課題の一つが、慢性的な人手不足と高い離職率が引き起こす負のスパイラルです。
コールセンターの業務は、クレーム対応などの精神的負担が大きい「感情労働」であるため、オペレーターの定着が難しく、常に採用活動に追われる構造になっているからです。その結果、既存の熟練オペレーターに業務負荷が集中し、さらなる離職を招いてしまいます。
例えば、一人のベテランオペレーターが離職すると、その負担が他のメンバーに分散され、チーム全体の残業時間が増加します。その結果、疲弊した別のメンバーが退職を検討し始めるといった悪循環に陥るケースは少なくありません。
このように、構造的な人手不足の問題を解決し、従業員が働き続けられる環境を構築するために、AIによる業務の自動化・効率化が求められています。
課題2:オペレーターの応対品質のばらつきと教育コスト
オペレーター個人のスキルや経験に依存することで生じる「応対品質のばらつき」は、顧客満足度に直結する重大な課題です。
対応するオペレーターによって回答の正確さや丁寧さが異なると、顧客に「担当者によって言うことが違う」という不信感を与え、企業のブランドイメージを損なうリスクがあるためです。
例えば、ある顧客が製品の不具合について問い合わせた際、ベテランは的確な解決策を提示して満足を得られた一方、別の日に新人が同じ質問に誤った案内をしてしまい、二次クレームに発展する、といった事態が起こり得ます。この品質の差を埋めるための新人研修や継続的なトレーニングには、莫大な時間とコストがかかります。
したがって、顧客に均一で質の高いサービスを提供し、属人化を排除するためにも、回答を標準化できるAIの活用が有効な解決策となります。
課題3:溢れる問い合わせ(あふれ呼)と機会損失
繁忙時間帯に電話がつながらなくなる事態(あふれ呼)は、顧客満足度の低下だけでなく、売上機会を直接的に失う「機会損失」という経営課題です。
すぐに問題を解決したい、あるいは購入前に疑問を解消したいと考えている顧客にとって「待たされる」という体験はサービス利用を諦める理由になります。
例えば、購入を決意した顧客が最後の確認のために電話したものの、つながらずに断念し、競合他社で購入してしまうケースがあります。
結果として、競合他社のサイトで購入されてしまい、本来得られるはずだった売上を失うことになります。
このように、ビジネスチャンスを逃さないためにも、人間のキャパシティを超えた問い合わせの受け皿として、24時間対応可能なAIの導入が急務とされています。
課題4:多様化する顧客チャネルへの対応
電話だけでなく、メールやチャット、SNSなど問い合わせチャネルが多様化する中で、一貫したサポート品質を保つことが困難になっています。
チャネルごとに対応ツールや履歴の管理方法が異なると、情報が分散してしまい、顧客の過去のやり取りをスムーズに把握できないからです。
例えば、ある顧客がチャットで質問した後、詳細をメールで送り、最終確認を電話で行う、といった行動は珍しくありません。この時、各チャネルの情報が連携されていなければ、オペレーターは毎回同じ説明を顧客に求めることになり、顧客に多大なストレスを与えてしまいます。
したがって、複数のチャネルを横断しても、一貫性のあるスムーズな顧客体験を提供するために、情報を一元管理し、対応を効率化するAIの活用が求められています。
コールセンターで活用できるAIの種類と役割
コールセンターが抱える複雑な課題に対し、AIは具体的にどのような役割を果たすのでしょうか。ここでは、現場で活用されている代表的な5種類のAIとその機能について解説します。
ボイスボット/チャットボットによる問い合わせ自動化
ボイスボットとチャットボットは、定型的な問い合わせ対応を完全に自動化し、24時間365日の受付体制を構築するAIです。
これらのAIはあらかじめ登録されたシナリオやFAQにもとづき、人間の介入なしで自己完結型の対応が可能だからです。これにより、オペレーターは単純な反復作業から解放されます。
例えば、顧客が深夜に「営業時間を知りたい」と電話した場合、ボイスボットが即座に自動応答します。Webサイトから「資料を請求したい」と入力すれば、チャットボットが手続きを案内し、受付を完了させます。
ボイスボットやチャットボットは一次対応を自動化することで、あふれ呼を削減し、人間はより複雑な問い合わせに集中できる環境を実現します。
音声認識AI/応対評価AIによる品質管理
音声認識AIと応対評価AIは、コールセンターの品質管理(QA:Quality Assurance)業務を、属人的・断片的なものから、客観的・網羅的なものへと変革します。
なぜなら、通話内容をテキスト化し、事前に設定した評価基準(例:NGワードの使用、必須案内事項の発話)にもとづいてAIが自動でチェックするため、管理者の主観に頼らない公平な評価が可能になるからです。
例えば、従来は管理者がランダムに数件の通話を聞いて評価していたのに対し、AIは全通話を分析し「コンプライアンスに関する案内漏れがあった通話」だけをリストアップして管理者に報告します。
このように、AIによる品質管理は、評価業務の工数を削減しつつ、応対を客観的なデータにもとづいて改善していくための仕組みを構築します。
FAQシステム/ナレッジベースAIによるオペレーター支援
このAIは、オペレーターが「分からない」と感じる時間を限りなくゼロに近づけ、顧客の自己解決を支援します。
AIが顧客との会話の文脈をリアルタイムで理解し、オペレーターが検索する前に、必要と思われる情報を膨大なマニュアルやFAQの中から予測して提示(サジェスト)できます。
例えば、顧客が「A製品のBという機能のエラー」について話し始めると、オペレーターの画面には即座に「エラーBの対処法」に関するマニュアルの該当ページが自動でポップアップ表示されます。
そのため、オペレーターが回答を探すための保留時間を劇的に短縮し、迅速かつ正確な顧客対応を実現します。
AIによる応対内容の要約と回答支援
このAIは、オペレーターの「応対中」と「応対後」の両方を支援し、業務効率と応対品質を同時に向上させます。
応対中にはリアルタイムで回答候補を提示し、応対後には会話の要約を自動生成することで、オペレーターの記憶力や要約スキルへの依存をなくすことができます。
例えば、新人オペレーターが複雑な質問を受けた際、AIが画面に関連FAQを提示して回答を支援します。通話終了後、AIが数秒で生成した要約を確認・修正するだけで後処理(ACW:After Call Work)が完了するため、すぐに次の電話に対応できます。
AIはオペレーターの負担を軽減し、新人でもベテラン並みの対応ができるよう支援することで、応対品質の標準化に大きく貢献します。
テキストマイニングAIによるVOC(顧客の声)分析
テキストマイニングAIは、コールセンターに蓄積される膨大な対話ログを「コスト」から「価値ある資産」へと転換させる分析ツールです。
人間では読み切れない数千、数万件の問い合わせ内容をAIが高速で解析し、その中からサービス改善につながる重要な傾向やキーワードを自動で抽出・可視化できます。
例えば、「新製品Xに関する問い合わせの中で、『バッテリー』という単語の出現頻度が先週から200%増加している」といった分析結果をAIが自動でレポートします。これにより、製品の潜在的な不具合を早期に発見できます。
このように、テキストマイニングAIは、受動的な顧客対応部門を、能動的に事業改善を提案する戦略部門へと進化させる可能性を秘めています。
こうしたVOC分析をさらに進化させ、分析から次のアクションまでをシームレスに繋げるのが、AIエージェント機能を搭載した問合せ管理システムです。
「メールディーラー」は、蓄積された過去の対応履歴やFAQなどのナレッジをもとに、問合せに対して回答をAIが自動で生成する「回答自動生成エージェント」機能(2025年10月リリース予定)などを通じて、問合せ対応業務の完全自動化を目指しています。
【課題別】コールセンターでのAI導入事例
AI技術が、実際の現場でどのように活用され、企業の課題解決に貢献しているのでしょうか。ここでは、具体的な企業の成功事例を課題別にご紹介します。
人手不足・あふれ呼対策
ヤマト運輸:AIオペレーターが集荷依頼を自動化
ヤマト運輸では、電話による集荷依頼や再配達の受付にAIオペレーター(ボイスボット)を導入しました。AIが顧客の用件を音声でヒアリングし、必要な情報を聞き取ってシステムへ自動登録します。
この仕組みにより、集荷依頼の大半を自動で完結させることに成功。オペレーターの業務負担を大幅に軽減するとともに、顧客は時間帯を問わずスムーズに依頼できるようになり、サービス品質の向上を実現しています。
みずほ証券株式会社:AIボイスボットが定型手続き時間を短縮
みずほ証券は、住所変更やキャッシュカードの再発行といった定型的な電話手続きに、AI搭載のボイスボットを導入しました。顧客が音声ガイダンスにしたがって用件を話すだけで、AIが内容を正確に理解し、手続きを自動で完結させます。
この取り組みにより、簡単な手続きはAIに任せ、オペレーターは資産運用の相談といった、より専門性が求められる業務へ注力できるようになり、導入当初の50倍近くも問い合わせ対応が可能になりました。
応対品質の標準化
大手BPOベンダーであるトランスコスモスは、AIによる応対品質評価システムを導入し、従来スーパーバイザーが時間をかけて行っていたモニタリングと評価レポートの作成業務を自動化しました。
全通話をAIが客観的な基準でスコアリングすることで、評価にかかる工数を削減。全オペレーターに対して公平かつ迅速なフィードバックが可能になり、組織全体の応対品質向上に貢献しています。
オペレーターの業務支援
株式会社ワークスアプリケーションズ:AI検索で問い合わせ時間を50%削減
ワークスアプリケーションズは、社内ヘルプデスクの問い合わせ対応にAI検索システムを導入しました。オペレーターが自然言語で質問を入力するだけで、AIが膨大なマニュアルの中から意図を汲み取り、回答を瞬時に提示します。
このシステムにより、従来の情報検索にかかっていた時間を半減させ、迅速な問題解決と業務効率化を実現しました。
VOC(顧客の声)分析の効率化
株式会社JR西日本カスタマーリレーションズ:メール内容の要約で顧客の声(VOC)分析を効率化
JR西日本カスタマーリレーションズは、顧客から寄せられる大量の意見・要望メールの分析に生成AIを活用しています。従来は担当者が一件ずつ内容を確認・分類していましたが、AIがメールの要点を自動で要約する仕組みを構築しました。
分析にかかる時間を大幅に短縮し、サービス改善につながる貴重な「顧客の声」を、迅速に経営層へ報告できる体制を整えています。
セキュリティ強化と時間短縮
株式会社りそな銀行:AIボイスボットで手続き電話の完了率を向上
りそな銀行は、口座振替の申し込みや住所変更など、電話での各種手続きに関する問い合わせが多く、オペレーターの対応時間を圧迫していました。また、口頭での案内では顧客がURLなどを聞き間違えるリスクもありました。
そこで、AI自動音声対話システムを導入し、よくある質問にAIが自動回答し、手続きに必要なWebページのURLをSMSで顧客のスマートフォンに直接送信する仕組みを構築しました。
その結果、AIが定型的な手続き案内を代替することで、オペレーターの対応工数を大幅に削減しました。また、SMSで正確な情報を送ることで、顧客は聞き間違いなくスムーズに手続きを進められるようになり、電話手続きの完了率が向上し、セキュリティと利便性の両方を高めることに成功しました。
コールセンターへのAI導入で得られる3つのメリット
AI導入は、具体的にどのような数値的な効果をもたらすのでしょうか。ここでは、企業が得られるメリットを3つのポイントに集約して解説します。
メリット1:オペレーターの負担を軽減し離職率を改善
コールセンターの長年の課題は、オペレーターの高い離職率です。
AIの導入により、問い合わせ時の定型業務を代替し、オペレーターを単純作業や一次クレームの負担から解放します。これにより、精神的な負担が劇的に軽減され、従業員体験(EX:Employee Experience)が向上します。
結果として、高い離職率が改善され、採用・再教育にかかるコスト削減に直結します。
メリット2:顧客満足度(CSAT)の向上と機会損失の削減
顧客が特に不満に感じるのは「待たされる」ことです。
チャットボットやボイスボットは24時間365日、顧客を待たせることなく一次対応を行うため、「電話がつながらない」という最大の不満要因を解消します。そのため、顧客満足度(CSAT:Customer Satisfaction Score)を高める効果があります。
さらに、これまで取りこぼしていた営業時間外の問い合わせにも対応できるため、販売機会の損失を防ぎ、売上向上にも貢献します。
メリット3:オペレーターの定着率と生産性の向上
AIの回答支援は、新人オペレーターにとって「カンニングペーパー」のような役割があります。
手元の画面に常に適切な回答が表示されるため、知識不足への不安や、顧客を待たせてしまうストレスが大幅に軽減されます。この「安心して業務に臨める」という体験が、新人の早期離職を防ぎ、定着率の向上につながります。
また、一人あたりの対応件数が増加し、平均処理時間(AHT:Average Handling Time)が短縮されることで、コールセンター全体の生産性も向上します。
AIで進化する未来のコールセンターとオペレーターの役割
AIはオペレーターの仕事を奪うのではなく、オペレーター自身がより専門的で付加価値の高い「問題解決者」になることを後押しします。
なぜなら、AIはFAQへの回答といった定型的な「作業」を得意とする一方、人間は顧客の感情に寄り添う「共感力」や前例のない問題に対応する「高度な問題解決能力」といった本質的な「仕事」に秀でているからです。
例えば、AIが顧客からの一次対応と情報収集を行い、「お客様は製品Aの操作方法でお困りのようです」とオペレーターに要約を提示します。
オペレーターはその情報をもとに、複雑な課題解決や顧客の不安を取り除くという、重要なコミュニケーションに集中できます。
このように、AIを優秀なアシスタントとして活用することで、オペレーターの業務効率が向上し、人間にしかできない高度な対話に集中することができます。
コールセンターAIを導入する際の注意点と3つのリスク
AIは強力なツールですが、その導入はメリットだけではありません。特に顧客の情報を取り扱うコールセンターでは、リスクを正しく理解し、対策することが成功の条件です。
ここでは、特に注意すべき3つのリスクとその対策を解説します。
個人情報・録音データの取り扱いとセキュリティリスク
セキュリティリスクの可能性
コールセンターで扱う通話録音には、氏名や住所、クレジットカード情報など、様々な個人情報が含まれます。個人情報データをAIベンダーが提供する汎用モデルの学習に利用されると、情報漏洩や他社サービスでの利用といった重大なセキュリティインシデントにつながる危険性があります。
確認すべきポイント
AIツールを選定する際は「入力したデータを学習に利用しない(オプトアウト)」ことが契約で明記されているか、自社データ専用の環境で運用できるかを確認する必要があります。
選定基準
AIツールの選定基準として、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格である「ISO/IEC 27001 (ISMS)」などの第三者認証を取得しているかが、ベンダーのセキュリティレベルを測る重要な指標となります。
AIの応対品質とブラックボックス化のリスク
品質の問題
AIの音声認識精度は100%ではありません。方言や専門用語、回線の品質によっては誤認識が発生し、顧客との会話が成り立たなくなるリスクがあります。AIが誤った情報(ハルシネーション)を生成し、顧客に不利益を与えてしまう可能性もゼロではありません。
ブラックボックス化のリスク
AIの判断プロセスが不明瞭なブラックボックス状態では、なぜその回答を導き出したのか分からず、トラブル発生時の原因究明や改善が困難になります。
対策として、AIでは対応が難しいと判断した場合や、顧客が希望した場合に、スムーズに人間のオペレーターへ交代できるエスカレーションフローを事前に設計しておくことが不可欠です。
導入・運用コストと現場への影響に関するリスク
コストの問題
AIの導入には、初期費用だけでなく、月額利用料やシステム連携の開発費、継続的なメンテナンス費用など、ランニングコストがかかります。そのため、投資対効果を慎重に見極めることが必要です。
現場への影響
AI導入は業務フローを大きく変えるため、オペレーターへの十分な説明とトレーニングが欠かせません。教育を怠ると、現場から「使いにくい」「面倒だ」といった抵抗感が生まれ、誰も使わないツールになってしまう危険性があります。
組織文化の重要性
従業員が「AIに仕事を奪われる」などの誤解を生まないよう、注意が必要です。AIはあくまで「オペレーターを支援するパートナー」であることを明確に伝え、人間とAIが協業するビジョンを組織全体で共有することが成功の鍵です。
失敗しないコールセンターAI選定・導入の5ステップ
ステップ1:解決したい課題とKPI(目標数値)を明確にする
「何のためにAIを導入するのか」という目的を具体的に定義します。「人手不足の解消」といった曖昧な目標ではなく「応答率を現状の80%から95%に向上させる」「オペレーターの平均後処理時間を15%削減する」のように、具体的なKPI(重要業績評価指標)を設定することが重要です。
最初のステップを怠ると、「AIを導入すること」自体が目的になってしまいます。ゴールが不明確なままでは適切なツールを選べず、導入後に効果を測定することもできないため、プロジェクト全体の進行や修正が困難になります。
ステップ2:課題に合ったAIツールの種類を選定する
ステップ1で設定したKPIを達成するために、どのAI技術が適しているかを検討します。例えば「応答率の向上」が目的ならば「ボイスボット」、「応対品質の標準化」が目的ならば「応対評価AI」や「FAQシステム」が候補となるでしょう。
「応答率を改善したいのに、オペレーターの教育支援ツールを導入してしまった」となれば、投資が無駄になるだけでなく、現場の混乱を招くなどの問題に発展してしまいます。解決したい課題を明確にして、それに合うツールの導入を検討しましょう。
ステップ3:複数のツールを比較検討する(後述のチェックリスト活用)
同じ種類のAIツールでも、ベンダーによって機能、価格、サポート体制は大きく異なります。必ず複数の候補に絞り込み、後述の「選定チェックリスト」を用いて、客観的な視点で比較・検討しましょう。
複数の候補を比較せずに、最初に話を聞いた1社の情報だけで意思決定するのは危険です。機能やコストだけでなく、既存システムとの連携性やセキュリティレベルを多角的に比較しないと、導入後に「CRMと連携できない」「セキュリティ要件を満たしていなかった」といった致命的な問題が発覚する恐れがあります。
ステップ4:スモールスタート(PoC)で効果を検証する
いきなり全部門・全業務に導入するのではなく、まずは特定の業務や一部のチームに限定して試験導入(PoC:Proof of Concept)を行い、効果を測定します。そこでうまくいった部分を参考にし、逆に導入がスムーズにいかなかった点を次回の改善点として対策を練っておきます。このスモールスタートが、本格導入へのスムーズな移行を後押しします。
PoCを行わずに本格導入し、現場で使われなかったり、システム連携に重大な問題が見つかったりした場合、投資が無駄になるだけでなく、社内でのAIに対する信頼そのものを失ってしまいます。
ステップ5:本格導入と継続的なチューニング
PoCで効果が確認できたら、対象範囲を広げて本格導入へと進みます。ここで重要なのは、「導入して終わり」にしないことです。顧客の問い合わせ内容の変化に合わせてFAQを更新したり、AIの応答精度を定期的に評価・改善(チューニング)したりする運用体制を整える必要があります。
近年、AIは急速に進化しています。この継続的な改善を怠ると、導入当初は高かった性能が、新商品やサービスの登場によって徐々に低下し、数カ月後には「使えないAI」になってしまう恐れがあります。
【実践】コールセンターAI選定チェックリスト7項目
自社に合ったAIツールを選ぶために、具体的に何を比較・検討すればよいのでしょうか。以下の7つの項目をチェックリストとしてご活用ください。
① 自社の課題解決に直結する機能か?
「多機能」であることと「自社に必要」であることは違います。前述のステップ1で定義した課題を解決するために、本当に必要な機能が備わっているかを確認しましょう。
② 既存システム(CRM/CTI)と連携できるか?
既存の顧客管理システム(CRM)や電話システム(CTI)と連携できなければ、データが分断され、かえって業務が非効率になる可能性があります。API連携の実績や柔軟性を確認しましょう。
③ セキュリティ対策は万全か?
顧客の個人情報を扱う以上、セキュリティは最重要項目です。ISMS認証の有無や、データの暗号化、アクセス制御など、ベンダーのセキュリティ対策レベルをチェックしましょう。
④ 導入・運用コストは予算に見合うか?
初期費用だけでなく、月額利用料、オプション費用、メンテナンス費用などを含めた総所有コスト(TCO:Total Cost of Ownership)を算出し、予算内で継続的に運用可能かを見極めましょう。
⑤ 導入後のサポート体制は手厚いか?
導入時の設定支援はもちろん、運用開始後のトラブル対応や、より効果的な活用方法の提案など、ベンダーのサポート体制が充実しているかを確認しましょう。伴走してくれるパートナーとして信頼できるかが重要です。
⑥ AIの学習やチューニングは自社で可能か?
FAQの追加や応答パターンの修正などを、その都度ベンダーに依頼するのでは時間もコストもかかります。管理画面が直感的で使いやすく、自社の担当者が簡単に行えるかを確認しましょう。
⑦ クラウド型かオンプレミス型か?
迅速に導入でき、常に最新機能を利用できる「クラウド型」と、自社のセキュリティポリシーに合わせて柔軟にカスタマイズしやすい「オンプレミス型」。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社の規模や方針に合った方を選びましょう。
まとめ:AIでコールセンター業務を次のステージへ
本記事では、コールセンターが抱える課題に対し、AIがいかにして有効な解決策となるかを、具体的な機能や事例を交えて解説しました。AIはオペレーターの仕事を奪うのではなく、その負担を軽減し、より専門性の高い業務へとシフトさせる強力なパートナーです。
特に、電話だけでなく大量の問い合わせメールが日々寄せられる現代のコールセンターでは、AIの知能と、情報を一元管理するシステムの両輪で対策を講じることが成功の鍵となります。
問い合わせ対応の課題を解決するなら「メールディーラー」
「メールディーラー」は17年連続売上シェアNo.1のメール共有・管理システムです。チームで対応すべきメールを「新着」「対応中」「完了」といったステータスで一元管理することで、対応漏れや二重対応といったヒューマンエラーを解決します。
「このメール対応した?」といった無駄な確認作業がなくなり、情報共有をスムーズに行うことで、非効率なメール業務の生産性を向上させます。
最新AI機能で、対応の速度と品質を飛躍的に向上
「メールディーラー」はAI機能を搭載しているため、担当者の業務を強力にサポートします。2025年7月に「カスタム生成」をリリースしました。これにより、 担当者が入力した要点をもとに、AIが質の高い返信文案を自動生成することができます。
さらに、2025年10月には、AIが過去の対応履歴やFAQをもとに返信案を自動で生成する「自動生成」機能をリリース予定。要点を入力するだけで返信文を作成するカスタム生成と合わせ、担当者の経験や知識に左右されない、安定した品質のメール対応を実現できます。
メール対応を劇的に変える「メールディーラー」の詳細は、ぜひ以下の無料資料でご確認ください。
※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス(以下「当社」といいます)または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。