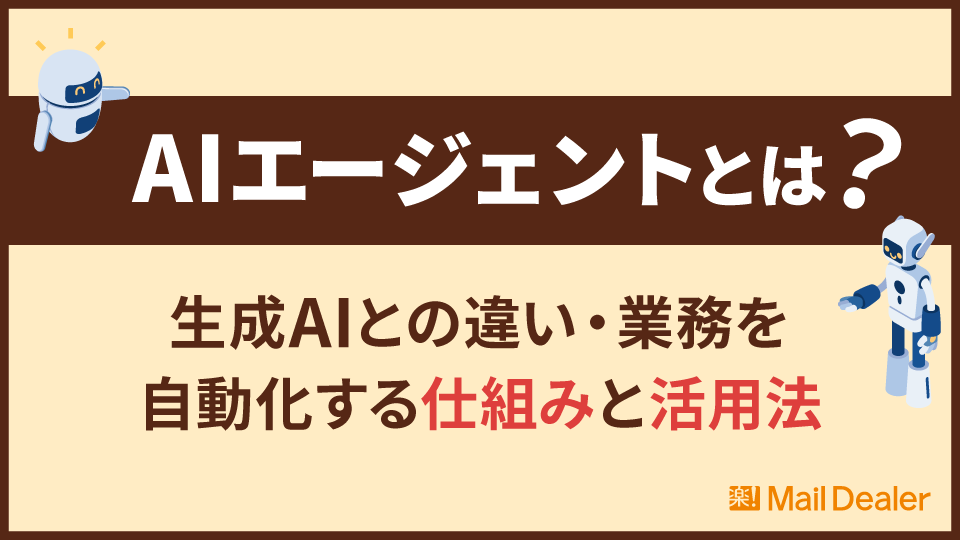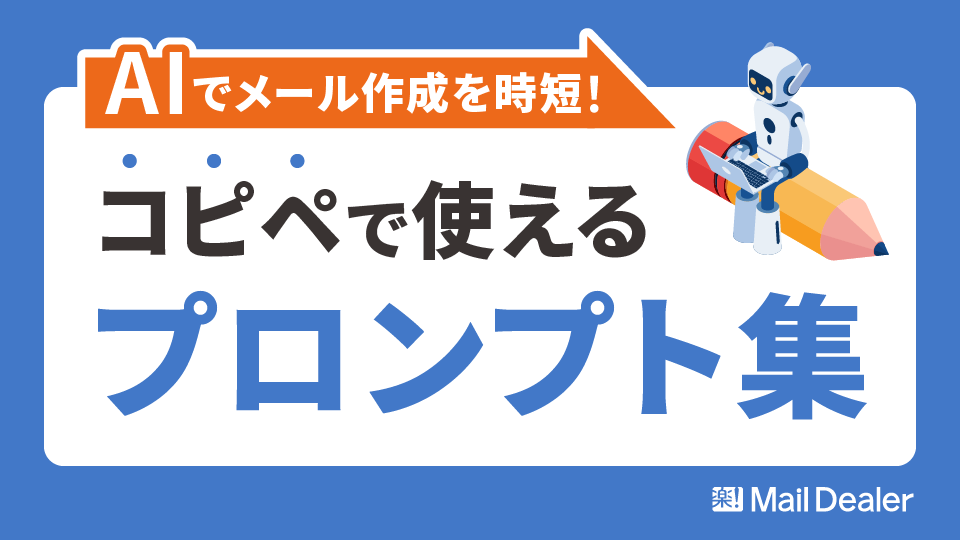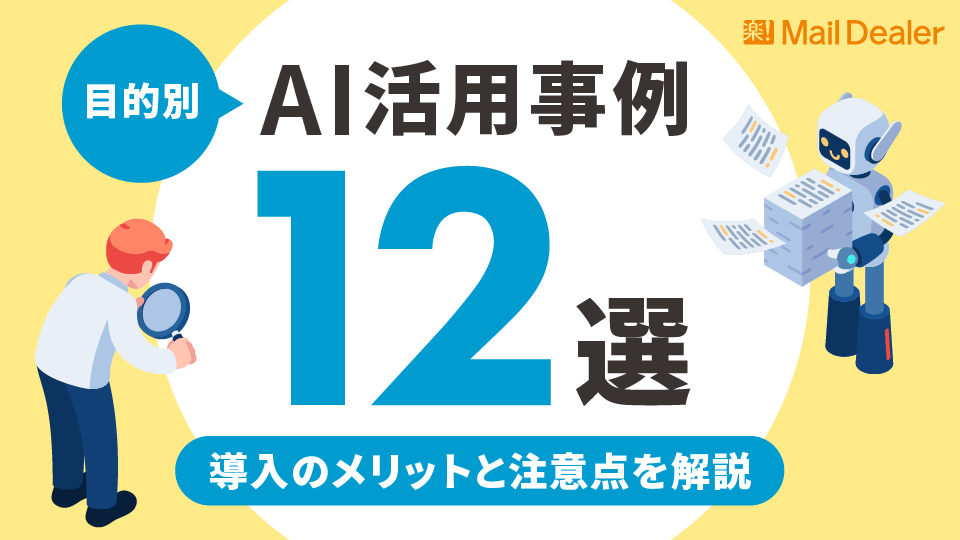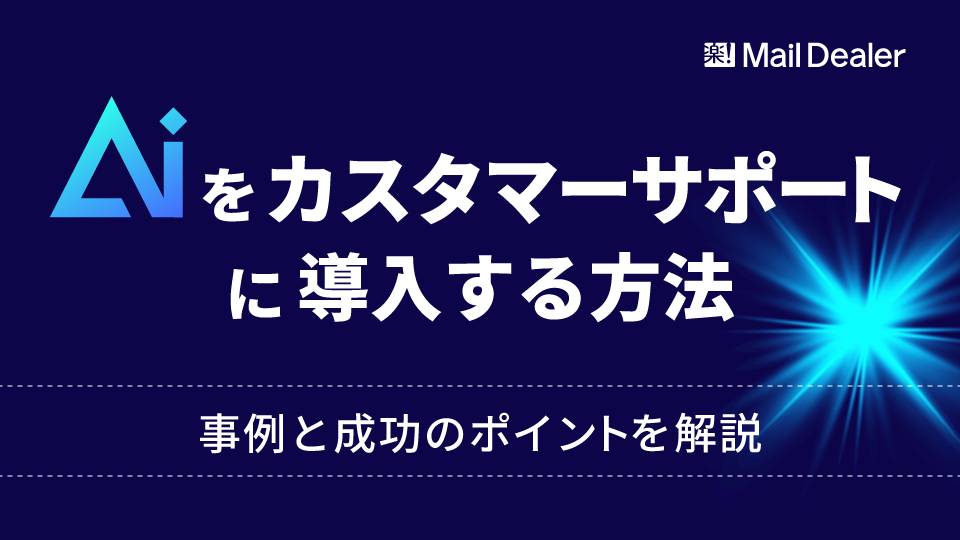
「問い合わせは増え続けるのに人手が足りない」「顧客を待たせてしまい満足度が下がっている」。
多くのカスタマーサポート部門が直面する課題です。
その解決策として注目されているのがAIの活用です。AIは顧客満足度を高めながらオペレーターの負担を軽減し、サポート部門をコストセンターからプロフィットセンターへと進化させる力を持っています。
本記事では、AIをカスタマーサポートで活用する際の具体的なメリットや活用事例を解説します。
なぜ今、AIを活用したカスタマーサポートが求められるのか?
なぜ今、多くの企業がカスタマーサポートにAIを導入しているのでしょうか。その理由は「深刻な人手不足」と「高まる顧客の期待」という課題に対し、AIが有効な解決策だからです。
従来のやり方では、オペレーターの負担が増大し続ける一方で、顧客を満足させることが困難になっています。
ここでは、AI活用が不可欠となったそれぞれの課題について解説します。
深刻化する人手不足とオペレーターの負担増大
カスタマーサポートは、クレーム対応など精神的負荷が多くかかる業務です。そのため、慢性的な人手不足と高い離職率が業界全体の課題となっています。
さらに、問い合わせが増え続けても限られた人員で対応しなければならず、オペレーター1人あたりの業務負担が増大し、結果として疲弊を招く悪循環を生み出しています。
特に、日々大量に寄せられる問い合わせメールへの対応は、業務を圧迫する大きな要因となっています。この課題に対し、AIを活用すれば、メール対応業務を劇的に効率化させることが可能です。
例えば「メールディーラー」は、AI活用でメール対応業務を効率化できるメール共有・管理システムです。「カスタム生成」が搭載されており、担当者が返信したい内容の要点を入力するだけで、AIが適切な返信文を自動で生成することができます。
その結果、作業時間を大幅に削減でき、スタッフの負担軽減につながります。
このように、AIはカスタマーサポート業務の構造的な課題に対して、問題を解決し、持続可能なサポート体制を構築する鍵として期待されているのです。
「待たされること」を許容しない顧客期待の高まり
スマートフォン一つで即時に問題を解決できる時代において「24時間365日、すぐに回答が得られること」は、特別ではなく当然の期待となりました。
一方で、電話がつながらない、返信が遅いといった体験は、顧客満足度を著しく下げ、顧客離れ(チャーン)を招く要因になります。
こうした高まる顧客の期待に人間だけで応えるのは限界があります。
その解決策がAIによる自動化です。AIを活用することで、時間や人員に縛られない持続可能な顧客対応が可能となります。
【顧客体験(CX)と従業員体験(EX)】AIがもたらす2つの戦略的価値
AIを導入するメリットは、単なるコスト削減だけではありません。
ここでは、AI導入のメリットを、顧客体験(CX)と従業員体験(EX)という2つの視点から、戦略的な価値を整理して解説します。
顧客体験(CX)の向上(24時間対応、待ち時間ゼロ、自己解決の促進)
AIチャットボットやボイスボットを導入すれば、人間のオペレーターが対応できない深夜や休日でも、24時間365日、顧客からの問い合わせに即時応答できます。
例えば、よくある質問(FAQ)にはAIが瞬時に回答するため、顧客の待ち時間をほぼゼロにすることが可能です。
さらに、AI搭載のFAQシステムは、顧客が入力した曖昧なキーワードでも意図を予測して適切な回答を提示できるため、顧客がオペレーターに頼らずとも問題を解決できる「自己解決率」が向上します。
このように、AIの活用によって顧客は迅速なサポートが受けられるようになり、顧客体験の向上に直結します。結果として、サービスの利用継続やリピート率向上にもつながります。
従業員体験(EX)の向上(単純作業からの解放、負担軽減、専門性の向上)
多くの企業では、問い合わせ全体の約8割が定型的な質問とされています。定型的な質問の対応をAIに任せることで、オペレーターは単純な反復作業から解放されます。
その結果、オペレーターはクレーム対応や複雑な相談など、より高度な判断と共感が求められる業務に集中でき、心理的・肉体的な負担を軽減できます。
つまり、AIを「優秀なアシスタント」として活用することで、オペレーターは単なる案内役ではなく、顧客の課題を解決する専門家としてスキルを磨くことができ、従業員体験の向上にもつながります。
例えば「メールディーラー」のようなツールを活用すれば、AIが最適な過去事例やよくある質問をもとに返信案を自動生成してくれます。面倒な検索や文章作成が不要になるため、従業員の負担を軽減することが可能です。(※本機能は2025年10月リリース予定)
ご興味のある方は以下より資料をダウンロードいただけます。
カスタマーサポートにおけるAIの活用パターン
カスタマーサポートにおけるAIの活用パターンを以下の3つのレベルに分けて解説します。
- レベル1:【自動応答】チャットボット・ボイスボットによる一次対応の自動化
- レベル2:【オペレーター支援】FAQサジェスト・応対メモ自動生成
- レベル3:【VOC分析】問い合わせデータの分析とサービス改善への活用
レベルが上がるほど、活用の内容が高度になります。
AIを活用する際は、一部の業務など、スモールスタートから始めるのが推奨されますので、段階的に導入を進める際の参考にしてください。
レベル1:【自動応答】チャットボット・ボイスボットによる一次対応の自動化
レベル1のAI活用パターンは、チャットボットやボイスボットによる一次対応の自動化です。
この段階では、よくある質問への回答や資料請求の受付など、定型的な問い合わせをAIが自動で完結させます。
AI導入の目的は、問い合わせが急増し電話がつながらない状態のことを指す「あふれ呼」の削減と、オペレーターの対応件数の削減です。
チャットボットとボイスボットの具体的な活用例は以下です。
- チャットボット:顧客からの質問に24時間体制でテキストで対応する
- ボイスボット:顧客から問い合わせに対し、AIがオペレーターの代わりに自動音声で対応する
このようにAIが「一次受付担当」としての役割を担うことで、顧客は必要なタイミングで迅速にサポートを受けられ、オペレーターは作業時間と労力を削減できます。
レベル2:【オペレーター支援】FAQサジェスト・応対メモ自動生成
レベル2のAI活用パターンは、FAQサジェストや応対メモ自動生成によるオペレーター支援です。
この段階では、AIをオペレーターの「アシスタント」として活用し、応対品質と業務効率を向上させます。
FAQサジェストと応対メモ自動生成の具体的な活用例は以下です。
- FAQサジェスト:顧客との会話中に、AIがリアルタイムで関連するFAQをオペレーターの画面に表示する
- 応対メモ自動生成:通話終了後に応対内容の要約を自動で作成する
このようにAIが「オペレーター支援」としての役割を担うことで、新人オペレーターの早期戦力化や、後処理時間(ACW:After Call Work)の短縮を実現できます。
レベル3:【VOC分析】問い合わせデータの分析とサービス改善への活用
レベル3のAI活用パターンは、問い合わせデータを分析し、サービス改善に生かす顧客の声(VOC:Voice Of Customer)分析です。この段階では、AIを「データアナリスト」として活用し、カスタマーサポート部門をコストセンターからプロフィットセンターへ変革します。
VOC分析の具体的な活用例は以下です。
- VOC分析:テキスト化された大量の通話履歴やチャットログから、「顧客が不満に感じている点」や「製品改善のヒント」などを自動で抽出・要約する
分析結果を製品開発部門やマーケティング部門にフィードバックすることで、事業全体の改善に貢献できます。
AIが「VOC分析」を行うことで、人による分析よりも精度が高く、解像度の高い改善点を導き出せます。
【最新】カスタマーサポートにAIを導入した事例6選
ここでは、カスタマーサポートにAIを導入した事例を6つ紹介します。
自社の課題と照らし合わせながら、「AIで何が解決できるのか」を具体的にイメージするための参考にしてください。
日本航空:AIチャットボットで24時間365日の問い合わせに対応
日本航空は、海外渡航者向けにAIチャット形式の情報提供サービスを導入しました。
【活用レベル】
レベル1(自動応答)
【内容】
FAQサイトに日本IBMのコグニティブ・システム「Watson」を活用したAIチャットボット「マカナちゃん」を導入しました。
従来、電話がつながりにくい時間帯や深夜の問い合わせに対応できなかった課題を解決しました。
ユーザーがいつでも自己解決できる環境を整え、顧客満足度が向上しました。
SBI証券:顧客需要が高い書類請求の電話をAIで自動化
SBI証券はコールセンター電話窓口に、対話型AIプラットフォームを活用したバーチャルアシスタントによる電話自動応対を導入しました。
【活用レベル】
レベル1(自動応答)
【内容】
口座開設資料の請求など、定型的かつ大量に発生する電話問い合わせに対し、Kore.ai.Japan合同会社の対話型AIプラットフォーム「Kore.ai XO Platform」を活用したAIボイスボットを導入しました。
24時間365日、AIが自動で受付を完結させることで、オペレーターの負担を軽減し、顧客の利便性を向上させました。
東京ガス:問い合わせに対する確認項目をAIが提示して業務効率アップ
東京ガスは、コールセンター電話対応業務を効率化するためにAIを導入しました。
【活用レベル】
レベル2(オペレーター支援)
【内容】
顧客との通話内容をAIがリアルタイムで認識し、オペレーターが確認すべき項目や、案内の抜け漏れがないかをPC画面上に表示します。
この支援により、オペレーターが情報を探す手間が削減され、応対時間が平均10秒短縮されました。さらに、必要な情報が即座に手に入ることで自己解決できる範囲が広がり、管理者にエスカレーションする件数も14%削減されました。
これらの効果が積み重なった結果、年間1万1000時間もの応対時間削減を達成すると同時に、よりスムーズで的確な対応が可能となり、顧客満足度の向上にもつながっています。
サントリーウエルネス:生成AIによる対話要約の自動化
サントリーウエルネスは、お客さまとの対話要約を自動化し、顧客対応業務を効率化するためにAIを導入しました。
【活用レベル】
レベル2(オペレーター支援) & レベル3(VOC分析)
【内容】
生成AIを活用し、顧客との対話内容を自動で要約します。オペレーターの後処理業務を効率化すると同時に、要約された質の高いVOCデータを蓄積しています。
このデータを分析することで、顧客理解の深化とサービス改善につなげています。
明治安田生命:応対時メモの自動生成でACWの削減
明治安田生命は、コミュニケーションセンターでのお客さま応対メモの作成業務を自動化するAIを導入しました。
【活用レベル】
レベル2(オペレーター支援)
【内容】
株式会社ELYZA、カクラリ株式会社それぞれと連携し、通話内容をAIが自動で要約し、応対メモを作成するシステムを導入しました。
従来、通話終了後にオペレーターが手作業で行っていた後処理時間(ACW)を最大30%削減できる見込みであり、オペレーターの負担軽減と生産性向上を目指しています。
株式会社JALカード:生成AIの仮想顧客分析で購買率向上
株式会社JALカードは、効果的なマーケティング施策としてAIを導入しました。
【活用レベル】
レベル3:(VOC分析)
【内容】
NTTデータの生成AIを活用し、カードの利用傾向などから複数の「AIバーチャル顧客」を作成しました。仮想空間でAI同士にグループディスカッションを行い、効果的な販促ターゲットやDMの訴求方法に関する示唆を抽出しました。
この示唆にもとづきDMを送付した結果、従来ターゲットより購買率が3.0%向上しており、顧客データをもとにした高度な需要予測や施策立案にAIを活用する先進的な事例となっています。
カスタマーサポートにAIの導入を成功させるための5ステップ
カスタマーサポートにAIを導入して成功に導くための手順を、以下の5つのステップに分けて解説します。
- ステップ1:導入目的とKPI(目標数値)を明確にする
- ステップ2:AIに任せる業務と人間が担う業務を切り分ける
- ステップ3:自社の課題に合ったAIツールを選定する
- ステップ4:スモールスタートで効果を検証・改善を繰り返す
- ステップ5:運用ルールを定め、オペレーターへの教育を行う
それぞれの注意点を把握して、自社のカスタマーサポートの業務効率化やコスト削減などを目指しましょう。
ステップ1:導入目的とKPI(目標数値)を明確にする
まず「何のためにAIを導入するのか」という目的を定めましょう。目的を明確にすることで、自社に適したツールを選択でき、効果的なAI活用につながります。
なぜなら、カスタマーサポートのAI活用シーンは多岐にわたるため、目的を定めなければ達成したいゴールと導入するツールにずれが生じてしまうからです。
例えば「平均応答時間を3分から1分に短縮する」「自己解決率を20%から40%に向上させる」など、具体的な数値目標(KPI)を設定することが重要です。
ステップ2:AIに任せる業務と人間が担う業務を切り分ける
次に、AIがどのような業務で活用できるのかを把握し、AIに任せる業務を明確にしましょう。AIには定型業務を任せ、人間は共感力や高度な判断が求められる業務に集中する切り分けが重要です。
すべての業務をAI化するのではなく、AIの得意なことと人間の得意なことを整理し、役割分担を行います。
例えば、以下のように業務を分担します。
- AIが担う業務:よくある質問への回答、データ入力
- 人間が担う業務:クレーム対応、複雑な個別相談
ステップ3:自社の課題に合ったAIツールを選定する
ステップ1で設定した目的にもとづき、自社の課題に合ったAIツール(チャットボット、ボイスボット、FAQシステムなど)を選定します。
AIツールの選定時には、以下のポイントを確認しておきましょう。
- 機能や費用対効果
- 既存のCRMや電話システムとの連携性
- セキュリティ対策
- 導入後のサポート体制
これらのように多角的な視点から比較検討することで、選定ミスの可能性を減らすことができます。
ステップ4:スモールスタートで効果を検証・改善を繰り返す
AIツールの選定が完了したら、全社に一度に導入するのではなく、まずは特定の問い合わせ内容や一部のチームに限定して試験的に導入しましょう。
スモールスタートをすることで、失敗時のコストを最小限に抑えられるためです。試験導入で得られたデータをもとに、設定したKPIが達成できるかを検証します。
そして、AIの回答精度をチューニングするなど改善を重ねながら、徐々に対象範囲を拡大し、導入の幅を広げていきましょう。
ステップ5:運用ルールを定め、オペレーターへの教育を行う
AI導入後の運用ルールを明確に定めておくことも重要です。例えば「AIが対応できない場合の有人への引き継ぎ手順」などを決めておきます。
また、オペレーターには「AIは仕事を奪うものではなく、業務を支援するパートナーであること」を伝え、AIリテラシーに関する教育を行いましょう。
さらに、従業員の具体的な使い方や連携方法についての実践トレーニングを実施することが必要です。
こうした教育を強化することで、組織全体のスキルアップと目標達成の支援につながります。
カスタマーサポートにAIを導入する前に知るべき失敗事例と回避策
カスタマーサポートにAIを導入する際に、多くの企業が陥りがちな失敗事例を3つ紹介します。
- 「AIに丸投げ」してしまい、複雑な問い合わせで顧客満足度が低下
- 有人対応へのエスカレーション(引き継ぎ)がスムーズにいかない
- 導入後のメンテナンスを怠り、AIの回答精度が劣化
それぞれの失敗を防ぐための回避策も解説しているので、導入前に確認しておきましょう。
「AIに丸投げ」してしまい、複雑な問い合わせで顧客満足度が低下
AIは定型的な問題には対応はできますが、複雑な問い合わせには十分に対応できない場合があります。
以下、事例と回避策です。
【事例】
AIの能力を過信し、本来人間が対応すべき複雑なクレームや個別相談までAIに任せてしまう。結果、画一的な対応となり、顧客の不満を増大させてしまう。
【回避策】
AIと人間の役割分担を明確にする。AIには一次対応や定型業務を任せ、感情的な対応や個別対応が求められる場面では、人間が責任を持って対応する体制を整える。
有人対応へのエスカレーション(引き継ぎ)がスムーズにいかない
AIが対応しきれない問い合わせやクレームの場合、スムーズに有人対応に切り替える仕組みを整える必要があります。
以下、事例と回避策です。
【事例】
AIが対応できないと判断した際に、有人チャットや電話へスムーズに引き継ぐ動線が設計されておらず、顧客は同じ説明を何度も繰り返すことになり、ストレスを感じてしまう。
【回避策】
AIとの対話履歴をオペレーターがシームレスに確認できるシステムを導入するなど、顧客が「オペレーターと話したい」と思った時に、ワンクリックで簡単に切り替えられる導線を分かりやすく設置する。
導入後のメンテナンスを怠り、AIの回答精度が劣化
AIは一度導入すれば終わりではありません。効果を最大限に引き出し、システムを長期間安定して使用するには、定期的なメンテナンスが不可欠です。
【事例】
AIを導入したまま放置し、FAQの更新や学習データの追加を行わないため、新商品やサービスの変更に対応できず、AIが古い情報や誤った情報を回答し続け、使えないシステムになってしまう。
【回避策】
AIの回答精度を定期的にモニタリングし、顧客からのフィードバックを基にFAQを更新・改善する。運用保守の体制をあらかじめ構築しておく。
まとめ:AIをパートナーに、顧客と従業員双方に選ばれるサポート体制へ
AIカスタマーサポートを成功させるためには、自社の課題と成熟度に合わせたAI活用法を選択し、明確な目的意識を持って段階的に導入を進めることが重要です。
AIを単なる効率化ツールではなく、オペレーターを支援する「パートナー」として位置づけることで、顧客と従業員の双方から選ばれる質の高いカスタマーサポート体制を実現できます。
そして、AIによる返信文の自動生成や分析といった機能は、「メールディーラー」のようなメール共有・管理システムの導入がおすすめです。
「メールディーラー」は、AIが要点入力だけで返信文案を作成する「カスタム生成」機能を搭載しています。これにより、対応品質の維持・向上と、オペレーターの負担軽減を同時に実現します。
以下では、カスタム生成のデモ画面で操作感をご確認いただけます。要点のメモからビジネスメールを一瞬で作成できる様子を体験いただけます。
※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス(以下「当社」といいます)または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。