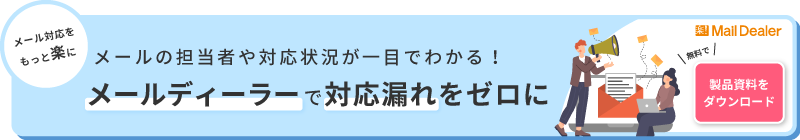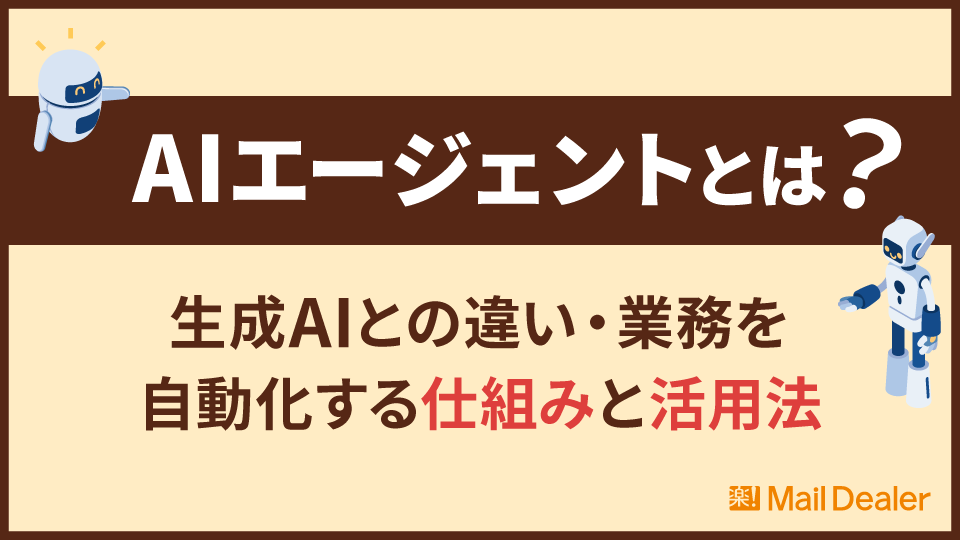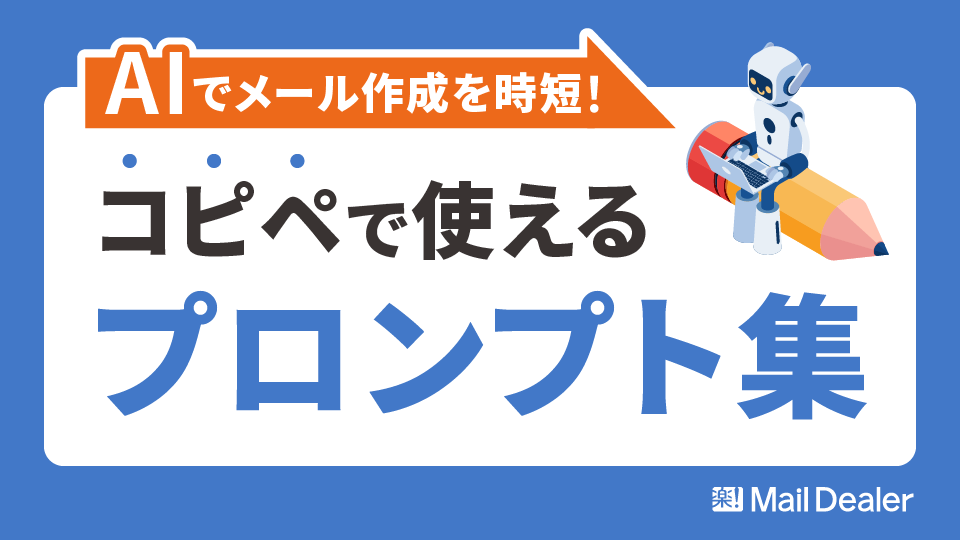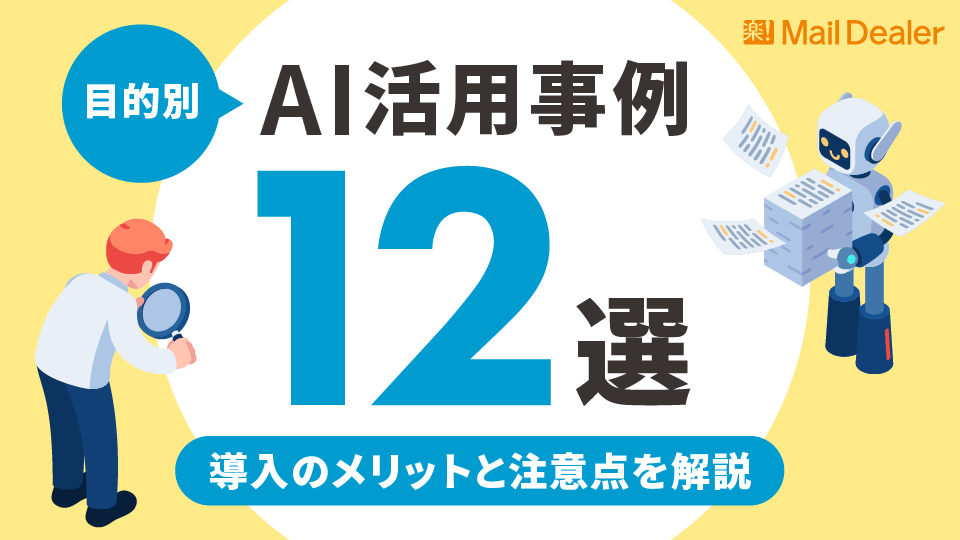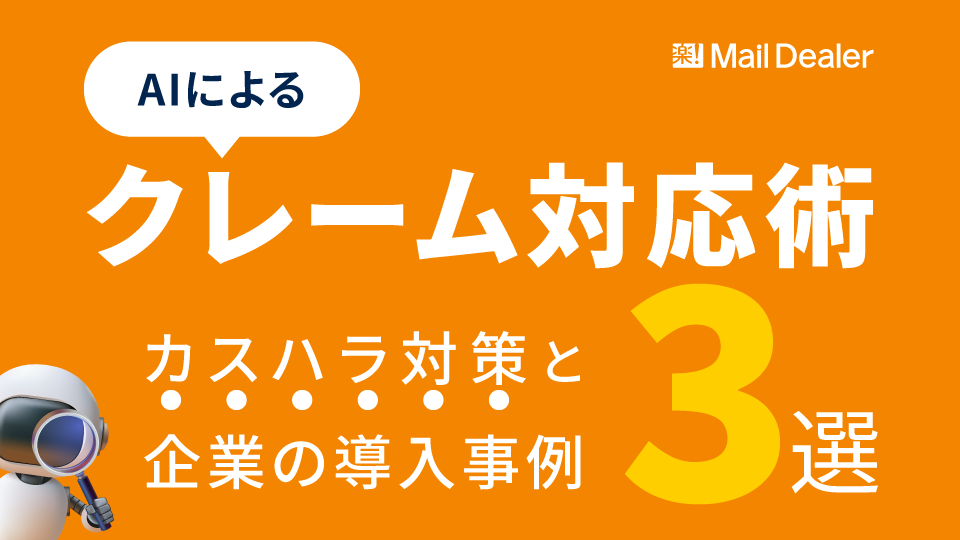
クレーム対応は、企業の成長に不可欠である一方、従業員の心身を疲弊させる大きな要因です。
特に近年問題視される「カスタマーハラスメント(カスハラ)」から、どう従業員を守るか。
その答えが「AIの戦略的活用」にあります。本記事では、AIを活用し、オペレーターを守りながら顧客満足度も向上させる、新しいクレーム対応の形を具体的に解説します。
なぜ今、AIによるクレーム対応が求められるのか?
なぜ今、多くの企業でAIによるクレーム対応が求められているのでしょうか。その背景を以下の3つに分けて解説します。
- オペレーターの負担
- 品質のばらつき
- カスタマーハラスメント問題
オペレーターの深刻な精神的負担と離職率の高さ
オペレーターの深刻な精神的負担と高い離職率は、企業にとって重要な経営課題の一つです。顧客対応のストレスが積み重なることで、モチベーションは低下し、早期離職を選択することも珍しくありません。実際、サービス業の離職率は他業種と比較して高い傾向にあります。
厚生労働省の「令和5年雇用動向調査結果の概況」(2023年)によると、コールセンターを含むサービス業の離職率は23.1%、パートタイマーに限定すると32.7%となり、全業種平均の15.4%と比較して高くなっています。
AIが人間のオペレーターの代わりに一次対応を自動化することで、オペレーターが過度なクレームの矢面に立つ回数を減らし、精神的負担を軽減する役割を果たします。
担当者による応対品質のばらつき
担当者のスキルや経験に依存する「応対品質のばらつき」も、AI導入が求められる大きな要因です。経験豊富なベテランは冷静に対応できても、経験が浅い担当者が対応を誤り、問題を深刻化させる「二次クレーム」へと発展するリスクが常に存在します。
この課題に対し、AIは適切な回答候補をリアルタイムで提示したり、トークスクリプトを案内したりすることができます。そのため、担当者の経験に関わらず、常に一定水準の正しい対応ができ、応対品質の標準化を実現できます。
社会問題化する「カスタマーハラスメント(カスハラ)」
近年、顧客による度を越えた要求や暴言といったカスハラが深刻な社会問題となっています。これは従業員の尊厳を傷つけ、安全を脅かす許されざる行為であり、企業には従業員を守るための具体的な対策を講じる社会的責任が求められています。
AIは通話内容から暴言などの危険なキーワードをリアルタイムで検知し、管理者に通知することが可能です。従業員を危険から守るための対策として、AIの活用に大きな期待が寄せられています。
AIによるクレーム対応で実現できること
AIは単に業務を自動化するだけでなく、オペレーターを支え、守り、そして企業全体の対応力を向上させるパートナーとなり得ます。
ここでは、AIがクレーム対応の現場で具体的にどのような役割を果たし、どのように貢献できるのかを以下の4つの主要な機能に分けて解説します。
- 一次対応の自動化
- オペレーターのリアルタイム支援
- クレームの検知とエスカレーション(音声認識/キーワード検知)
- 応対内容の分析とナレッジ化(テキストマイニング)
なお、ラクスのメール共有システム「メールディーラー」は「リスク検知」機能を搭載しており、メールを自動ラベリングし、管理者へアラート通知をしてくれます。
担当者は全メールを確認せずとも、対応すべき案件をリアルタイムで把握可能です。気になる方は無料で資料をダウンロードできますので、メールディーラーの強みや料金などをご確認ください。
一次対応の自動化(チャットボット/ボイスボット)
AIを搭載したチャットボットやボイスボットは、よくある質問や定型的な申し出などの一次対応を24時間365日、自動で受け付けます。
人間の感情に左右されることなく、常に一定の品質で迅速に対応できるのが強みです。
例えば、製品の操作方法に関する簡単な問い合わせや、返品手続きの案内などを自動化することで、顧客の初期段階の不満を解消します。
顧客満足度の向上が期待できるだけでなく、オペレーターはより複雑で、人間による共感や判断が求められる本質的なクレーム対応に集中できるようになり、業務全体の効率が飛躍的に向上します。
オペレーターのリアルタイム支援(感情分析/回答案サジェスト)
AIはオペレーターが顧客と対話している最中でも、リアルタイムで支援が可能です。
顧客の音声のトーンや話す速度、言葉の選び方から「怒り」「不満」「焦り」といった感情をAIが瞬時に分析し、オペレーターの画面にアラートを表示します。
さらに、AIは対話の内容をもとに過去の対応履歴やFAQデータベースから、その状況に適した回答候補やトークスクリプトを画面上に提示(サジェスト)します。
オペレーターは顧客の感情の起伏に冷静に対処でき、経験の浅い担当者でもベテランのような質の高い対応が可能になります。
クレームの検知とエスカレーション(音声認識/キーワード検知)
AIは、オペレーターを悪質なクレームやカスハラから守る「監視役」としても機能します。
AIは通話内容をリアルタイムでモニタリングし「暴言」「脅迫」「不当な要求」など、あらかじめ設定されたカスハラの可能性がある危険なキーワードを自動で検知できます。
危険を察知するとスーパーバイザーへ即座にアラートが通知されるため、迅速な対応や介入(エスカレーション)が可能です。
オペレーターの心理的安全性を確保しつつ、質の高いクレーム対応を実現できます。
応対内容の分析とナレッジ化(テキストマイニング)
AIによるクレーム対応では、すべての対応履歴をテキストデータとして蓄積し「テキストマイニング」によって分析できます。
これにより、どの製品や機能に関するクレームが増えているか、どの対応が顧客満足度の向上に効果的かといった傾向やパターンを可視化可能です。
分析結果は、製品やサービスの改善、FAQコンテンツの充実、オペレーター研修のナレッジ化などに活用でき、企業の対応力やサービス品質の向上につながります。
クレーム対応にAIを導入するメリット
AIの導入は、クレーム対応の現場における業務効率化やオペレーターの負担軽減に留まらず、コスト削減や顧客満足度の向上など、経営的なメリットもあります。
ここでは、AI導入がもたらす3つの主要なメリットを解説します。
オペレーターの離職率改善と採用・教育コストの削減
AI導入の大きなメリットの一つは、オペレーターの精神的負担を軽減し、職場定着率の向上につながる点です。
AIが一次対応の窓口として機能し、感情的なクレームに対する緩衝材となることで、オペレーターを過度なストレスから守ります。
これにより、従業員満足度(ES:Employee Satisfaction)が向上し、オペレーターの職場環境が整い、安心して長く働けます。
さらに、定着率が向上すれば、人材補充や新人教育コストの削減を通じて経営の安定化にも貢献するでしょう。
顧客満足度とブランドイメージの向上
AIと人間の連携により、迅速かつ一貫性のある高品質な顧客対応が可能となり、顧客満足度の向上につながります。
よくある問い合わせはAIが24時間体制で即座に解決し、複雑な問題はAIの支援を受けたオペレーターが丁寧に対応することで、顧客は「待たされない」「たらい回しにされない」というポジティブな体験を得られます。
また、企業がAI技術を活用して従業員を守り、クレームに毅然かつ真摯に対応する姿勢は、顧客や社会に信頼感を与えます。
こうした取り組みは、長期的に企業のブランドイメージを高め、顧客ロイヤリティの醸成にもつながる重要な投資と言えるでしょう。
顧客の声(VOC)分析によるサービス改善
AIを活用した顧客の声(VOC:Voice of Customer)分析は、クレームを貴重なフィードバックとしてとらえ、事業全体の品質を継続的に向上させます。
AIは、日々蓄積される膨大なクレームデータを、種類別、製品別、時期別など様々な切り口で自動的に分析し、その結果を可視化することが可能です。これにより、製品やサービスの根本的な欠陥や、顧客が不便に感じている点を正確に特定できます。
そして、データにもとづく改善サイクルを回すことで、事業全体の品質を継続的に向上させ、より顧客に選ばれる企業へと成長します。
クレーム対応・カスハラ対策へのAI導入事例
AIがクレーム対応やカスハラ対策の現場でどのように活用され、どのような成果を上げているのか、具体的な事例を4つ紹介します。
自社で導入する際のヒントとして、ぜひ参考にしてください。
ラクス:AIによるメールのクレーム検知と対応エスカレーション
ラクスのメール共有・管理システム「メールディーラー」の「リスク検知」機能は、受信したメールの本文をAIが自動で解析します。
クレームの可能性が高いと判断されたメールは、自動的に優先度を上げ、管理者に通知される仕組みになっています。
これにより、クレームの早期発見と、熟練した担当者による迅速な初期対応ができ、遅延や不適切な対応による二次クレームを防ぐことが可能です。
さらに、オペレーターの精神的負担を軽減する体制が整い、効率的で安心して対応できる環境が構築されます。
ソフトバンク:AIによる威圧的な音声の平穏化
ソフトバンクは、顧客からの電話口での怒鳴り声や強い口調を、AIがリアルタイムで穏やかな声色に変換してオペレーターに届ける技術「Emotion Canceling」を開発しました。
その結果、30%以上の怒り抑制効果が得られ、オペレーターが音声によって受ける心理的ストレスを軽減することに成功しました。
顧客が話している内容はそのままで声のトーンや抑揚を調整することで、オペレーターは冷静さを保ちながら、要求内容に集中できるようになります。
RevComm:AIによる会話の可視化とキーワード検知
RevCommのAI搭載型のIP電話サービス「MiiTel」は、通話内容をリアルタイムで文字起こしし、会話を可視化・分析するソリューションを提供しています。
事前に「不当な要求」などのNGキーワードを登録しておきます。通話中にこれらのキーワードが検知されると、管理者に自動でアラートが通知されるため、問題が深刻化する前に対応が可能です。
富士通:AIによるカスハラ体験研修ツール
富士通は、犯罪心理学の知見にもとづき、様々なパターンのカスハラをAIアバターが再現する研修ツールを開発しました。
オペレーターは、実際の顧客対応で起こりうるリアルなカスハラの状況を、安全な仮想環境で疑似体験できます。
体験後には、AIアバターから個々の対応内容にもとづいた客観的なフィードバックを受けることができ、実践的な対応スキルの習得につながります。
クレーム対応にAIを導入するための4ステップ
AI導入を成功させるためには、技術的な側面だけでなく、目的設定や運用体制の構築といった戦略的な視点が不可欠です。
ここでは、自社でAI導入をスムーズに進めるための手順を4つのステップに分けて解説します。
ステップ1:目的の明確化(何を守り、何を改善したいか)
最初に「なぜAIを導入するのか」という目的と、それを測るKPIを明確に定義しましょう。
「オペレーターの精神的負担の軽減」を優先するのか「二次クレームの発生率を削減する」のか、具体的な目標を定めます。
この目的とKPIが、導入プロジェクト全体の羅針盤となります。
ステップ2:AIと人間の役割分担の設計
ステップ2では、AIと人間の役割分担を設計します。
AIは万能ではなく、得意なことと不得意なことがあります。AIと人間のそれぞれの強みを活かした役割分担を設計することが重要です。
例えば、定型的な問い合わせへの回答やデータ分析はAIに任せ、人間は最終的な謝罪や共感を示す対話に集中する、といった形が考えられます。
ステップ3:ツールの選定とスモールスタート(PoC)
ステップ3は、設定した目的に合った機能を持つAIツールを選定し、一部チームや特定のクレーム種別に限定して試験導入(PoC)する段階です。
PoCを通じて「自社の業務に本当にフィットするか」「期待した効果が得られるか」を小規模で検証します。
ここで得られた結果や課題を基に、本格導入に向けて計画を修正・改善していきます。
ステップ4:運用ルールの策定と継続的な改善
ステップ4では、AIが対応できない場合の人間への引き継ぎルールを明確に定めます。
特に「AIでは対応しきれない場合に、どのタイミングで、誰に、どのように引き継ぐのか」というエスカレーションルールは詳細に定める必要があります。
また、導入後も新たなクレームの傾向をAIに学習させたり、オペレーターからのフィードバックを反映させたりして、継続的に精度を改善する運用体制を構築することも重要です。
AIの導入前に知るべき注意点と「AIに任せてはいけないこと」
AIはクレーム対応の強力な武器となりますが、その能力には限界があり、万能の解決策ではありません。AIの限界を正しく理解し、導入前に注意すべき点と「AIに任せてはいけないこと」を見ていきましょう。
注意点:セキュリティと個人情報の厳重な管理
AIを導入する際は、情報漏洩のリスクを理解し、セキュリティ対策が万全なツールを選定する必要があります。
クレーム対応で取り扱う音声やテキストデータには、氏名、住所、連絡先などの個人情報が多く含まれています。
個人情報の流出は、社会的信用の喪失にとどまらず、法的責任を問われるリスクがあります。提供元のセキュリティ対策が十分であるAIツールを導入することが重要です。
AIに任せてはいけないこと1:最終的な謝罪と共感の表明
最終的な謝罪と共感の表明は、人間が担うべき重要な役割です。
強い不満や悲しみを抱える顧客が最終的に求めているのは、テンプレート通りの謝罪の言葉ではなく、心からの共感と温かみのあるコミュニケーションです。
深刻なクレーム対応や謝罪対応、緊急対応をAIに任せることは、かえってトラブルを深刻化させ、企業の信用損失を招く可能性があります。
AIに任せてはいけないこと2:前例のない複雑な問題解決
前例のない複雑な問題解決は、AIが苦手とする分野です。
AIの基本的な動作原理は、過去に蓄積された膨大なデータからパターンを学習し、それにもとづいて答えを導き出すことです。そのため、前例のない複雑なトラブルや、複数の部署にまたがる問題の解決には向いていません。
前例のない問題解決では、人間の柔軟な思考力と創造的な問題解決能力が不可欠です。
まとめ:AIを活用してメール対応から始める新しいクレーム対策
本記事で解説した通り、AIはオペレーターを過度な精神的負担や悪質なカスハラから守る強力な「盾」となります。
AIが定型業務やデータ分析を担うことで、人間は本来持つべき共感力や問題解決能力を最大限に発揮できるようになります。
そして、この「AIと人間の協業」を、多くの企業にとって主要な顧客接点であるメール対応の現場で具体的に実現するのが、AI機能を搭載したメール共有・管理システム「メールディーラー」です。オペレーターを守り、対応品質を向上させる具体的な機能を見ていきましょう。
チームのミスを防ぎ、炎上リスクを低減する管理基盤
17年連続売上シェアNo.1を獲得している「メールディーラー」は、チームのメール対応状況を全員で可視化できます。
社内の共有アドレスに届くメール一通ごとの「対応状況」や「担当者」をチーム全員で可視化することができるため、「このメール誰か対応した?」といった無駄な確認作業や、致命的な返信漏れ・二重対応をシステムで防止します。
担当者不在時でも、他の人が対応履歴を遡れるため、業務の属人化を防ぎ、安定した顧客対応の基盤を構築します。
最新のAI機能でオペレーターを守り、品質を向上しよう
「メールディーラー」は、AIがクレームの可能性を検知する「リスク検知」機能を搭載しています。これにより、対応が遅れてはならないメールを管理者に即時通知します。
さらに、返信文案を自動生成する「カスタム生成」機能が、担当者のスキルに依存しない、迅速で質の高い対応を実現します。
要点入力だけで返信文を自動生成する「カスタム生成」は、無料のデモ画面で今すぐ操作感を確かめていただけます。
※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス(以下「当社」といいます)または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。