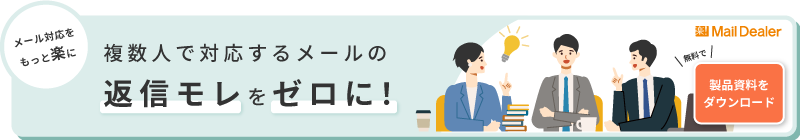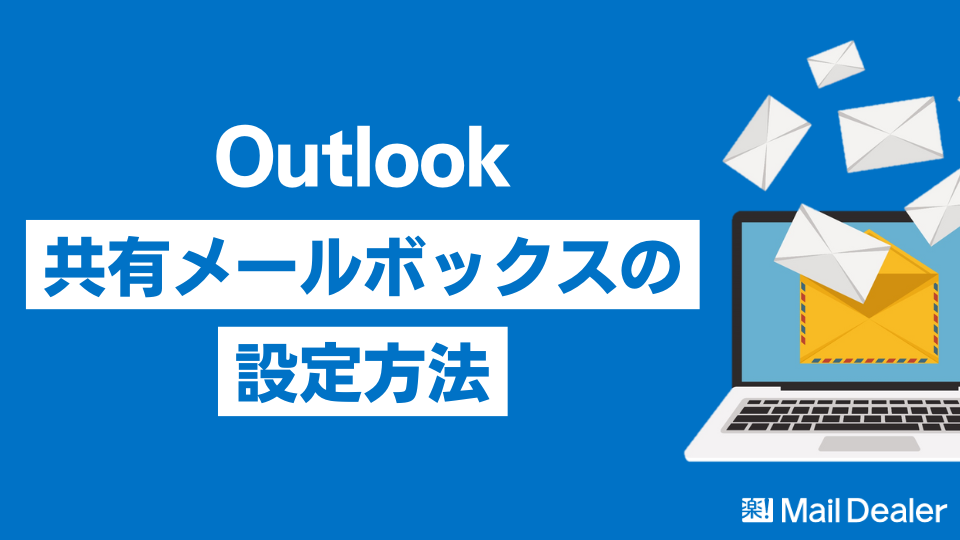現状のヘルプデスク業務に課題を感じたら、改善に向けてヘルプデスクツールの導入を検討してはいかがでしょうか。ヘルプデスク業務のリソース不足や、サポート品質の低下を解決するためにはツールを活用するのがおすすめです。
本記事では、ヘルプデスクツールを導入するメリットや、ツール選びのポイントなどをお伝えします。ヘルプデスクなどの問い合わせ対応に関して課題解決を目指す担当者は、ぜひ参考にしてください。
ヘルプデスクツールの基礎知識
最初にヘルプデスクツールで実現できることや、主な役割・機能などの基礎知識を解説します。導入を検討するための基本知識を押さえておきましょう。
ヘルプデスクツールとは?
ヘルプデスクツールとは、顧客からの問い合わせ対応業務を効率化させるツールを指します。
導入によって効率化が期待できるのは、製品やサービスのトラブル対処、質問応対などの業務です。これらの業務で取り扱う情報をシステム上で管理することで、対応漏れや二重対応といったヒューマンエラーの防止にもつながります。
現状、問い合わせ対応業務に関する課題を抱えている場合、ツールを活用することで改善できる可能性があります。
ヘルプデスクツールの役割
ヘルプデスクツールの役割は、大きく「問い合わせに関する情報の記録や共有」と「問い合わせ対応の品質とスピードの向上」の2つに大別できます。
問い合わせに関する情報の記録や共有
お客様からの問い合わせに正しく回答するには、情報の正確な記録やシームレスな共有は必須となります。ヘルプデスクツールは、問い合わせが発生した日付・問い合わせ内容・対応者といった詳細情報を登録することができます。また、データとしてシステム上に蓄積されているので、スムーズな対応履歴の閲覧および検索が可能となり、お客様にストレスを与えることなく、情報共有することも可能になります。
問い合わせ対応の品質とスピードの向上
ヘルプデスク担当者の問い合わせ対応をサポートすることで、品質やスピードを向上させることができます。
具体的には、コールセンターの電話応対で用いられるトークスクリプトや、メール定型文のテンプレートなどを管理します。よくある質問を管理する「FAQシステム」や、チャット機能でコミュニケーションを行う「チャットボット」なども該当します。
ヘルプデスクツールが具体的にできること
製品によって搭載されている機能はやや異なるものの、ヘルプデスクツールを活用するとできることは、主に以下のとおりです。
- 情報の蓄積
- 回答が難しいときの対応
- 対応の自動化
- レポート作成・データ分析
- テンプレート作成と呼び出し
- お客様からの問い合わせ内容の整理
それぞれの機能について解説します。
情報の蓄積
ヘルプデスクツールでは、これまでに寄せられたお客様や社内からの問い合わせに関する情報を蓄積できます。
過去に問い合わせを受けたお客様から再度連絡を受けた際に、担当者が異なっていても一から内容を聞かなくて済むほか、同じような問題が発生した際に迅速な対応を取れるでしょう。
また、これまで多く寄せられた質問をデータベース化しFAQとして対応することで、対応の効率化が実現します。蓄積された情報から、対応内容に関する改善点を洗い出すことにも活用できます。
回答が難しいときの対応
オペレーターや担当者は、寄せられたすべての問い合わせに即座に回答できるわけではありません。担当外の内容の問い合わせを受けたり、経験が浅く知識が十分に備わっていなかったりすると、その場で適切な回答ができないこともあるでしょう。
オペレーターや担当者が質問に回答できない場合に、ヘルプデスクツールの「エスカレーション機能」を使って、正確に回答できるオペレーターに引き継ぐことが可能です。エスカレーション機能とは、現場のオペレーターや担当者が回答できない問い合わせを、専門的な知識を持つ上位の担当者に引き継ぐ機能です。
対応の自動化
ヘルプデスクツールの中には、基本的な内容や、繰り返し寄せられる問い合わせ内容などに対して、AIによる自動対応ができる製品もあります。
「チャットボット」が搭載されている製品では、お客様がチャットのウィンドウ画面に問い合わせ内容を入力すると、AIが自動的に回答を生成し表示します。これによりオペレーターなどの業務の軽減や、対応の迅速化が期待できるでしょう。
レポート作成・データ分析
ヘルプデスクのレポート作成機能とは、問い合わせ内容に関するデータを収集・分析し、レポートを作成する機能です。
たとえば、「対応中の問い合わせはどの程度あるのか」「回答期日を超過している問い合わせはいくつあり、誰が担当なのか」といったデータをレポートとして作成し、表示できる製品もあります。
テンプレート作成と呼び出し
ヘルプデスクの製品によっては、テンプレート作成と呼び出し機能が搭載されています。よくある回答のテンプレートを作成し、必要に応じて呼び出すことが可能です。
そのため、ソフトウェアのインストール方法や契約更新の流れ、商品を返品する手順などの頻繁に寄せられる問い合わせへの回答をテンプレート化しておくと、業務効率が向上します。
お客様からの問い合わせ内容の整理
お客様からの問い合わせをシステム内の各フォルダに内容別に分類し、整理する機能を持つヘルプデスクツールもあります。
それにより、オペレーターや担当者は素早く必要な情報を探し出せるため、対応速度や精度を向上できるでしょう。
ヘルプデスクツールを選定するポイント
ヘルプデスクツールの導入を成功へ導くためのポイントをお伝えします。ツールの選び方では、以下の5つのポイントを意識してみましょう。
機能
問い合わせ対応業務において、効率化したい課題を解決できる機能が備わっているかどうかは選定ポイントのなかでも特に重要です。
レポート作成機能や自動回答ができる機能、テンプレート作成機能などは、多くのヘルプデスクツールに備わっています。しかし、どのような機能を重視すべきかは、業種や会社の規模などによって異なります。
たとえば、お客様とのリアルタイムなコミュニケーションが求められている場合は、チャット機能や電話ポート機能を優先しましょう。また、問い合わせ数が非常に多い場合は、自動化ツールを活用すると業務負荷を軽減できます。
自社にとって優先順位の高い機能を見極め、必要な機能が充実した製品を選びましょう。
操作性
複数のヘルプデスクツールを比較する際は、操作性の高さも注目すべきポイントです。たとえ高機能なヘルプデスクツールを導入したとしても、現場の担当者やオペレーターがなかなか使いこなせない場合、業務がかえって非効率になってしまう可能性もあり得ます。
直感的なインターフェースを持つヘルプデスクツールであれば、問い合わせにより迅速に対応できるようになるでしょう。また、使えるようになるまで時間を要さない製品の場合、トレーニング期間を短縮でき、生産性の向上に寄与します。
ほかのツールとの連携性
ほかのツールとの連携性も、ヘルプデスクツールを選ぶ際にチェックしておきたいポイントです。
たとえば、導入時は問い合わせ管理システムのみが必要であっても、導入後しばらくするとFAQシステムやチャットボットなどが必要になるといったケースも珍しくありません。
そのため、導入時にすでに存在する既存のツールとの連携だけでなく、将来導入する可能性のあるツールとの互換性を考慮して製品を選ぶのが賢明です。将来的に必要なツールと連携ができないと、業務に支障をきたしてしまいかねません。
ヘルプデスクツールとそのほかの基幹ツールと連携ができれば、ヘルプデスクチームは複数のプラットフォームを行き来する必要がありません。一元的なインターフェースで業務ができると、作業効率の向上だけでなく、お客様満足度の向上にもつながります。
サポート体制
ヘルプデスクツールが社内に定着して問題なく活用できるようになるまでには、一定の時間がかかります。サービスによっては導入サポートや運用サポートが無料で提供されているため、ぜひ利用しましょう。
導入実績が豊富でサポートが充実したベンダーなら、ノウハウを生かして手厚くフォローしてもらえる点で安心です。社内の担当者の負担軽減につなげるためにも、サポート体制の充実度をチェックしてことがおすすめです。
【問い合わせ管理におすすめ】ヘルプデスクツール10選
ヘルプデスクツールと一口にいっても、問い合わせ管理に強みを持つタイプやCRM(顧客関係管理)機能を持つタイプ、生成AIを活用したタイプなどさまざまな種類が存在します。
ここからは、とくに問い合わせ管理におすすめのヘルプデスクツールを紹介します。
1.メールディーラー(株式会社ラクス)

クラウド型のメール共有管理システムです。共有メールを一元管理して、対応状況のステータス表示、対応履歴の一覧表示により情報をリアルタイムで可視化します。
対応漏れや二重対応の防止はもちろん、メール管理に役立つ機能が網羅的に備わっていることが特長です。
-
<メールディーラーの特徴>
- 共有メールの一元管理で効率化を実現
- 対応状況のステータス表示、対応履歴の一覧表示で社内の連携を強化
- 導入設定から運用定着まで電話やメールにて専任スタッフがサポート
-
<メールディーラーの料金プラン>
- 初期費用は要問い合わせ
- 月額費用は要問い合わせ
- 無料トライアルあり
2.Zendesk(株式会社Zendesk)

マルチチャネルで利用可能なカスタマーサービスソリューションです。独自のヘルプセンターを構築し、FAQのセルフサービス化を推進できます。AIとチャットボットによる顧客対応の自動化も可能です。
-
<Zendeskの特徴>
- 電話、チャット、SNS、メールなどのマルチチャネルに対応
- ヘルプセンター構築により担当者の業務負担を軽減
- 顧客対応を自動化
-
<Zendeskの料金プラン>
- Suite Teamプランは月額$49/1名(年払い)
- Suite Growthlプランは月額$79/1名(年払い)
- Suite Professionalプランは月額$99/1名(年払い)
- 無料トライアルあり
3.Freshdesk(Freshworks)

顧客対応をオムニチャネル化するカスタマーサポートソフトウェアです。複数のコミュニケーション手段を統合し、サポートの柔軟性を高めます。さらにプラットフォームのFreshworks NEOと連携すれば、多数のアプリと連携可能です。
-
<Freshdeskの特徴>
- オムニチャネル化で顧客体験を向上
- ライブチャット、Web、モバイル、コンタクトセンターなど複数のサポートを統合
- アプリ連携で幅広い顧客ニーズに対応
-
<Freshdeskの料金プラン>
- Growthプランは月額$15/1名(年払い)
- Proプランは月額$49/1名(年払い)
- Enterpriseプランは月額$79/1名(年払い)
- 無料トライアルあり
4.Zoho Desk(Zoho Corporation)

複数チャネルからの問い合わせを一元管理するカスタマーサポートツールです。マニュアル活用に役立つナレッジベース機能を搭載。さらに顧客満足度調査の機能も搭載し、対応品質の向上に寄与します。
-
<Zoho Deskの特徴>
- メール、電話、チャット、SNS、Webサイト経由の問い合わせを一元化
- ナレッジベースで業務の知見やマニュアルの活用を促進
- 自動の顧客満足度調査で対応品質を向上
-
<Zoho Deskの料金プラン>
- エクスプレスプランは月額税抜800円/人(年払い)
- スタンダードプランは月額税抜1,680円/人(年払い)
- プロフェッショナルプランは月額税抜2,760円/人(年払い)
- エンタープライズプランは月額税抜4,800円/人(年払い)
- 無料トライアルあり
5.Service Cloud(Salesforce)

カスタマーサポート向けのプラットフォームです。ナレッジ管理やサービスプロセス自動化などの多彩な機能を搭載しています。AIの活用により、生産性向上や顧客対応のパーソナライズを実現します。
-
<Service Cloudの特徴>
- ナレッジ管理で生産性を向上
- 簡単な操作のみでサービスプロセスを自動化
- AI活用で最適なカスタマーサポートを提供
-
<Service Cloudの料金プラン>
- 初期費用は問い合わせ
- Essentialsプランは月額税抜3,000円(年払い)
- Professionalプランは月額税抜9,000円(年払い)
- Enterpriseプランは月額税抜18,000円(年払い)
- Unlimitedプランは月額税抜36,000円(年払い)
- 無料トライアルあり
6.Tayori(株式会社PR TIMES)

ノーコードで簡単にテンプレートを作成できるカスタマーサポートツールです。フォーム・FAQ・アンケート・チャットの4種類を作成・運用できます。直感的に使いやすい操作性も特長となっています。
-
<Tayoriの特徴>
- ノーコードのため専門知識が不要で使いやすい
- テンプレートが豊富に用意されている
- 導入時の準備や費用の負担が少ない
-
<Tayoriの料金プラン>
- 初期費用は無料
- プロフェッショナルプランは月額税抜7,400円(年払い)
- スタータープランは月額税抜3,400円(年払い)
- 無料でお試し可能なフリープランあり
7.Yaritori(Onebox株式会社)
月額1,980円というリーズナブルな料金で利用できる、問い合わせメールの対応効率化に特化したヘルプデスクツールです。シンプルで使いやすいインターフェースで、はじめての導入に適しています。
メールを見ながらのリアルタイムでのチャットによって、対応方針の相談や情報共有ができるため、メールの転送や口頭での確認などの工程を省けます。
-
<Yaritoriの特徴>
- AIによる文章の自動生成や翻訳・丁寧語への変換が可能
- クレームメールの自動検出機能あり
- 充実したお客様サポートを受けられる
-
<Yaritoriの料金プラン>
- 月額費用は月額税抜1,980円/人~
- 初期費用完全無料
- 無料トライアル7日間
- 最低契約期間なし
8.メールワイズ(サイボウズ株式会社)

共有メールの送受信から管理まで可能なメール共有システムです。メールアプリケーションでは複数アドレスの一元管理が可能。コメント機能を搭載し、社内のコミュニケーションを充実化します。
-
<メールワイズの特徴>
- メールアプリケーションで送受信や管理を効率化
- コメント機能で社内向けの指示や引き継ぎがスムーズ
- 業務改善プラットフォーム「kintone」との連携が可能
-
<メールワイズの料金プラン>
- クラウド版は初期費用無料
- スタンダードコースは月額500円/人
- プレミアムコースは月額1,500円/人
- 無料トライアルあり
9.Optimal Remote(株式会社オプティム)
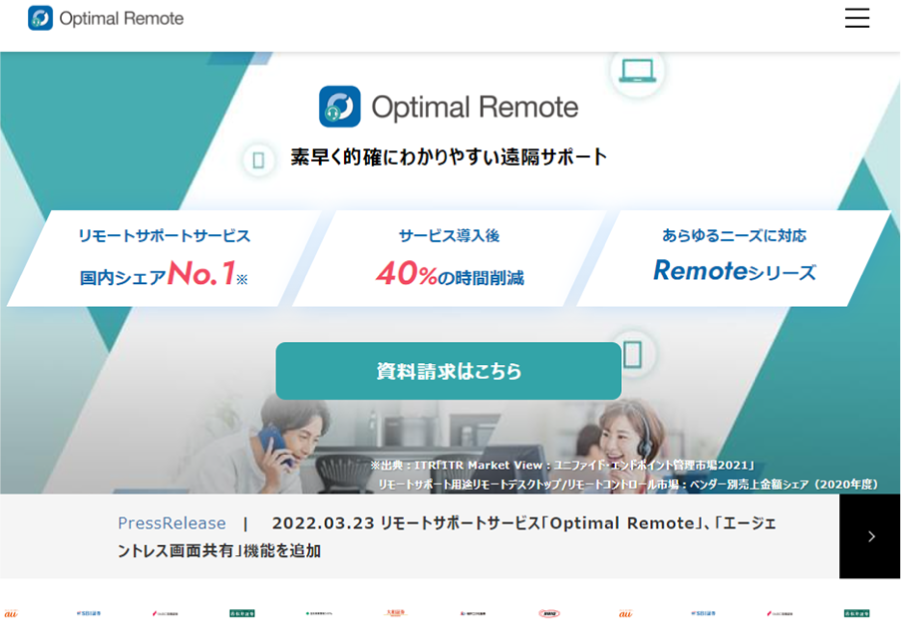
リアルタイムでの画面共有を実現する遠隔サポートサービスです。問い合わせ対応を視覚的にサポートする機能が搭載されています。サポート業務の時間短縮や満足度向上が期待できます。
-
<Optimal Remoteの特徴>
- 顧客と対応者の画面をリアルタイムで共有
- 赤ペン・指差し機能で対応者の説明作業をサポート
- 顧客の画面を代理で操作する機能も搭載
-
<Optimal Remoteの料金プラン>
- 初期費用は問い合わせ
- 月額費用は問い合わせ
10.LMIS(株式会社ユニリタ)

ヘルプデスク業務を効率化するサービスマネジメントプラットフォームです。問い合わせ対応のナレッジを集約して、品質の標準化につなげます。レポートやダッシュボードによるデータの可視化や分析も可能です。
-
<LMISの特徴>
- ナレッジを集約して社内の情報共有スピードを向上
- FAQの改善で問い合わせの自己解決をサポート
- 豊富なレポート・ダッシュボードのテンプレートで必要なデータを可視化
-
<LMISの料金プラン>
- 初期費用は300,000円
- 月額費用は100,000円
- 無料トライアルあり
【CRM型】ヘルプデスクツール3選
CRM型ヘルプデスクツールとは、顧客情報管理や問い合わせチャネルの一元管理、応対履歴などの機能を備えたヘルプデスクツールのことです。おすすめのCRM型ヘルプデスクツールをご紹介します。
1.FastHelp5(テクマトリックス株式会社)

コンタクトセンターやコールセンターに適した顧客管理システムです。ナレッジ検索機能で問い合わせ対応をサポートし、効率化と品質向上につなげます。対応漏れを防止するアラート機能も充実しています。
-
<FastHelp5の特徴>
- 業務画面は各自でカスタマイズ可能
- ナレッジやFAQの検索による問い合わせ対応を効率化
- 多彩なアラート機能でヒューマンエラーを防止
-
<FastHelp5の料金プラン>
- 初期費用は問い合わせ
- 月額費用は問い合わせ
3.Zoho CRM(ゾーホージャパン株式会社)
営業部門の問題解決のために開発されたCRM・SFAツールです。顧客管理や商談管理、営業担当者の割り当てといったCRMに必要な機能が一通り揃っているにもかかわらず、月額1,680円からという手頃な価格で利用できることが魅力です。
商談の状況や営業活動の可視化によって担当者がやるべきことを明確にでき、さらに自動化による業務効率化によって企業の業績向上を力強くサポートします。
-
<Zoho CRMの特徴>
- 「マルチチャネルコミュニケーション機能」でお客様とのやり取りを一元管理
- 商談の角度や見込みをAIが予測
- ワークフロー機能により定型的な業務を自動化
-
<Zoho CRMの料金プラン>
- 月額費用は税抜1,680円/人~(年間契約)
- 無料トライアルあり
4.InfiniTalk(ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社)
顧客情報管理と応対履歴の一元管理ができる、ヘルプデスク向けCRMツールです。CRMと連携することで、オペレーターのPCには応答前にCRM画面が表示され、 どのようなお客様からの入電なのかを把握してから応答できます。
クラウド版は、基本プランに加えてさまざまなオプションの追加が可能です。たとえば、通話録音データをテキスト化したり、VPNや専用線などの帯域幅の広いデータ回線を使用した接続構成を組めたります。
-
<InfiniTalkの特徴>
- スモールスタートが可能
- PBXなどの専門知識がなくても使える視認性に優れたユーザーインターフェース
- APIとして「AGI」「AMI」が利用可能
-
<InfiniTalkの料金プラン>
- 月額費用は問い合わせ
- 初期費用は無料(クラウド型)
【生成AIを活用】ヘルプデスクツール3選
ここからは、生成AIを活用した業務効率化に役立つヘルプデスクツールをご紹介します。
1.PKSHA AI ヘルプデスク(株式会社PKSHA Workplace)
独自AI×生成AIを活用し、業務を自動化するヘルプデスクツールです。寄せられた問い合わせ内容はTeams内に集約され、チャットボットがFAQ・社内ドキュメント検索・有人応対などから、質問内容に合った解決方法につなげてくれます。
-
<PKSHA AI ヘルプデスクの特徴>
- AI研究・製品開発を手がけるPKSHA Technologyのグループ会社が提供
- FAQが0件でも導入可能
- FAQ化の必要性がありそうな問い合わせを抽出し、提案する「FAQ提案機能」を搭載
-
<PKSHA AI ヘルプデスクの料金プラン>
- 初期費用は問い合わせ
- 月額費用は問い合わせ
2.AIヘルプデスクソリューション(NTTデータビジネスシステムズ)
質問の意味を理解する、高性能AIを活用した社内問い合わせ対応向けヘルプデスクツールです。思考型AIエンジンを搭載したポータルサイトを構築し、窓口として利用できるため、問い合わせ対応の負担が軽減されます。
-
<AIヘルプデスクソリューションの特徴>
- Web検索のようなシンプルな入力で詳細回答を入手
- QA一覧の登録のみで利用スタート可
- 1つの回答の入力のみで、言い回しが違う検索内容でも意味を解釈して回答が可能
-
<PKSHA AI ヘルプデスクの料金プラン>
- 初期費用は問い合わせ
- 月額費用は問い合わせ
3.AI-FAQボット(株式会社LisB(エルイズビー))
事前学習不要で利用できる、チャットボットツールです。チャット画面で入力された口語調の自然文を理解して、適切な回答を自動的に導き出し出します。
初回にExcelで質問と回答を設定しておけば後は自動で対応していくため、使用開始にあたって大きな作業負荷がかかりません。社内向け、社外向けのいずれの場面でも利用できます。
-
<AI-FAQボットの特徴>
- ビジネスチャット・グループウェアと連携
- カテゴリーボタンの自動生成が可能
- 言葉の揺れを自動的に学習するため2回目からの回答精度が向上
-
<AI-FAQボットの料金プラン>
- 月額費用は税抜30,000円~
- 初期費用はなし
- 無料トライアルあり
ヘルプデスクツールの導入を検討すべきタイミング
企業はどのような課題に対してヘルプデスクツールの導入を検討すれば良いのでしょうか。
ツール導入によって課題の改善につながる可能性がある具体的なシーンを紹介します。
ヘルプデスクに割り当てるリソースが不足している
規模が小さめの企業では、ヘルプデスクの専任者がいないケースも少なくありません。IT機器の知識を持つ情報システムの担当者がヘルプデスクを兼任している場合もあるでしょう。
一方で、マニュアルが整備できていなかったり、既存のマニュアルが活用されていなかったりすることも。
こうしたシーンではヘルプデスクツールによる効率化が有効です。現状のまま放置すれば、担当者の負担が増え過ぎて対応が追い付かなくなるリスクがあります。リソース不足による対応方法の属人化にも注意が必要です。
自社の製品・サービスの評判や口コミが悪化している
顧客から寄せられる問い合わせで、自社の製品・サービスに関するトラブルやクレームが増加傾向にある場合、ヘルプデスクツールの導入を検討しましょう。
企業はトラブルやクレームの原因を迅速に分析して、問題解決へ向けて取り組まなければなりません。対策がおろそかになれば、多数の問い合わせが集中して顧客への返答が遅れたり、担当者の業務負担が増加したりする恐れも。ヒューマンエラーによりさらなるトラブルやクレームの発生を招き、悪循環に陥ってしまうリスクがあります。
ヘルプデスクツールを導入するメリット
問い合わせ対応に関する課題を抱えているなら、ヘルプデスクツールを活用した解決策を検討しましょう。ここでは、ツールの導入で期待できるメリットを解説します。
問い合わせ対応業務の効率化につながる
ヘルプデスクツールを活用すると、業務そのものを自動化したり、テンプレートを使用して業務負担を抑えたりできます。
たとえば、電話の自動応答システムによる顧客案内の自動化や、メール定型文による返信工数の削減などが挙げられます。業務効率化を実現するには、自社が求める機能が搭載された最適なツールを選ぶことが大切です。
問い合わせ業務の属人性を低下できる
ヘルプデスクツールの導入によって、問い合わせ業務の属人性の低下が期待できます。ヘルプデスクでは、特定の分野について、その内容に詳しい担当者のみが回答しているケースも散見されます。
しかし、このように問い合わせ業務が属人化していると、当該担当者が不在の日は回答できず、お客様を待たせてしまうことになりかねません。
ヘルプデスクツールは回答をデータベース化できるため、担当者が不在の日であっても問題なく問い合わせ対応を行えます。
顧客情報や問い合わせ内容の管理・共有が楽になる
ヘルプデスクツールのシステム上では、情報の管理・共有が簡単にできます。
ヘルプデスクの人手不足が原因で、目の前の問い合わせ対応に追われてしまい、複数の担当者同士で共有するべき情報があっても、それができないことも珍しくありません。
しかし、過去の問い合わせ履歴を確認できるようになれば、担当者の異動や離職が生じても、スムーズに引き継ぎがしやすくなるでしょう。
また、担当者の不在時に別の担当者が代理で対応するなど、情報共有の強化によりチームでの柔軟な対応を実現できます。
データ分析に基づく運用効率化が期待できる
ヘルプデスクツールに蓄積されたデータは、分析してヘルプデスク業務の運用改善に役立てることが可能です。
たとえば、自社の問い合わせ内容や件数、問い合わせが集中する時期、対応に要した時間などを分析して対策を実施すれば、課題解決につなげられます。
運用における課題の明確化や、ワークフローの見直しに効果的です。
問い合わせ対応に関するノウハウを蓄積できる
問い合わせ対応に関するノウハウを蓄積でき、問い合わせ内容はもちろん、それらの問い合わせにどのように対応してきたかについてのデータも残せます。過去の対応方法を確認すれば、経験の浅い担当者であっても迅速かつ適切な対応を取れるでしょう。
担当者の人事評価に役立つ可能性がある
ヘルプデスクツールによって担当者の仕事が可視化されると、社内の人事評価を適正化しやすくなります。
一般的にヘルプデスク・サービスデスク・カスタマーサポートなどの業務は仕事の成果を正確に把握するのが難しい傾向にあります。システム上で対応状況を数値として表示させることで、従来よりも人事評価の基準を設定しやすくなるでしょう。
ヘルプデスクツールを導入するデメリット・注意点
ヘルプデスクツールを活用して問い合わせ対応を向上させるには、どんな点に留意すべきでしょうか。押さえておきたいデメリットや注意点をお伝えします。
問い合わせの応答が画一的になり過ぎる恐れがある
ヘルプデスクツールは自動化機能や豊富なテンプレートなどが強みです。ただし、機能面に頼り過ぎると、問い合わせ対応が応用のきかないやり取りにもなりかねません。
導入後は定期的に自動化の設定やテンプレートの使用方法を見直し、適切な活用につなげる必要があります。
更新とメンテナンスが求められる
更新とメンテナンスが求められる点も、ヘルプデスクツールを導入するデメリットといえるでしょう。ヘルプデスクツールは、セキュリティの強化や新機能の追加を理由として定期的な更新を求められることがあります。
更新中は業務がストップしてしまうリスクがあることに、注意が必要です。
ツールの保守や運用に継続的なコストがかかる
ヘルプデスクツールを導入するなら、長期的な運用を前提に、保守や運用にかかるコストを考慮して選定することが重要です。
初期費用やカスタマイズ費用などの導入コストだけでなく、月額費用やメンテナンス費用、運用に必要な人員なども含めて、事前に費用を算出しておきましょう。
データの漏洩や不正アクセスのリスクがある
ヘルプデスクツールを利用する際は、データの漏洩や不正アクセスが起こらないように注意しましょう。
顧客情報や問い合わせ内容を保存するという性質上、十分なセキュリティ対策が欠かせません。データの漏洩や不正アクセスが起きると、会社としての信頼を失ってしまうでしょう。
ヘルプデスクツールの導入前に、ツールのセキュリティ対策が十分かどうかを確認したり、ツールの使用状況を定期的に監査し、脆弱性を早期に発見・対処したりするなどの対策が必要です。
ヘルプデスクツールで問い合わせ対応の課題を解決
ヘルプデスクツールの基礎知識から、選定するポイントや導入するメリットまでお伝えしました。
ツールの活用によって問い合わせ対応が効率化され、社内の情報共有がスムーズになれば、現状のヘルプデスク業務の課題を改善できる可能性があります。導入後は継続的にコストが発生するため、自社の目的に適したツールを選定し、ベンダーのサポートを受けながら最適な運用体制を整備していきましょう。
※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス(以下「当社」といいます)または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。