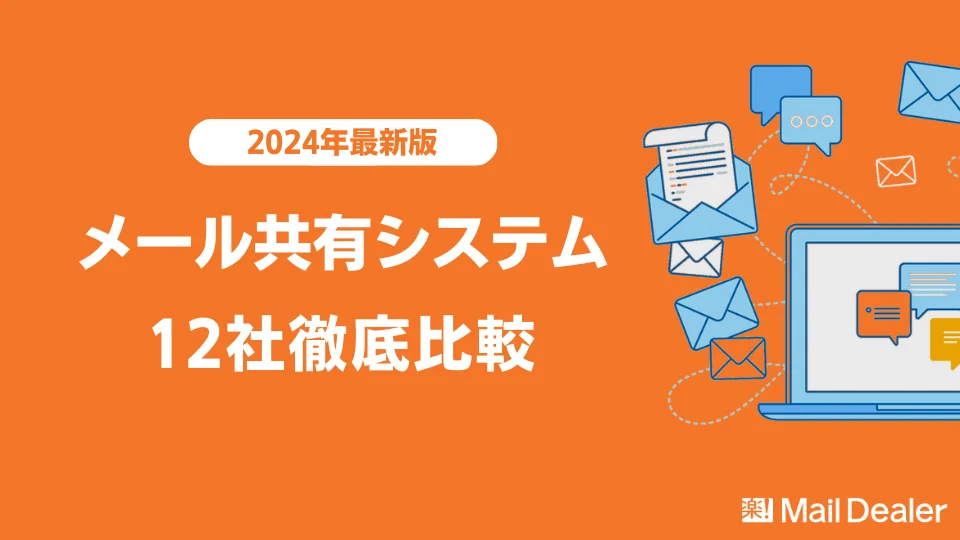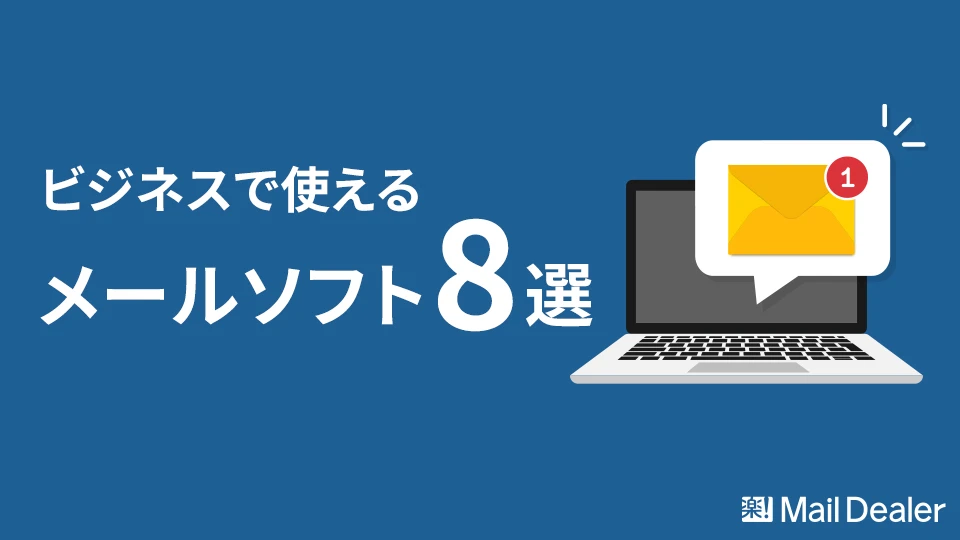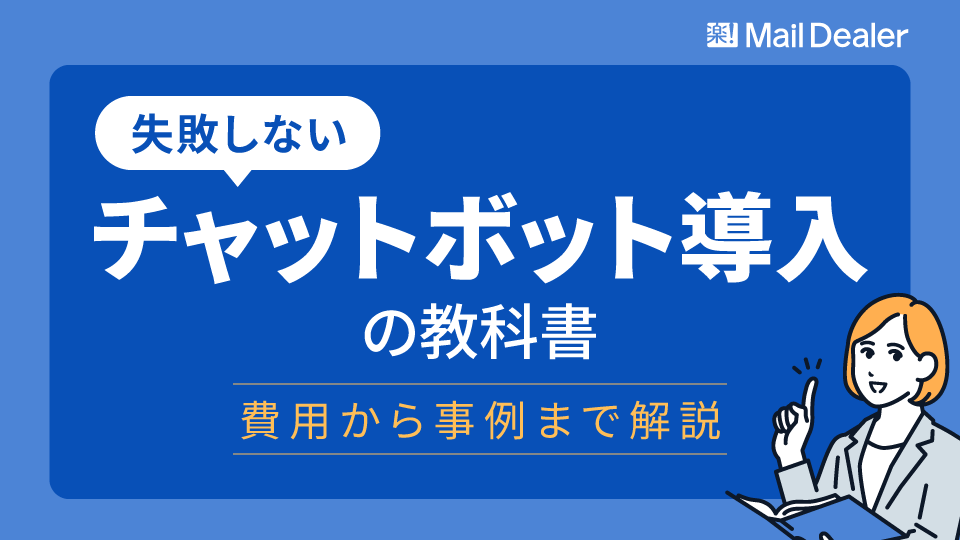
「問い合わせ対応の工数を削減したい」
「24時間顧客対応できる体制を整えたい」。
そんな課題を解決するチャットボットの導入ですが、計画なく進めると「導入したのに使われない」という失敗に陥るリスクもあります。
本記事では、導入の具体的な5つの導入フロー、費用相場、そしてよくある失敗例と回避策などを解説します。
なお、メールでの問い合わせの効率化なら、「メールディーラー」などのメール共有・管理システムがおすすめです。
そもそもチャットボットとは?2つの基本タイプを解説
チャットボットとは「チャット」と「ロボット」の2つの言葉を組み合わせたもので、人工知能を活用した「自動会話プログラム」です。
チャットボットには主に、以下の2つタイプがあります。
- シナリオ(ルールベース)型チャットボット
- AI(機械学習)型チャットボット
ここでは、それぞれの特徴と長所・短所・活用例を解説します。
自社の目的に合ったタイプを判断できるよう、チャットボットの基本からしっかり押さえておきましょう
シナリオ(ルールベース)型チャットボット
シナリオ型チャットボットは、あらかじめ設定されたシナリオ(脚本)に沿って、選択肢やキーワードに回答する形式のチャットボットです。
例えば「Aという単語が入力されたらBを返す」など、会話の内容を認識せずに、決められたルールにしたがって回答するため「ルールベース型チャットボット」とも呼ばれます。
| 長所 |
|
|---|---|
| 短所 |
|
| 活用例とおすすめの使い方 |
|
AI(機械学習)型チャットボット
AI型チャットボットは、AIが大量の学習データから質問の意図や文脈を理解し、適切な回答を生成する形式のチャットボットです。
あらかじめ設定されていない自由な質問にも対応できます。
| 長所 |
|
|---|---|
| 短所 |
|
| 活用例とおすすめの使い方 |
|
導入を検討する際にはシナリオ型でスモールスタートし、蓄積された対話データをもとにAI型へ移行・拡張するハイブリッドなアプローチも有効です。
チャットボットの導入で得られる5つのメリット
チャットボット導入のメリットは大きく5つあります。
- メリット1:問い合わせ対応工数の削減
- メリット2:24時間365日対応による機会損失の防止
- メリット3:オペレーターの負担軽減と離職率の改善
- メリット4:顧客満足度(CSAT:Customer Satisfaction Score)の向上
- メリット5:対話データを活用したマーケティングへの展開
これらのメリットについて、具体的な効果や数値を交えて解説します。チャットボット導入後のROI(投資対効果)の参考にしてください。
メリット1:問い合わせ対応工数の削減
チャットボットが一次対応を自動化することで、オペレーターが直接対応する件数を大幅に削減できます。特に、問い合わせの多くの割合を占めるとされる「よくある質問」を自動化することが効果的です。
例えば、株式会社斎藤英次商店ではチャットボットの導入により、月200件ほどあった電話問い合わせが導入後には約50件まで減少しました。そのうちホームページに掲載している内容に関する問い合わせは10〜20件程度となり、導入前の10分の1程度にまで抑えられた事例があります。
このように、チャットボットを導入することで、オペレーターの対応工数が大幅に削減でき、業務効率化の向上につながります。
メリット2:24時間365日対応による機会損失の防止
チャットボットの導入により、人間のオペレーターが対応できない深夜や休日でも顧客対応が可能です。
24時間365日いつでも即時対応できるため、営業時間外にサイトを訪れた見込み客の質問にも回答できるようになります。
その結果「電話がつながらない」ことによる顧客離脱や販売機会の損失を防ぐことにつながります。
メリット3:オペレーターの負担軽減と離職率の改善
チャットボットの導入により、単純な繰り返しの多い質問からオペレーターを解放でき、業務負担の軽減につながります。
さらに、オペレーターが高度で複雑な問い合わせに集中できる環境を構築できるのも大きなメリットの一つです。これによりオペレーターの業務満足度が向上し、カスタマーサポート部門の課題である、離職率の改善にもつながります。
メリット4:顧客満足度(CSAT)の向上
チャットボットを導入することで、顧客はスムーズな対応を受けることができ、顧客満足度(CSAT)の向上につながります。
顧客はオペレーターに電話する手間なく、待ち時間ゼロで24時間いつでも疑問を自己解決できるため、顧客のストレスを軽減することが可能です。
メリット5:対話データを活用したマーケティングへの展開
チャットボットは問い合わせ対応にとどまらず、顧客との対話データを活用してマーケティング施策に役立てることができます。
顧客との対話ログは、蓄積されることで「顧客の生の声」が集まった貴重なデータ資産となります。
「どのような質問が多いか」「顧客は何に困っているか」を分析することで、FAQ(よくある質問)の改善、Webサイトのコンテンツ拡充、さらには商品・サービス開発のヒントを得ることが可能です。
失敗しないチャットボットの導入フロー
チャットボット導入のメリットはありますが、ただツールを導入するだけで成果が上がるわけではありません。プロジェクトを成功させ、確実に効果を得るためには、明確な計画にもとづいたステップを踏むことが重要です。
ここでは、失敗しないチャットボット導入のフローを、5つのステップに分けて解説します。
- ステップ1:目的とKPIの明確化
- ステップ2:ツール選定と無料トライアル(機能・予算で比較)
- ステップ3:FAQ・シナリオコンテンツの準備
- ステップ4:テスト運用とチューニング
- ステップ5:本格導入と効果測定
ステップ1:目的とKPIの明確化
目的を明確にすることで、プロジェクト全体の方針を定め、導入時の失敗を防ぐことができます。「AIを導入すること」自体が目的になってしまうと、どのツールが自社に最適か、どのような機能が必要かを正しく判断できません。
ステップ1では、まず「何のためにチャットボットを導入するのか」という目的を明確にしましょう。
例えば目的は次のように設定します。
- 社外向け:問い合わせ件数の削減
- 社内向け:ヘルプデスクの工数削減
さらに、必要な機能を見極めるためには、具体的な数値目標(KPI)を設定することが重要です。
例えば、以下のように目標を立てます。
- 「問い合わせ件数を30%削減する」
- 「自己解決率を50%に向上させる」
ステップ2:ツール選定と無料トライアル(機能・予算で比較)
目的とKPIが定まったら、それを実現するための具体的なツールを選定します。公式サイトの情報だけで判断するのではなく、必ず複数のツールを客観的に比較検討しましょう。
この比較検討をせずにツールを決定してしまうと、導入後に「必要な機能が足りなかった」「想定外の費用が発生した」「使いにくくて現場に定着しない」といった問題に直面するリスクが非常に高くなります。
そのため、多くのツールが提供している無料トライアルを必ず活用しましょう。実際の操作感や設定のしやすさを導入前に確認できるため、ミスマッチを防ぐことができます。
ステップ3:FAQ・シナリオコンテンツの準備
導入するツールが決まったら、チャットボットのFAQやシナリオのコンテンツを準備します。これは、チャットボットの回答精度、ひいてはプロジェクトの成否を大きく左右する重要工程の一つです。
どれだけ高性能なAIツールを導入しても、学習させるFAQの質が低ければ、チャットボットはユーザーの質問に答えることができません。この準備を怠ると、回答できるものが少ないチャットボットになってしまい、ユーザーの不満を増大させ、プロジェクトが失敗に終わる直接的な原因となります。
まずは、想定される質問と適切な回答を整理しましょう。ベンダーによっては、シナリオ作成を効率化できるテンプレートを用意している場合もあるため、ステップ2のツール決めの際に確認しておくと安心です。
特にシナリオ型チャットボットを導入する場合は、ユーザーが迷わないように対話の流れ(シナリオ分岐)を細かく設計する必要があります。その際には、既存のFAQや過去の問い合わせ履歴を参考にすると、よりユーザーに寄り添ったシナリオを作成できます。
ステップ4:テスト運用とチューニング
ステップ4では、本格公開前に向けたテスト運用とチューニングを行います。チャットボットのシナリオ構築を最初から完璧にするのは難しいため、この工程は不可欠です。
まずは一部の部署や限られたユーザーのみがアクセスできる環境でテスト運用を行い、以下のようなフィードバックを収集します。
- 回答が不十分
- シナリオが分かりにくい
- ユーザーが途中で離脱してしまう
その後、テストで得られた課題をもとにFAQコンテンツの追加やシナリオの修正(チューニング)を行い、回答精度を高めていきましょう。
ステップ5:本格導入と効果測定
テスト運用とチューニングが完了したら、いよいよチャットボットをWebサイトや社内ポータルに本格的に導入します。
導入後は、ステップ1で設定したKPI(問い合わせ削減率、自己解決率など)をもとに成果を定期的に測定し、改善していくことが重要です。さらに、導入効果を定量的に評価するだけでなく、その背景にあるユーザーの心理や行動を分析し、改善施策に取り入れていきましょう。
利用状況の分析とコンテンツの継続的な更新を運用に組み込むことで、チャットボット導入の効果を最大限に引き出すことができます。
チャットボットの導入費用の相場【料金体系を解説】
チャットボット導入にかかる費用は、大きく分けて「初期費用」と「月額費用」の2つです。ただし、導入するツールの種類や機能によって、金額に差があります。
ここでは、費用の相場や料金体系を解説していきます。
初期費用:0円~100万円
初期費用は導入時に一度だけ発生する費用です。アカウント設定費や基本的なシナリオ構築のサポート費などが含まれます。
簡単なシナリオ型チャットボットであれば比較的安価で導入でき、0〜10万円程度、あるいは無料のプランが用意されている場合もあります。
一方で、AI型チャットボットや特殊な機能をカスタマイズしたい場合は、初期費用が10〜100万円程度かかるケースもあります。
【初期費用の目安】
- シナリオ型:0〜10万円
- AI型:10〜100万円
導入を検討する際は「自社の目的に合っているか」「サポートを必要とするか」を踏まえてツールやプランを選び、コストパフォーマンスを最大化しましょう。
月額費用:5,000円~100万円
月額費用は毎月継続的に発生する費用です。システムの利用料や保守・サポート費用が含まれます。
シナリオ型チャットボットであれば、月額数千円〜数万円が相場です。一方、AI型チャットボットは月額10万円〜30万円程度が相場となります。
ただし、高性能なチャットボットによってはシナリオ型でも月額10万円を超えるものもあり、AI型では月額100万円以上の費用がかかるケースもあります。
【月額費用の目安】
- シナリオ型:月額5,000円〜5万円
- AI型:月額10万円〜50万円
- 高機能:50万円〜100万円
また、月額費用はオペレーターのID数や月間のチャット回数などによって変動するケースが多い点に注意が必要です。料金が高いからといってAIの性能が優れているとは限りません。
費用を左右する3つのポイント(AIの有無、サポート体制など)
初期費用・月額費用について理解したところで、次はチャットボットの導入費用を左右する3つのポイントを紹介します。
- ポイント1:AIの有無
- ポイント2:サポート体制
- ポイント3:連携機能
ポイント1:AIの有無
チャットボットの費用を大きく左右するのがAIの有無です。一般的に、シナリオ型に比べてAI型は価格が高くなる傾向があります。
さらに、AI型の中でもAIの種類や性能によって価格差が生じます。高度な会話ができる機能を備えるほど費用は高くなります。
また、ツールによっては複数のプランが用意されており、利用する機能に応じて段階的に価格を設定できる場合もあります。
チャットボットの導入時には、必要なAI機能の範囲をよく確認してみましょう。
ポイント2:サポート体制
サポート体制の有無や内容によっても価格に差が生じます。特に、 ベンダーによるシナリオ構築支援や定例会での改善提案など、手厚いサポートが含まれるプランは高価になる傾向があります。
一方、安価なツールでは導入サポートが含まれていない場合も多いため注意が必要です。シナリオの構築はチャットボットの回答精度を大きく左右する重要な工程の一つです。特に初めて導入する場合は、ベンダーによる導入サポートを活用することをおすすめします。
また、問い合わせ内容の分析やFAQの改善支援など、導入後の運用サポートの有無も確認しておきましょう。
「自社で対応できること」「ベンダーに任せること」を明確にし、自社に合ったサポートレベルを選ぶことが重要です。
ポイント3:連携機能
初期費用と月額費用とは別に、外部システムとの連携で追加費用が発生するケースがあります。特に、CRMやMAなどのマーケティングシステムと連携する場合は注意が必要です。
ツールによって連携費用の有無や料金は異なります。導入前に連携したいシステムの確認と追加費用の有無をチェックしておきましょう。
チャットボット導入でよくある失敗例と回避策
チャットボットの導入プロジェクトは、計画を立てずに進めると「導入したのに使われない」「逆に不満が増えた」などという結果になってしまいます。
ここでは、代表的な3つの失敗例を挙げ、それを未然に防ぐための具体的な回避策をセットで解説します。
- 「導入」が目的化し、誰にも使われない
- シナリオ設計が不十分で、顧客の不満が増大
- 導入後のメンテナンスを怠り、情報が陳腐化
失敗を防ぐための回避策も解説しているので、導入前に確認しておきましょう。
「導入」が目的化し、誰にも使われない
チャットボットの導入自体が目的になり、実際には誰にも使用されないケースがあります。
以下、事例と回避策です。
【事例】
「流行っているから」という理由だけで導入した結果、解決すべき課題が曖昧なままになり、現場のニーズと合わずに利用が定着せず、やがて使われなくなる。
【回避策】
導入ロードマップのステップ1「目的とKPIの明確化」に立ち返り「誰の」「どのような課題」を解決するためのツールなのかを徹底的に議論する。
シナリオ設計が不十分で、顧客の不満が増大
導入したものの、シナリオ設定が不十分だとユーザーが求める回答を得られず、不満につながるケースがあります。
以下、事例と回避策です。
【事例】
シナリオ設計が不十分なため、ユーザーが求める回答にたどり着けず、同じ質問を繰り返したり、最終的に有人対応へたどり着けなかったりして、逆に顧客満足度を下げてしまう。
【回避策】
導入前のFAQコンテンツ準備を徹底する。また、チャットボットで解決できないと判断した場合は、スムーズに有人チャットや電話窓口へ引き継ぐエスカレーション動線を必ず設計しておく。
導入後のメンテナンスを怠り、情報が陳腐化
メンテナンスを怠ると、情報が古くなりユーザーが求める回答を提供できなくなるケースがあります。
【事例】
チャットボットを導入したまま放置し、FAQの更新やシナリオの改善を行わない。その結果として、新商品やサービスに関する質問に答えられず、古い情報を回答し続ける「使えない」チャットボットになってしまう。
【回避策】
導入ロードマップのステップ5「効果測定と改善」で解説したように、効果を最大化するためには定期的な分析・改善が不可欠。月に一度は利用状況を分析し、回答できなかった質問をFAQに追加するなど、継続的にメンテナンスを行う運用体制をあらかじめ構築しておく。
チャットボットの導入事例3選
ここでは実際にチャットボットを導入し、明確な成果を上げている企業の事例3選を紹介します。
日本航空(JAL):自己解決率を向上させ顧客満足度アップ
日本航空(JAL)は、顧客が24時間365日利用できるAIチャットボットを導入しました。
【目的】
電話がつながりにくい時間帯でも顧客が疑問を解決できるようにし、顧客満足度を向上させる。
【成果】
Webサイトに24時間対応のAIチャットボット「チャット自動応答サービス」を導入。導入当初は限定的だった回答範囲を継続的に拡大し、現在では回答カバー率が約90%に向上。顧客の自己解決を促進し、入電数の削減にも貢献した。
東京都:都庁の代表電話への問い合わせを自動化
東京都は、都庁の代表電話への問い合わせを自動化するためチャットボット導入による「チャットボット総合案内」サービスを開始しました。
【目的】
都庁に寄せられる膨大な数の電話問い合わせに対し、都民を待たせることなく、適切な窓口へ迅速に案内する。
【成果】
AIチャットボットとボイスボットを導入し、代表電話の一次対応を自動化。よくある質問にはAIが直接回答し、専門的な内容は適切な担当部署を案内することで、都民サービスの向上を図っている。
近年、機能が追加され、今後も継続的なコンテンツの充実と改善を行っていく方針です。
クレディセゾン:内製AIツールで全社の業務効率化を推進
クレディセゾンは「全社員によるDX実現」への一環として、生成AIの活用を軸とした取り組みを開始しました。
【目的】
文章要約やアイデア出し、社内情報の検索、議事録作成といった日常業務を効率化し、社員がより付加価値の高い業務に集中できる環境を構築する。
【成果】
「SAISON ASSIST」や社内情報回答チャットボット「アシストくん」、議事録作成システムといったAIツールを内製開発。プロンプトの共通化やSlack連携により、社員の利用ハードルを下げ、全社的なAI活用を推進。2019年から2022年までのDX推進で累計79万時間(社員約400人分)の業務自動化を達成しているため、今後も生成AIを軸にした業務プロセスの全面革新を行っていく。
まとめ:計画的なチャットボットの導入で業務を効率化しよう
本記事では、チャットボット導入の目的別の選び方や具体的な導入手順、費用、成功事例などを解説しました。成功の鍵は、明確な目的設定から始まる計画的な導入と、継続的な改善にあります。
チャットボットはWebサイトやアプリでの一次対応を自動化する上で非常に強力ですが、最終的にメールでの詳細なやり取りに繋がるケースは少なくありません。そのメール対応の品質と効率こそが、顧客満足度を決定づける最後の砦となります。
メールの問い合わせ対応を効率化したい方はAI機能を搭載したメール共有・管理システム「メールディーラー」がおすすめですので、主な機能などを見ていきましょう。
チームのミスを防ぐ管理体制を構築

「メールディーラー」は、17年連続売上シェアNo.1を獲得しており、チームの対応状況を可視化し、返信漏れや二重対応をシステムで防止します。
「このメール誰か対応した?」といった無駄な確認作業や、致命的な返信漏れ・二重対応をシステムで防止できます。
担当者不在時でも誰でも対応履歴を遡れるため、業務の属人化を防ぎ、安定した顧客対応の体制を構築することができます。
AIにより、リスク回避と業務を効率化
「メールディーラー」に搭載されている「リスク検知」機能は、AIがクレームの可能性を検知し、対応の遅れによる二次クレーム化を未然に防ぎます。
なお、2025年7月にリリースした、指示文から返信文案を作成する「カスタム生成」は、新人でもベテランのような質の高いメール作成を可能にし、チーム全体の対応品質を標準化します。
さらに、FAQをもとに回答案を自動で提示する「自動生成」(2025年10月リリース予定)も加わり、メール業務の速度と質を飛躍的に向上させます。
要点入力だけで返信文を自動生成する「カスタム生成」は、無料のデモ画面で今すぐ操作感を確かめていただけます。
※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス(以下「当社」といいます)または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。