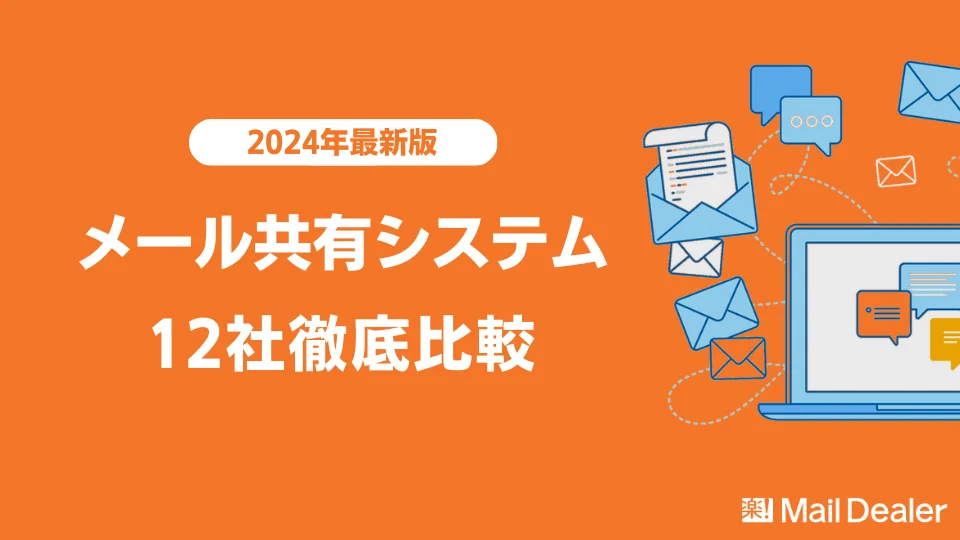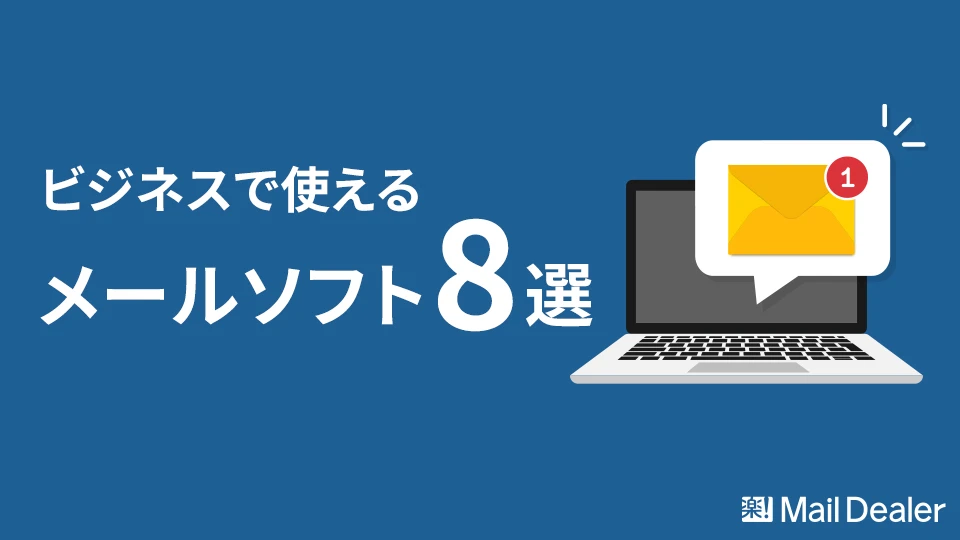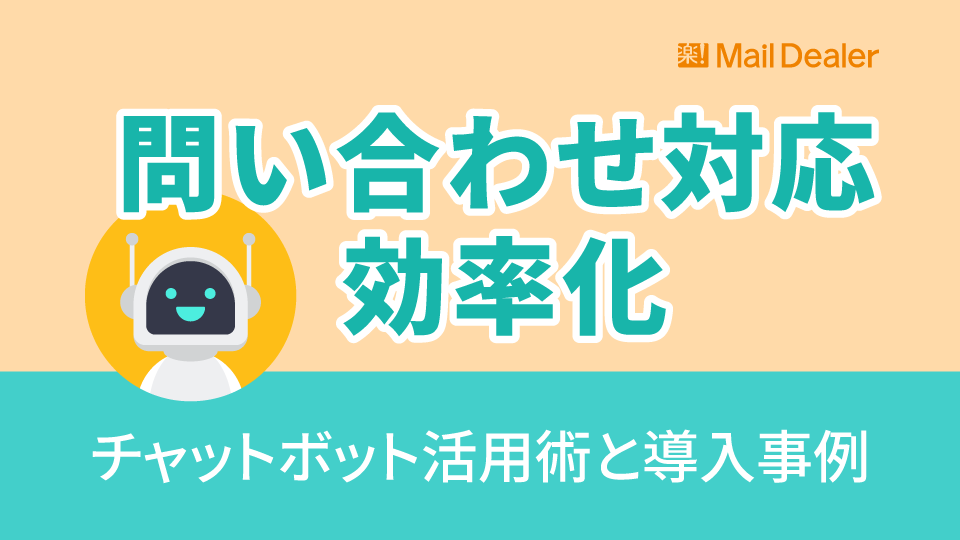
「また同じ問い合わせが来た」「担当者が不在で回答できない」。そんな問い合わせ対応の悩みを、チャットボットが解決します。
チャットボットの導入で、24時間365日、定型的な質問に即時対応することで、担当者の負担を劇的に軽減し、顧客や従業員を待たせない体験の提供で満足度向上にもつながります。
本記事では、社内と社外それぞれの問い合わせ対応におけるチャットボットの具体的な活用法から、失敗しないための導入ポイント、成功事例までを解説します。
なぜ問い合わせ対応にチャットボットが有効なのか?
チャットボットは、業務効率化や応対品質の向上、ユーザー満足度向上に有効な問い合わせ対応ツールです。ここでは、チャットボットの導入によるメリットを、自社のROI(投資対効果)をイメージしながら読み解いていきましょう。
メリット1:対応工数を大幅に削減し、担当者の負担を軽減
問い合わせの大部分を占める「よくある質問」は、チャットボットが一次対応することで、オペレーターの業務負担を大幅に軽減できます。例えば、営業時間や支払い方法の確認、パスワードの再設定方法などです。
担当者が直接対応していた質問にチャットボットが代わりに回答することで、対応件数が大幅に減り、担当者はより複雑な問い合わせに集中できます。
事実、実際にチャットボットの導入により、問い合わせの対応工数を50%削減したという企業もあります。
メリット2:24時間365日対応で、顧客や従業員を待たせない
チャットボットは24時間365日対応が可能で、問い合わせ先の担当者の勤務時間に依存せず、顧客や従業員を待たせません。深夜や休日でも、ユーザーからの質問に即時応答が可能です。
例えば「電話がつながらない」「メールの返信が来ない」といった待ち時間は、サービス離脱や業務停滞の原因となり、機会損失に直結します。顧客や従業員を待たせず即時対応できることは、顧客獲得の機会を逃さず、業務効率の低下を防げます。
メリット3:回答品質の標準化とナレッジの属人化を防止
チャットボットの導入により、回答品質の標準化とナレッジの属人化防止が期待できます。
有人対応では、担当者のスキルや経験によって回答に差が出る「属人化」が、よくある課題の一つです。属人化は業務の停滞だけでなく、回答品質の低下や担当者以外が業務を把握していないといった、デメリットを生み出します。
従来属人化していた対応も、ベテラン担当者の知識やFAQなどのナレッジをシナリオとしてチャットボットに登録すれば、回答が標準化され、品質を安定させる体制が整います。
メリット4:自己解決率の向上による顧客満足度と従業員満足度の向上
顧客や従業員の自己解決率が上がると、顧客や従業員の満足度向上につながります。不明点が発生するたびに電話やメールで問い合わせる手間がなくなり、Webサイト上でスピーディに疑問が解消されるためです。
この「すぐに解決できる」体験こそが、チャットボットを導入する大きなメリットです。不安を安心や信頼に転換させ、顧客満足度(CSAT:Customer Satisfaction)や従業員満足度(ESAT:Employee Satisfaction)の向上に結びつきます。
メリット5:問い合わせデータの蓄積と分析による業務改善
チャットボットは、単なる問い合わせ対応ツールではありません。蓄積した問い合わせデータを分析し、業務改善に役立てられます。
チャットボットに寄せられる質問は「顧客や従業員が本当に知りたいこと」が、集約された貴重なデータです。その中から「どのような質問が多いか」「解決できなかった質問は何か」を分析すれば、FAQの改善やマニュアルの整備、さらにはサービス改善のヒントが得られます。
蓄積したデータは、対応品質の向上にとどまらず、事業を成長させる資産となります。
【導入前診断】チャットボットが向いている問い合わせ業務とは?
チャットボットには、向いている業務と向いていない業務があります。特性を把握し、自社の状況に合わせて客観的に判断することが、導入後に生じる可能性のあるミスマッチを防ぎます。
なお、ここで紹介している内容は2025年時点での状況です。今後AIなどの技術の発展により、対応可能な業務範囲も拡大していくと予想されますので、技術の変化に合わせた役割分担やナレッジの整備が求められます。
チャットボットを活用できる業務:よくある質問、手続き案内など
チャットボットは、よくある質問や手続き案内に能力を発揮します。よくある質問や手続き案内は、パターン化されており、チャットボットの得意分野です。
例えば営業時間や場所の案内やパスワードリセットの手順案内、各種申請方法のガイドは、有人対応よりチャットボットでの対応が効果的と言えるでしょう。
条件付きでチャットボットが対応できる業務:資料請求、簡単なヒアリングなど
資料請求や簡単なヒアリングは、条件付きでチャットボット対応が有効な業務です。ただし、決められたシナリオだけでは完結せず、ユーザーからの個人情報の入力や、複数の選択肢への誘導が必要となります。
用意されたフローに従ってチャットボットが対応するため、ヒアリング項目の抜け漏れを防ぎ、問い合わせ対応の初期段階を効率化します。さらにフォーム連携機能や、有人チャットへのスムーズな連携(エスカレーション)機能があれば、より効果的な運用が可能です。
チャットボットが向いていない業務:クレーム対応、個別相談など
クレーム対応や個別相談は、チャットボットに向いていません。クレーム対応に必要な感情に寄り添う共感力や、個別相談で必要な状況を深くヒアリングする力は、チャットボットに不足しているスキルです。
これらの業務を無理に自動化しようとすると、チャットボットでは適切な対応ができず、かえって顧客満足度を低下させる恐れがあります。そのため、クレーム対応や個別相談は、チャットボットではなく有人で対応すべきです。
なお、有人対応でメールを使用する際には、ラクスが提供するメール共有・管理システム「メールディーラー」がおすすめです。
「メールディーラー」には「リスク検知」という機能が搭載されており、見逃してはいけないクレームメールをAIが自動で判別し、管理者に通知してくれます。
これにより、経験豊富な担当者が迅速に初期対応を行う体制が整い、対応の遅れや不適切な初動による問題の深刻化を防ぐことができます。
【社外向け】顧客からの問い合わせ対応におけるチャットボット活用法
社外向けのチャットボット活用法を紹介します。カスタマーサポートなど、顧客と直接接する部門での具体的な活用法と事例です。
Webサイトでの一次受付とFAQ案内
チャットボット活用法の一つ目は、Webサイトでの一次受付とFAQ案内です。
Webサイトは顧客にとって企業の第一印象を決める重要な入口です。ここにチャットボットを設置し「何かお困りですか?」と能動的に話しかけることで、問い合わせのハードルを下げられます。
また、よくある質問にはその場で回答し、顧客の自己解決を促進。従来のように顧客がWebサイト上を隅々まで探す必要がなくなり、簡単な質問を問い合わせるのは申し訳ない、という心理的負担も軽減します。
結果として、些細な疑問が原因でのサイト離脱を防ぎ、顧客満足度の向上も期待できます。
ECサイトでの注文状況や在庫の確認
ECサイトの注文管理システムと連携すれば、注文状況や在庫確認の問い合わせについて、チャットボットが活躍します。
例えば「この商品の在庫はありますか?」という購入前の疑問や「注文した商品はいつ届きますか?」などの不安に、24時間365日チャットボットが自動で回答。リアルタイムで購入前後の不安を解消できるため、顧客は安心して購買活動を進められます。
このスムーズな体験はコンバージョン率の向上や「カゴ落ち」の防止だけでなく、購入後の満足度を高め、リピート購入へとつなげる重要な役割を担います。
【事例】日本航空(JAL):AIチャットボットで顧客の自己解決を促進
日本航空(JAL)では、AIチャットボットの導入で、顧客の自己解決を促進しています。
同社では顧客満足度向上のため、電話窓口の営業時間に左右されず、顧客がいつでも疑問を解決できる環境の整備が課題でした。そこで、24時間365日対応のAIチャットボットを導入し、航空券の予約やマイルに関するよくある質問に、自動で応答する仕組みを構築しました。
チャットボットだけで回答を完結できる、回答可能範囲カバー率90%を達成し、顧客の自己解決を強力に促進。コールセンターの通話時間短縮を実現し、顧客満足度の向上に成功した事例です。
【社内向け】従業員からの問い合わせ対応におけるチャットボット活用法
チャットボットを、社内向けの問い合わせ対応に活用する方法を紹介します。特にバックオフィス部門の業務効率化につながる、社内ヘルプデスクとしての具体的な活用法と事例を取り上げます。
情報システム部門へのパソコントラブルやパスワードリセット対応
情報システム部門では、パソコントラブルやパスワードリセット対応といった定型的な問い合わせを自動化し、担当者を本来のコア業務に集中させられます。
社内から頻繁に寄せられる「パソコンが動かない」「パスワードを忘れた」といった問い合わせは、チャットボットが簡単なトラブルシューティング手順の案内や申請ページへの誘導を行い、自己解決を促します。
インフラ構築やセキュリティ強化といった本来注力すべき業務が中断されがちだった担当者は、コア業務に集中できるようになり、部門全体での生産性向上を望めます。
人事部門や総務部門への各種申請/手続き案内
人事部門や総務部門への申請、手続き案内においても、チャットボットが活用できます。
マニュアルを参照すれば分かる内容も「探すのが手間」という理由で、担当部門に問い合わせが集中しがちです。そこで活躍するのが、第一の窓口としてのチャットボットです。例えば「年末調整、住所変更、福利厚生の利用方法」などの定型的な問い合わせに対し、チャットボットが必要な申請書の保存場所や手続きのフロー案内をします。
チャットボットの活用により、部門ごとの担当者の工数を削減し、組織全体の業務効率が高まります。
【事例】クスリのアオキ:社内問い合わせ工数を削減
社内問い合わせにチャットボットを導入し、工数削減を目指した、クスリのアオキの事例を紹介します。
同社では労務管理部門に、全国の従業員から類似の問い合わせが多く寄せられ、対応業務が大きな負担となっていました。そこで、社内ポータルにAIチャットボットを導入。給与や勤怠、人事など約300件のFAQを搭載し、従業員からの定型的な質問に自動で応答する体制を整えています。
運用後、労務部門の問い合わせ対応業務が75%削減しました。
チャットボットと有人対応の切り分け方
前章で説明したように、チャットボットを活用すると満足度が上がる一方、チャットボットが対応したために満足度が下がってしまう可能性も秘めています。
そのため、チャットボットと人間、どちらで対応するべきかの切り分け方を解説します。
この項目を読めば、チャットボットの限界を正しく理解し、AIと人間の強みを最大限に活かすための役割分担ができます。
チャットボットに任せるべき業務:定型的または高頻度の質問
定型的または高頻度の質問は、特にチャットボットに任せるべき業務です。回答パターン化された質問はチャットボットの得意分野であり、回答の水準を一定に保ち、何度も発生する同じ質問に疲弊することなく対応します。
定型的または高頻度の質問は一次対応をチャットボットに任せ、人間はより付加価値が高く、思考力が求められる業務に集中できます。
人間が対応すべき業務:クレーム、複雑な相談、個別対応
一方でクレームや複雑な相談、個別対応といった、柔軟性と共感力が求められる業務は人間が対応すべきです。
特にクレーム対応は、顧客の感情に寄り添う姿勢が求められますが、キーワードやシナリオをベースに回答するチャットボットには不向きな領域と言えます。また、前例のない複雑な相談、契約内容の確認など個人情報を含む個別対応も、チャットボットは適切に対応できません。パターン化されていない質問への臨機応変な対応も、人間の強みが活かされる場面です。
スムーズな連携(エスカレーション)設計の重要性
チャットボットで一次対応をし、解決できない場合は有人対応に切り替える運用もあります。よくある質問はチャットボット対応で自己解決を促し、複雑な質問は有人対応で高い対応品質を保てます。
理想的な体制を実現する際に重要なのは、チャットボットが解決できない問い合わせをいかにシームレスに有人チャットや電話窓口へ引き継ぐ(エスカレーション)か、という動線設計です。チャットボットでのやり取り履歴を担当者に引き継げば、顧客は同じ説明を繰り返す必要がなくなり、有人対応によくある「たらい回しにされた」と感じるストレスを軽減します。
また、有人でメール対応をする際は、メール共有・管理システム「メールディーラー」がおすすめです。
「メールディーラー」はクラウド型のメール共有・管理システムであり、AIが過去の対応履歴やFAQなどのナレッジから、返信案を自動作成する機能もあります(※本機能は2025年10月リリース予定)。業務に慣れない新人でも、ベテランのような丁寧で適切な文章を作成でき、対応品質の均一化が可能です。
問い合わせ対応におけるチャットボット導入を成功させる4つのポイント
チャットボットの導入を成功させるためのポイントを4つ、解説します。
ポイント1:導入目的とKPI(自己解決率など)を明確にする
チャットボットの導入を成功させるためには「何のために導入するのか」という目的と「何を達成すれば成功か」という数値目標(KPI)の明確化が重要です。
目的を明確にするからこそ、チャットボットは単なるツールで終わらず、成果を生み出すビジネスツールとして機能します。例えば、業務効率化や顧客満足度向上、コンバージョン率の向上といったゴールが考えられます。
またKPIは、導入後の成果や進捗を把握し、改善につなげるための重要な指標です。KPIは「問い合わせ件数を30%削減する」「自己解決率を50%にする」など、具体的な数値決めがポイントになります。
目的が業務効率化なのか、顧客満足度の向上なのかによっても、その後の設計が大きく変わります。
ポイント2:FAQコンテンツの質と量を十分に確保する
チャットボットを導入する前に、FAQコンテンツの質と量を十分に確保しましょう。チャットボットは、用意された情報の中から回答を導き出すため、学習させるFAQの質と量に回答精度が大きく依存します。
そのため、導入前に既存の問い合わせ履歴などの分析が重要です。分析を行い、ユーザーが求めるQ&Aを十分に準備することが、活用できるチャットボットになるかの鍵になります。
ポイント3:導入後の定期的な分析とメンテナンスを怠らない
チャットボットは「導入して終わり」にせず、定期的な分析とメンテナンスを行い、回答精度の向上を目指します。
例えば定期的な分析として、回答できなかった質問をFAQに追加し、次からは回答できるようにします。また、分かりにくいシナリオを改善し、ユーザーの自己解決率を上げるようなメンテナンスも必要です。
こうした地道なメンテナンスを怠らないことが、高い回答精度でユーザーの自己解決率を向上させる秘訣です。
ポイント4:チャットボットの存在を社内や社外へ周知する
チャットボットの導入を成功させるためには、社内や社外にチャットボットの存在を周知する必要があります。どれだけ優れたチャットボットを導入しても、ユーザーに存在を知られなければ使われません。
導入後は、社内外への積極的な周知活動が必要です。例えば社外向けとしては「Webサイトの目立つ場所へ設置する」や「メールの署名に案内をつける」、社内にはポータルサイトで定期的に告知するといった方法があります。
まとめ:問い合わせ対応を「業務」から「資産」へ変革する次の一手
本記事で解説した通り、チャットボットは定型的な問い合わせ対応を自動化し、担当者の負担軽減とユーザー満足度向上を両立させる強力なツールです。
そして、チャットボット活用の本質は、単なる業務効率化に留まりません。蓄積される膨大な問い合わせデータは、顧客の「生の声」が集約された未来の利益を生み出す「資産」となります。
この貴重な「資産」を有効に活用するために、チャットボットから引き継がれるメールでの個別対応までを一元管理し、適切に運用することが次の一手となりますので、その具体的な解決策を見ていきましょう。
チームのミスを防ぎ、重要なやり取りを確実に記録
17年連続売上シェアNo.1の「メールディーラー」は、チャットボットでは解決できなかった個別の問い合わせメールについて、対応状況を可視化することができます。
一通ごとのメールに「未対応」「対応中」「完了」といったステータスと「担当者」が明示されるため、「誰が」「何を」しているかを管理でき、対応漏れや二重返信といったミスを防ぎます。
さらに、過去のやり取りはすべて一元管理され、チームの誰もが検索・参照できるため、重要な対話が組織全体の「資産」として蓄積されていきます。
最新AI機能で、対応の質と速度を向上
「メールディーラー」は、クレームの可能性を検知する「リスク検知」や、指示文を入力するだけで、文章案を生成する「カスタム生成」など、様々なAI機能を搭載しています。
さらに2025年10月にリリースを予定している「カスタム生成」機能は、返信文案を自動生成することができ、チャットボットから引き継いだ問い合わせに対し、迅速かつ高品質な対応を実現します。
要点入力だけで返信文を自動生成する「カスタム生成」は、無料のデモ画面で今すぐ操作感を確かめていただけます。
※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス(以下「当社」といいます)または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。