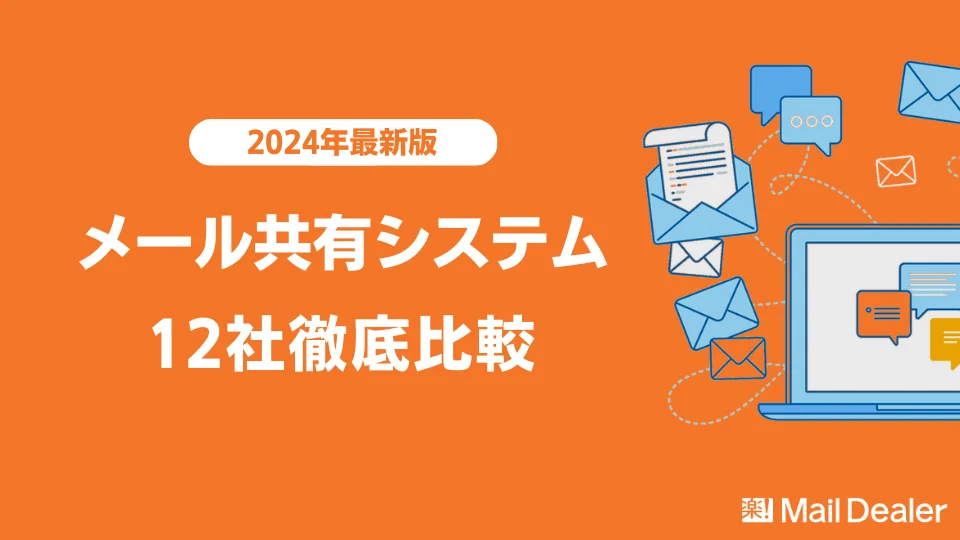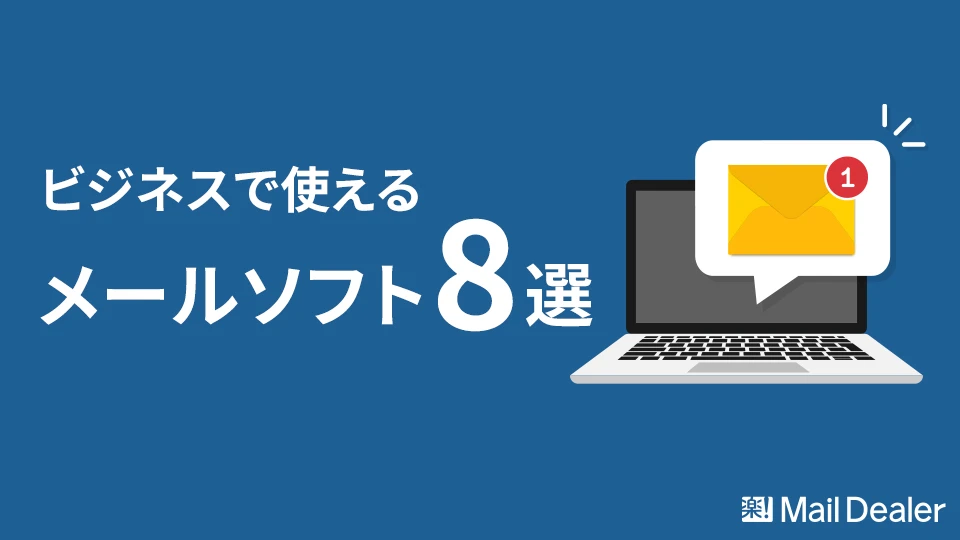「チャットボットを導入すれば業務が楽になるらしい。でも、実際にはどんなメリットがあるのだろう?」そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
チャットボットの価値は、単なるコスト削減だけではありません。経営者には経営効率化を、現場には業務負担の軽減を、そして顧客には利便性の向上を実現するツールです。
本記事では、チャットボット導入のメリットを「経営者」「現場担当者」「顧客・従業員」の3つの視点から解説します。さらに導入前に知っておきたいデメリットとその対策、成功事例まで紹介していますので、導入を検討する際の参考にしてみてください。
チャットボットとは?2つのタイプと基本を解説
チャットボットはチャット(会話)とボット(ロボット)を組み合わせた造語で、ユーザーからの質問に対して、自動で返答するツールです。
チャットボットは回答の生成方法により「シナリオ型」と「AI型」の2つがあります。使用する目的によって、選ぶべきタイプが異なりますので、チャットボットを導入する前に、それぞれの特徴を知っておきましょう。
シナリオ(ルールベース)型とAI(機械学習)型の違い
シナリオ型とAI型の違いを、以下の表にまとめました。解決したい課題や予算によって選ぶべきタイプが異なるため、まずはそれぞれの特徴を把握しましょう。
| 型の種類 | 回答方法 | 特徴 | 適しているケース |
|---|---|---|---|
| シナリオ型 | あらかじめ設定されたシナリオ(脚本)やルールに沿って、回答する | 回答品質をコントロールしやすい反面、シナリオにない質問には答えられない |
|
| AI型 | AIが質問の意図や文脈を理解し、適切な回答を生成する | 表記ゆれや曖昧な表現にも柔軟に対応できるが、導入コストが高く、AIの学習にデータが必要になる |
|
チャットボットがもたらすメリット
チャットボットの導入によって得られるメリットについて「経営者」「現場担当者」「顧客」という、3つの視点から解説します。
経営者のメリット:コスト削減と事業成長
チャットボットは、経営者にとって「コストを抑えつつ事業を成長させる」ための有効な手段です。人件費や採用コストの削減だけでなく、24時間対応による売上拡大や、問い合わせデータを活用した業務改善にもつながります。
以下では、その具体的なメリットを解説します。
メリット1:人件費と採用コストを削減
まずは、人件費と採用コストの削減というメリットがあります。チャットボットの自動化によって、オペレーターが対応すべき工数が減り、残業代の削減も見込めます。
オペレーター数を最適化すれば、人員不足の解消と採用や教育コストの削減が同時に叶います。
メリット2:24時間365日の機会損失防止と売上向上
チャットボットは24時間365日稼働するため、営業時間外の機会損失を防ぎ、売上向上が期待できます。
例えば、深夜や休日にサイトを訪れた顧客が疑問を解決できないと、そのまま離脱する可能性が高くなってしまいます。
しかしチャットボットがあれば、その場で疑問を解消でき、商品購入やサービス申し込みへスムーズに誘導可能です。
つまり、チャットボットは「いつでも即対応できる顧客接点」として、売上の取りこぼしを防ぎ、事業成長を支える重要な役割を果たします。
メリット3:問い合わせデータの資産化とサービス改善
チャットボットで受けた問い合わせのデータは、FAQの改善や商品開発、マニュアルの改善に活かせます。
日々、チャットボットに集まる顧客の声や疑問のデータは、自社の貴重な「資産」です。チャットボットは問い合わせ対応だけではなく、リサーチャーとしての役割も果たします。
例えば「収集した顧客の声を商品開発に活かす」「チャット内容のキーワードから市場のトレンドを把握する」などです。
データの分析により潜在的なニーズや不満を可視化し、より満足できるサービスに近づけることができます。
現場担当者のメリット:負担軽減と生産性向上
チャットボットで業務が楽になるだけではなく、より負荷の高い専門業務へシフトでき、担当者自身のスキルが上がり市場価値向上にもなります。
ここでは、現場担当者のメリットについて、詳しく解説します。
メリット4:定型的な問い合わせ対応からの解放
現場担当者は、定型的な問い合わせ対応に追われなくなります。
よくある質問に対しては、回答作成の工数がかかるだけではありません。日々の反復的な作業は、業務のマンネリ化やモチベーション低下を引き起こす一因です。
その点、チャットボットは反復作業に疲労を感じることなく対応できるため、現場担当者は作業工数の負担と精神的な負担の両方から解放されます。
メリット5:回答品質の標準化とナレッジの属人化防止
チャットボットは、回答品質の標準化とナレッジの属人化防止にも効果を発揮します。登録されたFAQやシナリオから、均一な品質の回答を提供するためです。
担当者間での情報の共有不足は、回答品質のばらつきを招く要因になります。
しかし、チャットボットの導入でナレッジを一元化できるため、特定の担当者に依存せず回答が標準化し、属人化の防止につながります。
メリット6:新人教育の効率化と早期戦力化
新人教育の現場でも、チャットボットは効率化と早期戦力化に有効なツールです。新人の担当者は、チャットボットに不明点を聞けば、先輩・上司などに頼らなくても自己解決できることが増えます。
OJT担当者の手が空いた時間を見計らわずにいつでもチャットボットに質問できる環境になり、新人の主体的な学習を促し成長スピードの向上が図れ、新人の早期戦力化が望めます。
OJT担当者も複数の新人から同じ質問をされなくなり、負担軽減になるのも大きなメリットです。
顧客のメリット:ストレスフリーな自己解決
チャットボットは「問題を迅速に解決できる」という、機能的なメリットから一歩進んで「好きな時間に、ストレスなく満足した回答が得られる」という優れた顧客体験も提供します。ここでは、顧客にとってのメリットを3点紹介します。
メリット7:待ち時間ゼロで24時間いつでも問題解決
チャットボットがあれば、営業時間に合わせて電話したり、メールの返信を待ったりする必要はありません。深夜や休日でも思い立ったときに問い合わせができ、顧客が助けを必要とするタイミングで即座に答え、自己解決へ導きます。
待ち時間の長さは、顧客満足度低下に直結します。特に、多くの人が時間対効果を意識する現代では、タイムパフォーマンスが重視されているためです。
メリット8:電話や対面より気軽に質問できる心理的ハードルの低さ
チャットボットの導入により、顧客は電話や対面よりも気軽に質問できるようになります。
問い合わせ自体に抵抗を持つ顧客も多くいますが、チャットボット相手には「こんな簡単なことを聞いてもいいのだろうか」という心理的なハードルが下がります。この気軽さこそが、見逃せないメリットです。
心理的ハードルの低減により、顧客が疑問を解消しやすい環境が整い、顧客満足度の向上が実現します。
メリット9:常に均一で正確な回答が得られる安心感
チャットボットは、常に均一で正確な回答を生成し顧客へ安心感を与えます。
オペレーターによって説明が異なった場合、顧客は「どの回答が正しいのか?」と、不安を抱きますが、チャットボットはFAQやシナリオという正しい情報から回答を生成するため、オペレーターの経験や知識に左右されず、常に標準化された情報を提供します。これにより、顧客はたらい回しにされるストレスもなく、問題解決までスムーズにたどり着けるのです。
他にもチャットボットの問い合わせ履歴がテキストとして残るのもメリットです。電話での「言った、言わない」というトラブルがなく、正確な記録が残る安心感が顧客からの信頼感を得ます。
なお、チャットボットから有人に切り替えてメール対応をする際には、ラクスが提供するメール共有・管理システム「メールディーラー」を使えば、顧客に安心感を与える回答作成ができます。
「メールディーラー」には、要点を入力すればAIがビジネスメールに変換する「カスタム生成」機能が搭載されています。これにより、業務に不慣れな新人でも、ベテランのように適切な文章を作成でき、対応品質の均一化が可能です。
導入前に知るべきデメリットと対策
チャットボットのデメリットと、その対策を解説します。チャットボットを導入した後に「想定と違った」とならないために、事前に把握しておきましょう。
デメリット1:初期設定とコンテンツ準備に手間がかかる
チャットボットは、初期設定とコンテンツの準備に手間がかかります。導入後、すぐに使えるわけではありません。特に回答のもとになるFAQの準備や、シナリオの設計に時間を要します。
対策として、以下のような事前準備があります。
- 導入前に、既存の問い合わせ履歴を整理しておく
- ベンダーの導入サポートを活用する
デメリット2:複雑な質問やクレームには対応できない
複雑な質問やクレームは、チャットボットには対応できません。
クレームには顧客の感情に寄り添って対応しますが、チャットボットは感情を読み取る力が不足しています。また、FAQやシナリオをもとに回答を生成するため、前例のない複雑な相談に答えられません。
チャットボットで対応できないと判断した場合に、スムーズに有人対応へ引き継ぐ(エスカレーション)フローの設計が要ります。
デメリット3:導入後のメンテナンスを怠ると陳腐化する
導入後の定期的なメンテナンスを怠ると、チャットボットが陳腐化します。
新商品やサービス、社内規定の変更があった場合は、チャットボットに登録した情報の更新が欠かせません。更新せず放置すると、古い情報や誤った情報を回答し続け、価値低下の原因となります。
定期的に利用状況を分析し、FAQを更新する運用保守ルールの事前構築が不可欠です。
デメリット4:導入効果が出るまでに時間がかかる場合がある
チャットボットの導入後は、期待した効果がすぐに出ないこともあります。
特にAI型チャットボットは、導入直後から完璧な回答ができるわけではありません。対話データを学習し時間をかけて精度が向上する性質上、学習が不足している初期段階は回答精度が低い可能性があり、考慮が必要です。
費用対効果を最大化するには、短期的な成果だけにとらわれず「半年後に問い合わせ件数を◯%削減する」など、中長期的な視点での改善が重要と理解しておきましょう。
導入時の確認ポイントと運用時の注意点
チャットボットの導入効果を最大化するには、事前の確認と継続的な運用の構築が肝心です。メリットとデメリットを理解し全体のイメージが掴めたところで、導入時の確認ポイントと注意点を解説します。
目的を明確にし、解決したい課題に合ったタイプを選ぶ
チャットボットを導入する際には、目的を明確にし、自社の課題に合ったタイプを選びましょう。
目的によって、選ぶべきチャットボットのタイプ(シナリオ型かAI型)が変わります。ここで抑えるべきなのは「コスト削減」や「顧客満足度向上」など、解決したい課題を一つに絞ることです。
シナリオ型は、AI型に比べて初期費用や運用コストが安く、よくある質問の一次対応に効果があるため、投資対効果(ROI)が上がります。AI型は、AIが質問の意図や文脈を理解し、適切な回答を生成するタイプです。また、シナリオ型に比べ質問の対応範囲が広く、顧客満足度を高めやすいといえます。
さらに、他ツールとの連携も検討しましょう。社内ヘルプデスクならSlack/Teams連携、社外の顧客対応ならWebサイトやLINE連携が適切です。
既存システムとの連携性を確認する
自社の既存システムとの連携性を確認します。チャットボットを導入しても、既存の業務フローと切り離されてしまっては、連携がスムーズにいかず、効果を活かせない恐れがあります。
連携性を確認すべきシステムとしては、CRM(顧客管理システム)やSFA(営業支援システム)、各種ビジネスチャットツールがあります。それぞれのシステムと連携するメリットは、以下の通りです。
| 既存システム | 連携するメリット |
|---|---|
| CRM |
|
| SFA |
|
| 各種ビジネスチャットツール |
|
サポート体制とセキュリティを確認する
導入前のチェックポイントとして、チャットボットのサポート体制と、セキュリティに問題がないかを確認します。
コンテンツの構築支援や導入後の改善コンサルティングなど、ベンダーのサポート体制が手厚いかを確認します。
チャットボットで個人情報や機密情報を扱う可能性がある場合は、セキュリティをしっかり評価すべきです。例えばIPアドレス制限やISMS認証(ISO/IEC 27001)など、セキュリティ要件を満たしているか、自社のセキュリティレベルと比較して問題ないか確認してください。
導入後の分析と改善を続ける運用体制を構築する
チャットボットを導入した後も、継続したデータの分析と改善が不可欠です。
チャットボットを「導入して終わり」では、単なる問い合わせツールの域を超えられません。自社の課題や目的に合わせて「育てていく」ことで、メリットを最大化します。
準備に時間をかけたコンテンツも、改善の余地があると理解しましょう。社内の運用変更や新商品の発売など、変化に合わせてユーザーからの問い合わせ内容も変わります。蓄積されたデータの中から「誰が」「いつ」「何を」分析し、どう改善していくのかという運用体制を、導入前に決めてください。
有人対応へのスムーズな連携(エスカレーション)を設計する
チャットボットでは解決できず有人対応に切り替える場合は、スムーズに切り替えられる動線設計が、顧客満足度の低下を防ぎます。
まずは「AIに任せる領域」と「人間が対応すべき領域」を、明確に切り分けておきましょう。チャットボットが解決できない問題は、顧客が迷わず有人対応へ進める導線を設計し、待ち時間の目安も明示できると理想的です。
特に顧客は、有人対応へ切り替わる際の「同じ説明の繰り返し」にストレスを感じます。それを防ぐには、会話履歴を保持したまま担当者へつなぐ仕組みの構築が必要です。この丁寧な連携こそが、満足度の低下を防ぎ、企業への信頼を損なわないための鍵になります。
チャットボットのメリットを実感した企業事例3選
チャットボットを導入し、成果を挙げている企業の事例を紹介します。
日本航空(JAL):顧客の自己解決を促進し満足度向上
日本航空(JAL)では、AIチャットボットにより顧客の自己解決を促進し、顧客満足度を向上させました。
同社では、電話受付時間外や混雑時でも対応できる、チャネルの不足が課題でした。そこで24時間365日、航空券の予約やマイルに関する質問にAIチャットボットが対応し、課題を解消。徹底した顧客目線でのFAQ作成とシナリオ設計で、顧客の自己解決を支援しています。
顧客の自己解決を促進し、コールセンターへの入電数を削減するとともに、顧客満足度を高めた事例です。
宮崎電子機器株式会社:バックオフィス部門の問い合わせ工数を大幅削減
バックオフィス部門への問い合わせにAIチャットボットを導入し、問い合わせ対応を50%削減することに成功したのが、宮崎電子機器株式会社です。
同社では「必要な情報をすぐに探せない」「バックオフィス部門への問い合わせが多い」といった課題がありました。その要因の一つは、社内資料が複数の場所に分散していたり、部署ごとに情報の形式や保存場所が異なったりしていて、適切な情報へ迅速にアクセスできない環境でした。
AIチャットボットに資料を集約した結果、社員が必要な情報を見つけられるようになり、業務効率化を実現しています。導入後は、バックオフィスへの問い合わせが50%減り、担当部門が本来の業務に集中できる環境が整いました。
北海道石狩市:利用者の利便性向上と業務効率化
北海道石狩市は、AIチャットボットの導入で、市民の利便性向上と業務効率化を実現した例です。
住民票などの手続きに関する情報提供に、AIチャットボットを導入。SNSやWeb上にチャットボットを設置し、24時間365日対応しています。
具体的には、以下のような情報に対応しています。
- ゴミの分別に関する案内
- 市民からの市道の破損状況通報
- 新型コロナウイルスワクチン接種の情報案内
同市のチャットボットの特徴は、市民が知りたい情報を迅速に提供し、利便性が向上している点です。
まとめ:チャットボットの次の一手は「メール対応」のDX
本記事で解説した通り、チャットボットは計画的に導入すれば「経営者」「現場担当者」「顧客」の三方よしを実現でき、問い合わせ対応を効率化できます。
しかし、チャットボットで一次対応を自動化した後、より複雑な問い合わせが最終的に行き着く「メールでの個別対応」の品質こそが、顧客満足度を決定づける最後の砦となります。
この「チャットボットから人間へ」の重要な引き継ぎを、AIとの連携でいかに最適化していくのか。その具体的な解決策を見ていきましょう。
チャットボットからの引き継ぎ体制を万全にする管理ツール
17年連続売上シェアNo.1の「メールディーラー」は、チームの対応状況を可視化し、返信漏れなどのミスをシステムで防ぐことで、この重要な連携体制を強化できます。チャットボットでは解決できなかった顧客を、待たせることなくスムーズな有人対応へとつなげることが可能です。
最新AI機能で、引き継ぎ後の対応品質も向上
さらに、AIがクレームの可能性を検知する「リスク検知」機能や、返信文案を自動生成する「カスタム生成」といった最新AI機能を搭載。チャットボットから引き継いだ複雑な問い合わせに対しても、担当者のスキルに依存しない、迅速で質の高い対応を実現します。
要点入力だけで返信文を自動生成する「カスタム生成」は、無料のデモ画面で今すぐ操作感を確かめていただけます。
※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス(以下「当社」といいます)または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。