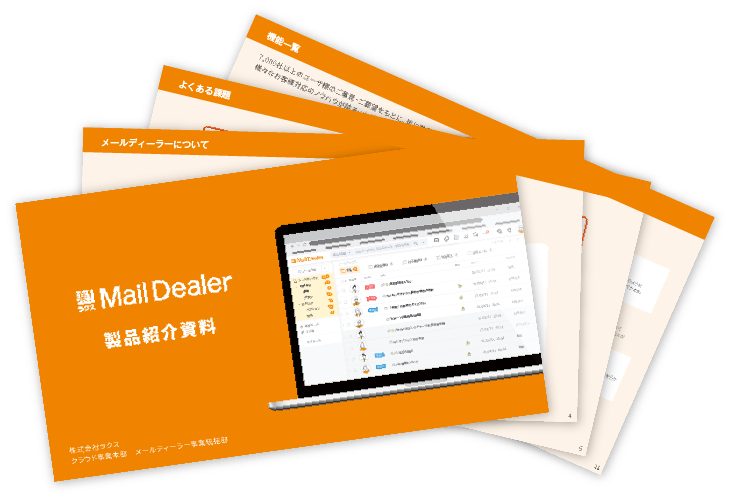企業様の海外出張の手配、サービス提供でお客様に「最も指示される」企業を目指す、株式会社日本橋夢屋様。航空券やホテル、ビザの提案、海外旅行保険から緊急時の対応など「安心・安全・便利」に法人企業様の「海外進出」を総合的にサポートしています。
ご導入企業様について

株式会社日本橋夢屋 様
仕事を可視化して共有すること
『仕事を可視化して共有するっていうのが一つのキーワードだと思います。誰かじゃないとできないのではなく、誰でもできるようになることで仕事がスムーズにいくようになったと思います。』
そう話すのは、株式会社日本橋夢屋 専務取締役 清宮 学様。
『個人のメールアドレスから、共有のメールアドレスへ変えることで、仕事のやり方が変わります。そもそも1人で仕事をするのではなく、チームで仕事をしやすい環境になる。そのような変化とともに、実際の社員のマインドも変わってくると思います。』
メールディーラーご導入のきっかけ
日本橋夢屋様がメールディーラーをご導入いただき、約9年。メールディーラーを知ったきっかけや、当時どのような思いでメールディーラーをご導入いただいたのか伺いました。
―メールディーラーを知ったきっかけを教えてください。
当時、名古屋営業所に行く新幹線の中で読んだ新聞広告でメールディーラーを知りました。
「これはもしかしてうちに合っているかもしれない」と思って社に戻ってきてから調べて、導入したという流れです。
―広告を見ていただいたのですね!ありがとうございます!どんなところが御社に合っていると感じられましたか?
そうですね、仕事を可視化し共有したいという考えがあり、それがメールディーラーに合っていると感じていました。
弊社のビジネスは、法人企業様の出張手配をしている旅行会社で、当時は10名程のスタッフが個人のメールアドレスを使ってお客様とやり取りをしていました。時代とともに、お客様からのオーダーはだんだんと「メール」が主流になってきて、電話でのやり取りであっても、書面に残して必ず確認のメールをお客様に送り、間違いがないように対応するようにするなど、メールの使用頻度も高くなってきました。また当時の運用としては、お客様に対し専任の弊社担当者をつけるようにしていたので、お客様からすると弊社担当者への連絡がしやすく、それがリピートにもつながっていました。
そういった背景もあって、専任担当制を採用しているのですがその反面、スタッフが休みの日の仕事内容や引継ぎ内容、または普段どのくらい仕事量があるのとていうのが把握できないという課題がありました。今では考えられないですが、休みのスタッフのPCを起動して、お客様にご迷惑がかからないよう未対応のメールがないか確認したりしていました。
―業務が「属人化」されていらっしゃったのですね。
はい。また、スタッフによっては業務量がまちまちで、あるスタッフは早く帰れるのに、あるスタッフは残業していることもありました。実際にどのくらいの問い合わせが来ていて、それぞれのスタッフがどのぐらいの業務量をこなしているのかが分からないということもあり、なるべく業務量を共有したい、可視化したい、というのが一つの目的でした。
―ほかにもご導入の決め手になったことはありましたでしょうか?
導入のしやすさですね。コスト的にもスタートしやすい金額で、最初からシステムを組むよりかは、クラウドシステムで月額料金制というのが弊社からすると、当時導入しやすかったのだと思います。
個人のメールアドレスから共有メールアドレスへの切り替え
個人のメールアドレスから共有のメールアドレスへ
―個人メールアドレスから共有メールアドレスに移行する際、いかがでしたでしょうか?
まず既存のお客様に、メールを共有するためにこのメールアドレスになりますと、新たに作成した「共有のメールアドレス」のご案内をしました。署名などのメールアドレスも全部「共有のメールアドレス」に変えて、次の返信分からは「共有のメールアドレス」を利用して、「メールディーラー」から返信するようにした結果、自然にメールアドレスが切り替わっていきました。
特別なことをした訳でもなく、スムーズに移行できたのを覚えています。
―スムーズに移行できたとのことで良かったです!
当時、共有のメールアドレスは3つぐらいだったかと思います。メインでお客様からお問い合わせをいただくアドレスと、info@のようなアドレスと、あとは、管理用のアドレスぐらいだったと思います。お客様とのやり取りが全部共有管理できるので、やりたいこととしてはほぼ狙いどおりでした。
業務を可視化することで得られた効果
個人のメールアドレスから、共有のメールアドレスに移行し、メールディーラーでの管理をはじめて、どんな効果が出ているかを伺いました。
残業が多いときの1/4に!
―共有のメールアドレスに変え、メールディーラーで管理をはじめてどんな変化がありましたか?
結果として「残業が減った」という効果を感じています。
専任担当制だと、「担当じゃないと分からない」という状態で仕事が「属人化」されてしまう反面、「このお客様は私だから頼んでくれる」というモチベーションにつながっている部分もありました。しかし、共有のメールアドレスを使って共有管理することで、全く反対の「チームで仕事をする」という方針に変えた結果、それぞれのスタッフが案件に対して「チーム」でスピーディーに問い合わせに対応し、顧客満足度を向上させたという結果に結びつきました。
―残業が減ったのはとても嬉しいです!チームで仕事をすることで具体的にどのように変わりましたか?
そうですね。メールディーラーで業務量が可視化されたので、たとえば誰か1人に見積依頼などが集中している場合、「Aさん見積対応が多いから、Bさん対応してあげて」と、みんなでお互いの業務量を見て協力することや、リーダーが指示を出して業務量を調整することが多くなりました。結果、お客様にとっても早いご案内ができるようになりましたし、なによりも、「チームで仕事をする」っていう意識もついてきましたし、とてもいい効果が出たと思います。
―もし差支えなければ。残業ってどのくらい減ったか教えていただけますでしょうか?
今の平均残業時間が1名あたり1か月で5時間以内程なので、当時はその3~4倍の時間がかかっていました。以前は対応状況が見えなかったので、どのくらいの業務量なのかが把握できなかったのですが、今では未対応のメールはどのくらい残っているのかなど進捗を把握できるので、業務を振り分けやすいです。
旅行会社は業界的にも残業時間が多い方ですが、弊社は業界の中でも残業が少ない方なので、そうなったきっかけはメールディーラーのおかげといえると思います。
メールを共有管理することで各拠点と助け合える
―本インタビューの冒頭に、名古屋営業所に向かう途中にメールディーラーを知ったと伺ったのですが、他拠点ともメールディーラーでメール共有はされていますか?
現在では、名古屋、大阪、福岡ともメールディーラーでメールの共有管理をしています。
普段は拠点ごとにメールボックスを分けそれぞれの拠点でメール対応を行っているのですが、2018年9月に、関西で大きな台風があった際に、鉄橋が壊れてしまい関空が封鎖されてしまったので、大阪営業所は問い合わせが多くて大変でした。そんなとき、大阪のスタッフには電話の対応のみ集中して対応してもらって、その間、問い合わせなどメール対応は東京のスタッフが返信するなど対処することができました。そういう場面では、本当にみんなで協力するためのツールになっていると感じます。
メールディーラーを運用していく中で便利な機能について
メールディーラーで問い合わせメールを共有管理することで、業務の可視化により結果的に残業時間が減り、スタッフ間同士はもちろん他拠点との協力体制もとることができた日本橋夢屋様。現在の運用について伺いました。
現在の運用について
―当時は10名のスタッフ様で問い合わせ対応をされていたとのことですが、現在は何名くらいでご対応されていらっしゃいますか?
現在は、50名の社員全員がメールディーラーを利用しています。
大阪、名古屋、福岡などの各拠点や、航空券、ビザ、ホテルなどそれぞれを扱っているセクション、経理など大きくは8つのチームでメールディーラーを利用しています。
―50名!対応されるメール担当の割り振りってどのようにされていらっしゃいますか?
メールを共有しているので、チームごとにフォルダを作成して対応すべきチームのフォルダのメールが入るようにしています。
またその中でも、メール本文中に「●●様」と弊社スタッフの名前が記載されていれば、自動で担当者が割り振られるようにもしていたり、逆に担当名が入っていないものは、リーダーが担当者を割り振ったり、手の空いているスタッフが取り掛かるといったようにしています。
以前課題だった代理対応も引継ぎが簡単に
メールディーラーでよくご利用いただいている機能はありますか?
引継ぎ事項の記載や、メモ帳がわりに、「コメント機能」をよく使っています。
担当者不在で別担当が代理対応することもあるので、お客様から連絡があって話した内容を残すのに利用しています。
ほかに、お客様から届いた問い合わせメールの内容だけでは情報が不足している際、お客様にお電話で確認した内容をコメントに残したり、案件に対して、担当スタッフやお客様への説明をどこまで行っているかなどを記載しています。
新人教育は承認機能で
―ほかにもよく利用されていらっしゃる機能はありますでしょうか?
お客様へご迷惑がかからないよう誤送信防止のために「承認機能」を利用しています。
たとえば、航空券のチケットをメールで送る際に「承認機能」で上長にチェックをしてもらってから送信できるので、未然に間違いを防ぐことができています。
また、新人教育の際に、お客様からの問い合わせに対して、フライトのスケジュールや料金の見積などいくつかのパターンを作って返信するのですが、その際ももちろん承認機能を利用して先輩や部長にチェックを通します。
そうする事によって、誤った内容の送信防止にもつながりますし、何より新人スタッフが安心してお客様対応ができる環境をつくっています。「間違った内容をお客様へ送らない」といったチェック体制を作れるので、新人を育てる過程でとても重宝しています。
―承認機能でしっかりと新人教育や誤送信防止をしていらっしゃるのですね!
ほかにも、チームでメールを共有しているので先輩に来た問い合わせメールを新人スタッフが練習で対応したり、その実際に届いた問い合わせの内容でロールプレイング的な教育もしやすいのでとても助かっています。共有しているからこそ、先輩スタッフがアドバイスもしやすく、実践に近い形でトレーニングができています。
テンプレートを共有して定型的な問い合わせ対応に
新人教育もメールディーラーを使って行っていただいているのですね!
旅行業界ですと定型的な問い合わせも多いかと思うのですが、そういった対応ってどのようにされていらっしゃいますか?
メールディーラー上でみんなが使えるテンプレートをシチュエーション毎にたくさん用意しています。
たとえば、ビザの代行申請だとか、ビザの取り方というのをそれぞれビザの種類ごとにテンプレート化しています。
テンプレートも共有管理ができるので、新人スタッフも一般のスタッフもみんなが使えるようにしています。
最後に一言お願いいたします。
―最後に、メールディーラーご検討中の企業様へメッセージをお願いします!
「メールを共有」することで、仕事のやり方が大きく変わりましたし、「チームで仕事をする」ということが浸透していったことで、安心して働けるようになりました。特に新入社員の子たちは、「チームで仕事をする」ことに、すごく安心感を持っていると思います。そういう意味でも業務の「可視化」というのは、いい方向に働きかけていると思います。