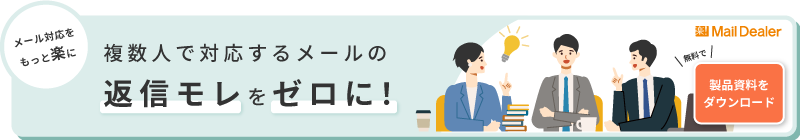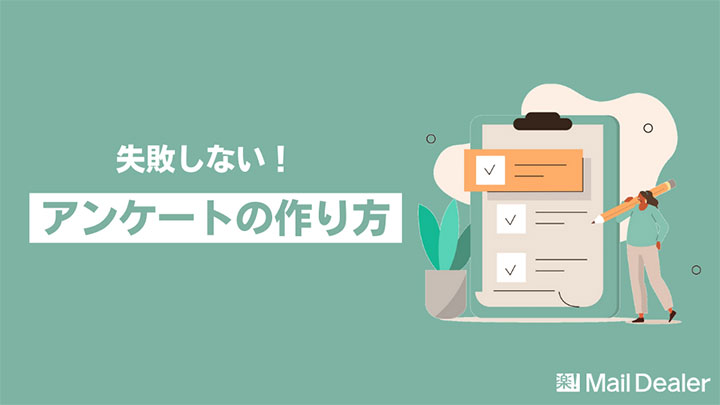
アンケートは作り方によって、回答率が大きく左右されます。
この記事では、アンケートの作り方と回答率の高いアンケートを作るための6つのコツを解説します。
アンケートの作り方
まずは、基本のアンケートの作り方について解説します。
STEP1:目的・ターゲットを決める
はじめに、「何を知りたくてアンケートをするのか」という目的を明確にしましょう。
目的を明確にしておかないと、何が聞きたいのかよく分からず、必要なデータを得られない結果となる可能性があります。
さらに「アンケート結果をどう利用するのか」も考えることで調査したデータを効率的に活かすことができるでしょう。
続いて、「誰に対してアンケートを実施するのか」を設定します。
性別、年齢、職業、既存顧客、見込み顧客など、アンケートの目的によって調査すべきターゲットが異なります。
STEP2:期間・方法を決める
次に、いつまで回答を募集するのか期間を設定しましょう。一般的には1ヶ月~2ヶ月くらいで設定する場合が多いです。
期間を決めたら、アンケートを集める方法を考えましょう。郵送、対面、電話、WEBなど、様々な媒体があります。
例えば、ターゲットが高齢者である場合、WEB調査ではなく対面や電話が最適です。
また事前説明が必要だったり、質問が複雑な場合は対面で回答を促す方法が最適です。ターゲットやアンケートの内容に合わせて最適な方法を選びましょう。
STEP3:質問項目を決める
次に、質問項目を決めます。最初は聞きたい内容を全て洗い出しましょう。
その中で、なんのために聞くのか、目的を意識して選別することが重要です。何が聞きたくてこの質問をするのかを明確にすることで、意味のある質問だけを残すことができます。
また、アンケート全体の冒頭には、性別、年齢、職業、家族構成、所在地などのユーザー属性に関する質問を入れると、後で属性ごとの集計が可能になります。
ただし、属性に関する質問が多すぎると、その後の回答率が下がる恐れもあります。アンケートの目的に合わせて最小限に絞りましょう。
STEP4:質問項目を選定し並び替える
次に、洗い出した質問項目を選定し、並び替えを行います。
似たような内容の質問を統合したり、優先度の低い質問を削除したりなど整理を行いましょう。全体の回答時間を調整し、実現可能な質問項目であるか検討することが重要です。
STEP5:回答方法を決める
次に、回答方法を決めます。同じ質問であっても聞き方によって分析できるデータが異なる可能性があります。
代表的な回答方法は選択式のラジオボタン、チェックボックス、スケール、マトリックス、自由記述式のテキストボックスの5つです。
ラジオボタン
ラジオボタンとは、複数の選択肢のなかから1つだけ選択して欲しいときに使用します。単一回答、SA(SingleAnswer)とも呼ばれます。
チェックボックス
用意した選択肢の中から当てはまるものを複数選択して欲しい時に使用します。複数回答、MA(Multiple Answer)とも呼ばれます。
スケール
スケールは、「満足、やや満足、どちらともいえない、やや不満足、不満足」や1から5までの数値で段階的に評価してほしい時に使用します。評定尺度法とも呼ばれます。
「どちらともいえない」という選択肢を加え、奇数個の選択肢にする場合が多く、満足度や好感度などの調査などに用いられます。
マトリックス
マトリックスは、スケールの質問項目を増やしたタイプの形式です。複数の項目についての評価やイメージ比較などの調査で用いられることの多い方法です。
例:
接客(満足・やや満足・どちらともいえない・やや不満足・不満足)味つけ(満足・やや満足・どちらともいえない・やや不満足・不満足)
雰囲気(満足・やや満足・どちらともいえない・やや不満足・不満足)
テキストボックス
テキストボックスは選択肢を選ぶのではなく、自由に記述する回答方法です。
例:今回ご注文いただいた商品は何ですか
テキストボックスは生の声を聞くことが出来ますが、回答に時間がかかるため、回答者の負担となります。回答率が下がるリスクがあるため、必要最低限に取り入れましょう。
STEP6:導入部分・挨拶文を考える
挨拶文・目的説明
質問に入る前に軽い挨拶文があると印象が良くなります。「アンケートにご協力頂きありがとうございます。」といった挨拶文に続けて、「このアンケートはサービス向上のために利用いたします。」など目的を説明すると良いでしょう。
回答期限・回答にかかる時間の目安
いつまでに回答すべきアンケートなのか、回答期限を必ず記載しましょう。
また、回答にかかる時間の目安を記載することで、顧客は空いている時間を利用して答えやすくなります。
個人情報の取り扱い方針
アンケートで氏名や住所、メールアドレス、会員番号などの個人を特定できる情報を集める場合は、個人情報の取り扱い方針を説明する文章を記載し、個人情報の問い合わせの窓口を設定する必要があります。
回答率の高いアンケートを作るための6つのコツ
アンケートの回答率を上げる6つのコツを紹介いたします。
1.適切なターゲットに絞り込む
アンケートは、目的・内容に応じた適切なターゲットに実施することが重要です。
例えば「自社商品のユーザー」について知るためのアンケートで、20〜30代のユーザーに偏ってアンケートを行ってしまうと、得られるデータにも偏りが発生します。
始めに設定したアンケートの目的に適切なターゲットに絞り込みましょう。
2.流れを意識して順番を決める
年齢、性別、住んでいる地域など、顧客にとって答えやすい質問を最初にすると、アンケートのハードルを下げることができます。
考えずに回答できる簡単な質問から始め、次にYes・Noで回答できる質問、選択肢のあるチェックボックスなどの質問、最後にマトリックスや自由記入の質問とすることで回答率が上がりやすくなります。
3.簡潔でわかりやすい質問にする
質問文が曖昧で不明瞭だと、正確な回答が得られなかったり、アンケートの途中で離脱してしまう可能性もあります。
難しい漢字や表現、専門用語などの利用を避け、簡潔でわかりやすい一文にまとめることが重要です。
人によって様々な解釈ができる言い回しや複数の意味を持つ言葉も避け、回答者と認識が統一できる質問を作成しましょう。
4.選択肢を整理する
選択肢を増やしすぎて内容の似ている選択肢があると、回答者が迷い、離脱につながります。逆に、選択肢が少ないと「その他」に回答が集中し、正確なデータが得られなくなります。漏れや重複が無いように選択肢を整理しましょう。
また、「その他」の具体的な回答を記述できるように、近くにテキストボックスを設置することもおすすめです。
5.質問数を最小限に絞る
質問数は少ないほど回答数も集まりやすくなります。多くなればなるほど、回答途中の離脱につながります。
集めたい情報の優先順位をつけ、質問を整理することが重要です。
目安としては5分以下で回答が終わるように質問数を絞りましょう。
6.インセンティブをつける
インセンティブは、アンケート回答のために時間や労力を割いていただいたことへの感謝を伝えるだけでなく、回答率を上げることができます。
質問数が多いアンケートや回答に時間がかかるアンケートは、時間と労力に釣り合うインセンティブをつけると良いでしょう。
また、景品を発送するためという用途があれば、回答を嫌煙されがちな個人情報も集めやすくなります。
そのまま利用できる!よくあるアンケート質問例
実用的なアンケート質問を考える際、その目的や対象者を念頭に置くことが重要です。また、質問は明確で、簡潔なものを心がけ、回答者が容易に理解しやすい形式であることが求められます。しかし、実際にこれらを満たした設問を作るのは難しく感じることもあるはずです。お悩みの際は下記アンケート質問例を参考に、作成してみてください。
- この製品を使用してみて、最も価値があると感じた機能は次のうちどれですか?
- 私たちのサービスへの満足度を5段階で評価してください。
- 最近購入いただいた商品「●●●●」について、既にご利用いただきましたか。また、ご利用いただいた場合、商品の改善すべき点があれば教えてください。
- 当社のカスタマーサポートチームが問い合わせをいただいてから返信までにかかる時間について、どの程度満足していますか?
- 新サービス「●●●●」に関するご意見をお聞かせください。
- 当社のウェブサイトを利用する際に必要な情報にスムーズにたどり着けないことはありましたか?お探しの情報と見つけづらかったページを教えてください。
- ●月●日開催のイベントに参加された感想をお聞かせください。
- 今後発売してほしい新商品やサービスについてご意見をお聞かせください。
- 当社製品/サービスのどの点が競合他社と比較して優れていると感じますか?
- 今回のアンケートに関して、改善してほしい点があればお聞かせください。
アンケート調査のためのおすすめツール
株式会社ラクスの提供する「メールディーラー」は、info@やsupport@など共有メールアドレスやメーリングリスト宛にくる複数名で対応・管理するメールに特化したメール共有システムです。
複数名でメールを共有する際に起こりがちな、メールの見落としや重複対応を防ぐための機能が備わっています。
メールディーラーの「お客様アンケート機能」では、メール対応を行った顧客にアンケートメールを自動送信し、自動で回答結果を集計することができます
また、アンケートフォームは自社のイメージに合わせて自由にデザインを変更できます。
アンケートの作り方・コツを抑えて、回答率を高めよう
サービスの向上や商品開発に役立つアンケートですが、作り方によっては必要な回答数やデータが得られない場合もあります。作成する際には過不足なく情報が得られる質問かを見直しましょう。
同時に、顧客にとって答えやすく、不愉快な気持ちにならないかも確認が必要です。今回紹介したコツを元に、顧客満足度に役立つアンケート調査を行いましょう。
※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス(以下「当社」といいます)または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。
※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス(以下「当社」といいます)または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。