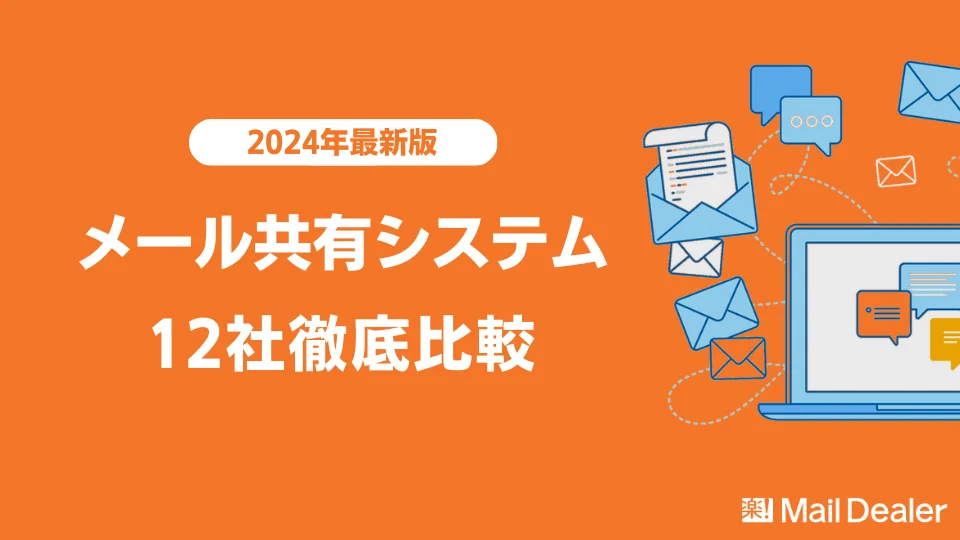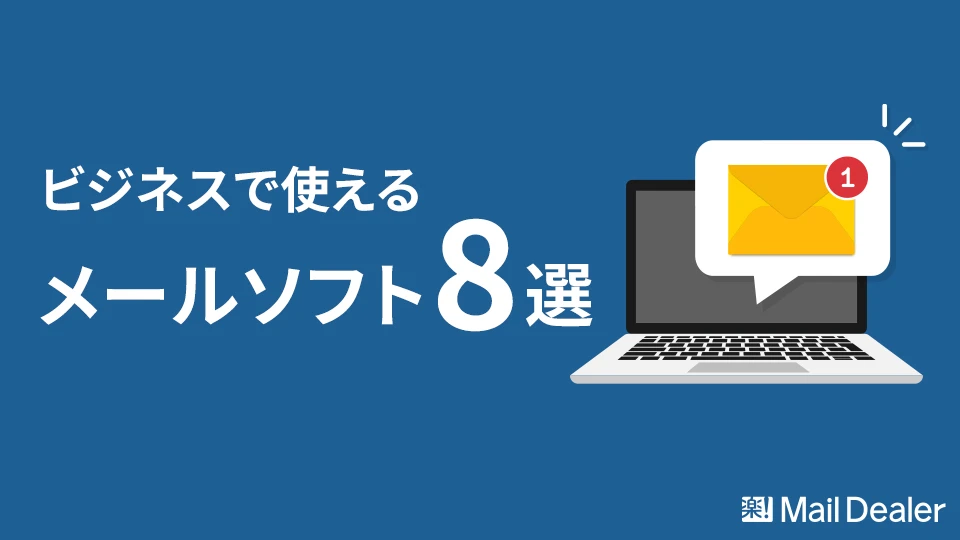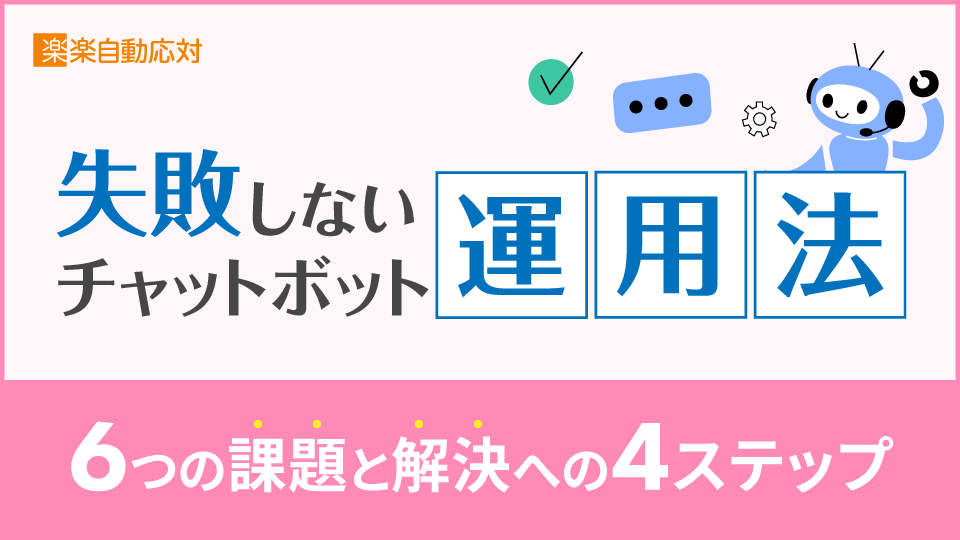
「コストをかけてチャットボットを導入したのに、問い合わせが減らない」「成果が分からない」 そんな悩みを抱えていませんか?チャットボットは導入して終わりではなく、効果を出すには継続的な改善が不可欠です。
本記事では、運用で直面する6つの課題、解決への4ステップ、ツール選びのポイントを解説します。この記事を読めば、自社の課題が明確になり、明日から実践できるアクションプランが分かります。
なぜチャットボットの「運用」が重要なのか
チャットボットは「導入して終わり」のツールではなく、導入後の「運用」が重要です。ここからはその理由を2つ解説します。
理由1:ユーザーの疑問や外部環境の変化に対応するため
一つ目の理由は、ユーザーの疑問や外部環境の変化に対応するためです。ユーザーが抱く疑問は、新サービスや料金プランの変更、季節的な要因などによって変化します。
そのため、チャットボットの情報を最新の状態に保たなければ、古い情報を案内してしまい、かえって顧客の混乱を招く原因になります。
理由2:利用者データにもとづき、より役立つツールへ育てるため
二つ目の理由は、利用者データにもとづき、チャットボットをより役立つツールへ育てるためです。実際にチャットボットを利用してもらうと「この質問には答えられないのか」「この説明は分かりにくい」といった、導入前には想定できなかった課題が見えてきます。
そのためには、これらの利用者の声を分析し、改善を繰り返すことが重要です。その結果、チャットボットはより回答精度が高く、使いやすいツールへと成長します。
多くの企業が経験する、チャットボット運用の課題6選
次に、チャットボットを運用する上で、多くの企業が経験する課題を6つ紹介します。自社の状況と照らし合わせながら、課題の原因を理解することが改善につながります。
課題1:導入した効果が分からない
最初の課題は、以下のようにチャットボットを導入した効果が分からないことです。
- 導入前に「解決率80%達成」のような具体的な目標数値(KPI:Key Performance Indicator)が設定されていない。
- 効果を測るためのデータ分析の仕組みが整っておらず、上司に費用対効果を説明できない。
成果が見えないと、改善の方向性が定まらず、担当者のモチベーション低下や関連予算の削減につながるリスクが発生します。
課題2:ユーザーに利用されない・認知されていない
二つ目の課題は、チャットボットがユーザーに利用されない・認知されていない点です。例えば「利用率が低い」「そもそも存在が知られていない」といった状況です。
その原因は、Webサイト上でチャットボットの場所が分かりにくいなど、ユーザーを誘導する仕組みが不十分なことです。
また、一度利用したユーザーが「使い方が難しい」「欲しい答えが見つからなかった」と感じ、次第に使われなくなるなどのケースもあります。
課題3:回答の精度が低く、役に立たない
三つ目の課題は、回答の精度が低く、チャットボットが役に立たないことです。
例えば「質問の意図を理解してくれない」「見当違いの回答が返ってくる」といった状況であり、主に以下のような原因が考えられます。
- 登録されているQ&Aデータが少ない。
- ユーザーが使う言葉の多様性(例:「料金」と「費用」)に対応できていない。
- 定期的な情報更新が行われていない。
回答の精度が低いと、ユーザーは自己解決を諦め、電話やメールで問い合わせることになります。その結果、本来の目的である問い合わせ削減効果が得られなくなります。
課題4:運用が特定の担当者に依存
四つ目の課題は、チャットボットの運用が特定の担当者に依存することです。
例えば「特定の担当者しか設定を変更できない」「担当者が休むと運用が止まる」といった状況です。この状況は「属人化」と呼ばれる状態であり、その原因として主に以下が挙げられます。
- 運用手順をまとめたマニュアルがない。
- 複数人で管理する体制が作られていない。
この状態は、担当者の退職によって運用が継続できなくなるだけでなく、多様な視点からの改善が進まない要因にもなります。
課題5:有人対応への切り替えが不親切
五つ目の課題は、チャットボットの有人対応への切り替えが不親切なことです。
例えば「チャットボットで解決できない場合、次にどこへ連絡すればよいか分からない」「有人チャットにつながるまで長時間待たされる」といった状況があり、その主な原因として、以下が挙げられます。
- チャットボットで対応する範囲と人が対応する範囲の切り分けが曖昧。
- 担当者へ引き継ぐ手順が決められていない。
これにより顧客満足度が下がり、チャットボットだけでなく企業全体の印象を損なうリスクが発生します。
課題6:チャットボット後のメール対応で新たな課題が発生する
最後に紹介する課題は、チャットボット後のメール対応で新たな課題が発生することです。チャットボットで解決できない複雑な問い合わせは、メールや電話などの有人対応に引き継がれます。
その際、メール対応において次のような新たな課題が発生します。
- 「誰がどのメールに返信しているか分からない」
- 「複数の担当者が同じメールに返信してしまう(二重返信)」
- 「対応が遅れてしまう(返信漏れ)」
これらは、チャットボットで一次対応を効率化しても改善につながりません。どれだけ優れたチャットボットを導入しても、この最後のメール対応でミスがあれば、顧客満足度は大きく低下します。
この「チャットボット後のメール対応」という最後の重要なポイントを強化して、顧客体験を完成させるのが、メール共有・管理システム「メールディーラー」です。
チームの対応状況をリアルタイムで可視化し、返信漏れや二重対応をシステムで根絶。さらに、最新のAI機能「カスタム生成」が返信文の作成をアシストし、引き継がれた複雑な問い合わせにも、迅速かつ高品質な対応を実現します。
チャットボット運用の課題を解決する4つのステップ
前述のチャットボット運用における課題を解決し、成果を出すための具体的なアクションを4つのステップに分けて解説します。この手順に沿うことで、チャットボット運用の改善をスムーズに進められます。
ステップ1:現状把握と目標数値(KPI)の設定
まずは「チャットボットで何件の問い合わせを解決できたか(解決率)」や「サイト訪問者のうち何人が利用したか(利用率)」など、現状を客観的な数値で把握しましょう。
その上で「3カ月後までに解決率を10%向上させる」のようなKPIを設定します。このKPIが、チャットボット運用改善のゴールとなります。
ステップ2:Q&Aデータの質と量を改善する
次に、チャットボットの回答の精度を上げるためにQ&Aデータの質と量を改善します。
まず、チャットの履歴(ログ)を分析し「ユーザーがどのような言葉で質問しているか」「回答できなかった質問は何か」をリストアップしましょう。
次に、リストアップした内容にもとづき、Q&A追加と既存回答の修正を行います。その際に、専門用語を簡単な言葉に言い換えるなどの工夫も重要です。
ステップ3:利用率向上のための導線を見直す
その次は、チャットボットの利用率向上のための導線を見直しましょう。例えば、Webサイトの画面右下など、ユーザーの目に留まりやすい位置に常に表示させることが有効です。
さらに「よくある質問」や「お問い合わせ」ページの上部にチャットボットを設置しましょう。「まずはこちらでお試しください」と案内するなど、ユーザーが問い合わせをしたくなるページで積極的にアピールすることも重要です。
ステップ4:運用体制とルールを整備する
最後は「属人化」を防ぐため、チャットボットの運用体制とルールを整備しましょう。主担当と副担当を置くなど、複数人で運用チームを組むことが効果的です。
また「月に一度、チャット履歴を見ながら改善会議を行う」「Q&Aを追加・修正する際の承認手順」など、具体的な運用ルールを定めることが重要です。
失敗しないチャットボットツールの選び方
これからチャットボットの導入や乗り換えを検討している企業向けに、失敗しないツール選びのポイントを3つ解説します。
「実際にチャットボット導入・運用をする際のツール選びは、どのような点を重視すればよいのか」などの問題を解決していきます。
ポイント1:分析機能が分かりやすく、充実しているか
一つ目のポイントは「チャットボットツールの分析機能が分かりやすく充実しているか」です。目標数値を測り、改善につなげるためには、詳細な分析機能が不可欠です。
確認すべき機能は次の3つです。
- 利用率や解決率を自動で集計する機能
- 回答できなかった質問の一覧を表示する機能
- ユーザーからのフィードバック機能
これらの機能が、誰でも簡単に使えるかどうかを確認しましょう。特に、分析データが一目で分かる管理画面になっていると、日々の改善が進めやすくなります。
ポイント2:Q&Aのメンテナンスが簡単に行えるか
二つ目のポイントは「Q&Aのメンテナンスが簡単に行えるか」です。「管理画面の使いやすさ」や「専門知識がなくても設定変更できるか」などを確認してください。
その際は、無料トライアルなどを活用しましょう。実際に管理画面を操作して、自社の担当者が使いこなせそうかを確認することが重要です。
ポイント3:提供会社のサポート体制は手厚いか
三つ目のポイントは、チャットボット導入時だけでなく、運用開始後もサポート体制が手厚い提供会社を選ぶことです。
次のようなサポートがあるか確認しましょう。
- 「定期的な利用状況レポートの提出」
- 「データにもとづいた改善点の提案」
- 「操作方法に関する勉強会の開催」
また、自社の人員に不安がある場合は、初期設定や運用の一部を代行してくれるサービスがあるかどうかも確認してください。
まとめ:チャットボット運用の成功は「継続的な改善」が重要
チャットボットは導入がゴールではありません。KPIのもと、データにもとづいた継続的な運用を行うことで初めてその価値を発揮できます。
そのためには、定期的に利用状況を見直し、Q&Aを更新し続けることが重要です。ユーザーにとって「本当に役立つ」チャットボットへと成長させることが、運用の成功につながります。
そして、チャットボットで一次対応を効率化した先に待っているのが、より複雑で専門的な問い合わせです。これらの対応品質を高めることが、顧客満足度をさらに向上させるための重要なポイントです。
チャットボットの先の「メール対応」で生まれる新たな課題
チャットボットによって、よくある質問への対応は大幅に効率化できます。しかし、チャットボットで解決できない複雑な問い合わせや、専門的な対応が必要なケースがあります。その場合、オペレーターによるメール対応に集約されることが多いです。
その先のメール対応で「対応状況が不明で返信が遅れる」「同じ問い合わせに二人が返信してしまう」といった課題が残っていては、顧客対応全体の品質向上にはつながりません。
その解決策として、メール共有・管理システムの「メールディーラー」の活用が有効です。
チームのメール対応を効率化するなら「メールディーラー」

出所:メールディーラー公式Webサイト
「メールディーラー」は、チームに届くメールの対応状況(未対応、対応中など)を全員で可視化し、返信漏れや二重対応を防ぎます。誰がどのメールを担当しているかが一目で分かるため、スムーズな連携の実現が可能です。
さらに「メールディーラー」にはAI機能が搭載されています。
| 機能名 | 内容 |
|---|---|
| リスク検知 | 受信したメールの内容をAIが感情分析を行い、クレームリスクのあるメールを事前に検知する機能です。 |
| カスタム生成 | AIが受信メールの内容と担当者が入力した「返信文作成の要点」をもとに、適切な返信文を自動作成します。 |
| 自動生成 | 蓄積された過去の対応履歴やFAQなどのナレッジをもとに、問い合わせに対して適切な回答をAIが自動生成します。 |
これらの機能は、メール作成にかかる時間の短縮や対応品質の均一化、顧客満足度の向上に貢献します。
チャットボット運用と合わせて「メールディーラー」を導入することで、一次対応から専門的な二次対応まで、一貫して品質の高い顧客体験の提供が可能です。「メールディーラー」の導入が貴社の業務にどう貢献できるか、ぜひ無料のトライアルで体験してください。
要点を入力するだけで返信文を自動生成する「カスタム生成」は、下記リンクのデモ画面ですぐにお試しいただけます。簡単なキーワードが、どのように自然で丁寧なメールに変換されるか、ぜひご自身の目でお確かめください。
※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス(以下「当社」といいます)または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。