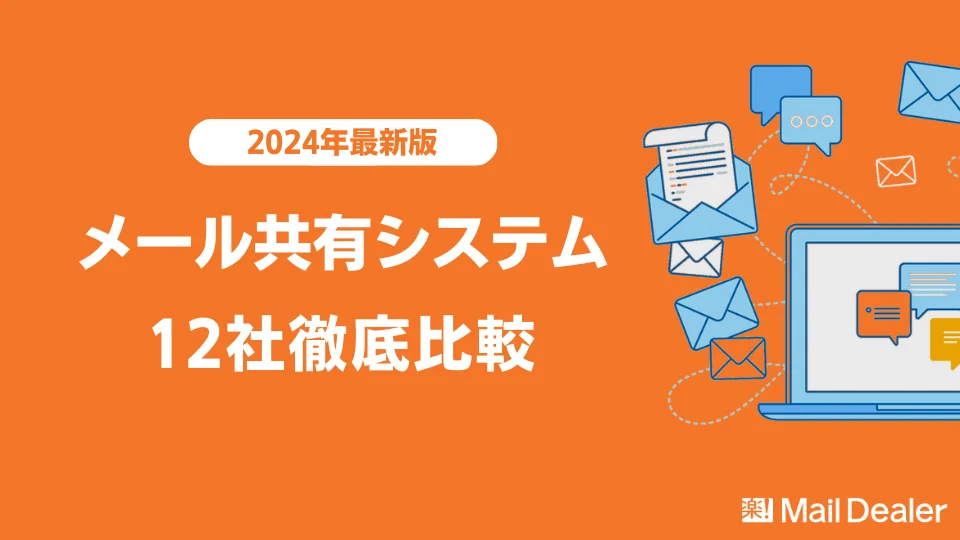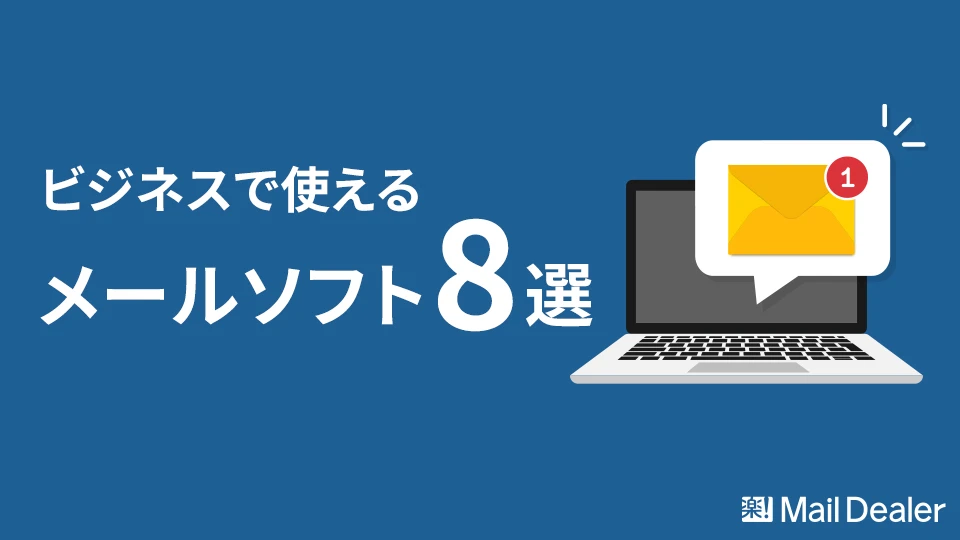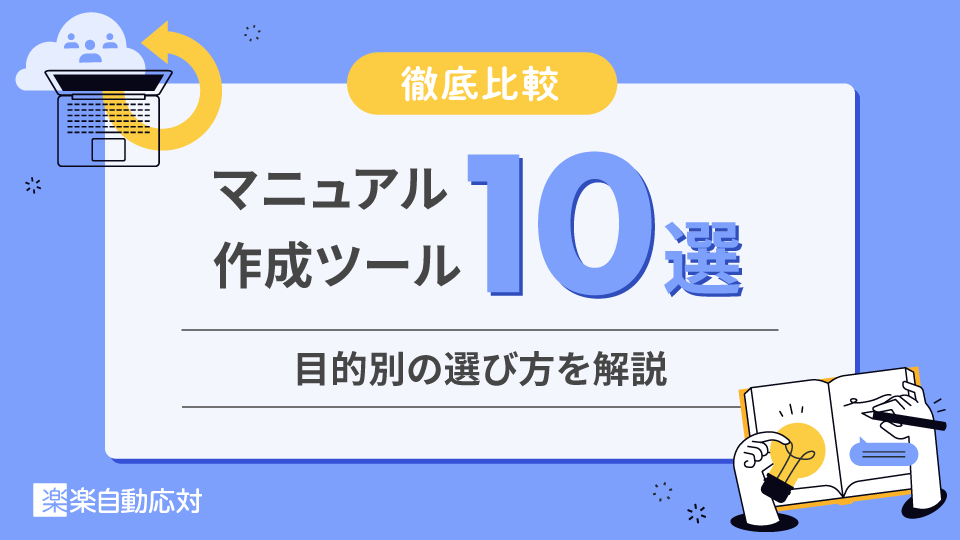
「マニュアル作成に時間がかかる」「品質がバラバラで活用されない」といった課題はありませんか?従来のWordなどでの作成は、業務の属人化や生産性の低下を招きがちです。一方でマニュアル作成ツールを導入すれば、誰でも効率的に高品質なマニュアルを作成・運用できます。
本記事では、ツールのメリットや目的別の選び方、失敗しないための比較ポイント、厳選したおすすめツール10選を詳しく解説します。本記事を読めば貴社に合ったツールが見つかります。
マニュアル作成ツールとは?導入で得られる3つのメリット
マニュアル作成ツールは作成から共有、更新、活用までを一元管理するための専用システムです。単なる文書作成ツールではなく、組織の生産性向上と業務標準化を推進します。
ここからは、ツールの導入によって得られる3つのメリットを紹介します。
メリット1:作成工数の大幅な削減と品質の向上
マニュアル作成ツールは、見やすいテンプレートや画像編集機能が標準搭載されています。これによりデザイン調整や別ツールでの画像加工といった手間の削減が可能です。
さらに、パソコン画面の操作を自動で記録するキャプチャ機能やAIによる文章生成支援などの機能が搭載されているツールもあります。これらを活用することで、作成者のスキルに依存せず、誰でも短時間で高品質なマニュアルが作成できます。
メリット2:マニュアル品質の標準化とガバナンス強化
作成者ごとにフォーマットや言葉遣いがバラバラなマニュアルは、読みにくいだけでなく、業務ミスの原因にもなります。マニュアル作成ツールを導入すれば、作成者ごとのばらつきを防ぎ、全社で統一された分かりやすいマニュアルを維持し、業務ミスの削減につながります。
また、版数管理や承認フロー機能が搭載されているツールも多いです。内容の正確性と信頼性を担保し、企業のガバナンス強化に貢献します。
メリット3:ナレッジの蓄積と戦略的な活用促進
マニュアル作成ツールは、個人の経験や直感、ノウハウなどの主観的な「暗黙知」を客観的に表現し、誰もが理解できる「形式知」へ変換できます。
これにより、組織全体の知的資産として蓄積することができ、ツールによっては、閲覧履歴や検索キーワードを分析できるものもあります。
その結果「どこで従業員がつまずいているか」「どのような情報が求められているか」を把握し、継続的な業務改善や教育研修の高度化が可能です。
【4つの目的別】マニュアル作成ツールの選び方
マニュアル作成ツールを選ぶ際に重要なのは「何のためにマニュアルを作るか」です。
ここでは4つの目的に分類し、それぞれに適したツールの特徴と、確認すべき具体的な機能について解説します。
業務手順書を作成したい場合
| 対象業務 | テキストと画像で正確に手順を伝えたい業務に有効です。 (例) 経理・総務などのバックオフィス業務フロー 店舗オペレーション コールセンターの応対手順 |
|---|---|
| 選ぶべきツール | ステップ形式で手順を分かりやすく見せられるツールがおすすめです。チェックリスト機能や承認フロー機能があると、業務の実行管理まで行えます。 |
システム・アプリの操作手順書を作成したい場合
| 対象業務 | パソコンの画面上で操作を説明したい業務に有効です。 (例) 新規導入したSaaS(Software as a Service) 基幹システムの操作方法 情報システム部門が行うパソコンのセットアップ手順 |
|---|---|
| 選ぶべきツール | 操作画面の自動キャプチャ機能は必須です。さらに、作成したマニュアルを多様なファイル形式(Word、PDF、HTML5など)に出力できるか確認しましょう。 |
現場作業向けの動画マニュアルを作成したい場合
| 対象業務 | 文章化しにくい「動き」や「コツ」を伝えたい業務に有効です。 (例) 製造ラインの作業手順 機器のメンテナンス方法 調理や接客の手本 |
|---|---|
| 選ぶべきツール | スマートフォンでの撮影・編集が簡単なツールがおすすめです。さらに、字幕の自動生成や多言語への翻訳機能があると、外国人スタッフへの教育にも対応できます。また、視聴状況の分析機能も重要です。 |
社内ナレッジの蓄積・共有を強化したい場合
| 対象業務 | 組織内のあらゆる情報を一元管理し、有効活用したい業務に有効です。 (例) 社内FAQ 議事録 営業日報 |
|---|---|
| 選ぶべきツール | 添付ファイル(Word、PDFなど)の中身まで検索できる高度な検索機能を持つツールがおすすめです。コメント機能や共同編集機能があると、コミュニケーションの活性化にもつながります。 |
マニュアル作成ツール選定で失敗しないための比較ポイント5選
マニュアル作成ツールを比較検討する際、機能の多さだけでなく、組織に定着し使い続けられるかが重要です。
導入後のミスマッチを避けるため、チェックすべき5つの比較ポイントを解説します。
ポイント1:誰でも直感的に使える操作性か
作成したマニュアルをIT部門だけでなく、現場の従業員が更新できるか確認しましょう。その際に、専門知識が不要なシンプルなUI/UXは必須です。
また、無料トライアルでは必ず複数の部署や役職の担当者に実際に利用してもらいましょう。その際に、操作性に関するフィードバックを集めることが重要です。
ポイント2:マルチデバイスに対応しているか
店舗スタッフや現場作業員など、パソコンを持たない従業員でもスマートフォンやタブレットで、手軽にアクセスできるかを確認しましょう。
専用アプリの有無やオフライン環境でも閲覧できる機能があると、実際の業務での利用シーンが格段に広がります。
ポイント3:検索機能や管理機能は充実しているか
キーワード検索の精度だけでなく、タグ付けやカテゴリ分類など、マニュアルが増えても必要な情報にすぐ辿り着けるか確認しましょう。
また、ユーザー・グループごとの詳細なアクセス権限設定やIPアドレス制限、監査ログ機能など、組織の規模やルールに応じた管理機能も重要です。
ポイント4:セキュリティ対策は万全か
企業のノウハウという機密情報を預けるため、マニュアル作成ツールの通信の暗号化(SSL/TLS)やデータのバックアップ体制などを確認しましょう。
また、標準規格である「ISO/IEC 27001」などの第三者認証を取得しているかどうかも、信頼性を判断する上で重要です。
ポイント5:サポート体制は手厚いか
マニュアル作成ツール導入時に、初期設定やデータ移行の支援があるか確認しましょう。また、導入後のカスタマーサクセスがあるかどうかも重要です。
さらに、電話やメール、チャットでの問い合わせ対応に加え、オンラインヘルプやユーザーコミュニティが充実していると自己解決が進めやすいです。
【目的別】おすすめのマニュアル作成ツール比較10選
ここからは、解説した選び方とポイントを踏まえ、おすすめのマニュアル作成ツールを用途別に分けて10個紹介します。
【業務手順書向け】おすすめマニュアルツール3選
テキストと画像が中心の業務マニュアル作成に強みを持つ「業務手順書向け」ツールを3つ紹介します。テンプレートの豊富さや、誰でも迷わず使えるシンプルな操作性がポイントです。
Teachme Biz(株式会社スタディスト)
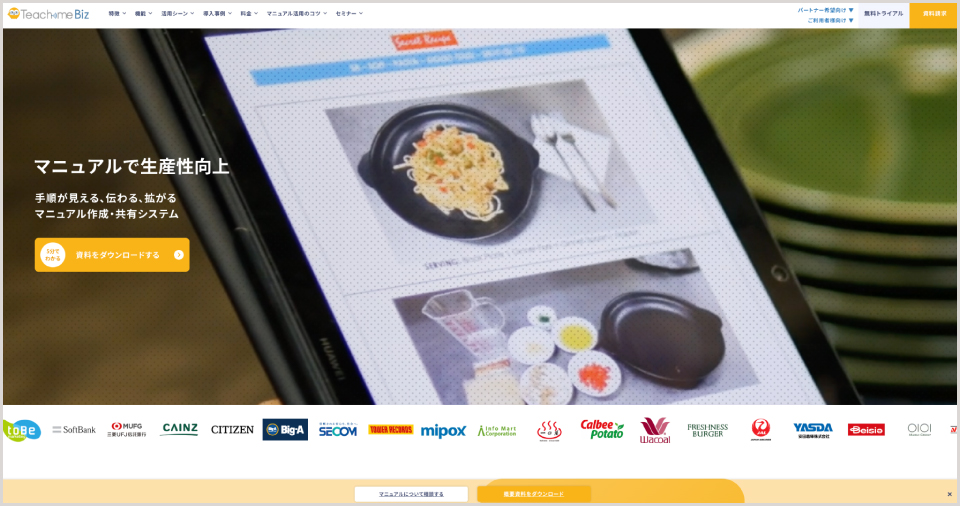
出所:Teachme Biz公式Webサイト
Teachme Bizは、画像や動画をベースにしたステップ形式のマニュアルを直感的に作成できるツールです。マニュアルの閲覧状況やテスト結果を管理できるため、教育の進捗管理や習熟度の可視化に貢献します。
小売・飲食・製造業など、多店舗・多拠点で業務標準化を進めたい企業におすすめです。導入費用は月額59,800円(税抜)からです。(2025年9月時点)
COCOMITE(コニカミノルタ株式会社)

出所:COCOMITE公式Webサイト
COCOMITEは、Wordのような感覚で使えるシンプルな編集画面が魅力で、ITツールに不慣れな従業員が多い企業におすすめです。
また、既存のOfficeファイルをインポートしてマニュアル化できるため、まずはスモールスタートしたい企業にも向いています。料金は月額29,600円(税抜)からで、別途初期費用の150,000円(税抜)が必要です。(2025年9月時点)
ヘルプドッグマニュアル(noco株式会社)

出所:ヘルプドッグマニュアル公式Webサイト
ヘルプドッグマニュアルは、タイトルを入力するだけで、AIが構成のたたき台を自動生成します。そのため、マニュアル作成ノウハウがない企業におすすめです。
さらに、作成したマニュアルはQRコードで簡単に共有できます。現場の機器や什器に貼り付けておくことで、必要な時にすぐスマートフォンで確認できます。料金は月額35,000円(税抜)からです。(2025年9月時点)
【操作手順書向け】おすすめマニュアルツール3選
社内システムやSaaSの操作方法など、パソコン画面の操作説明に特化したツールを3つ紹介します。操作画面の自動キャプチャ機能や、多様なファイル形式への出力機能がポイントです。
Dojo(株式会社テンダ)
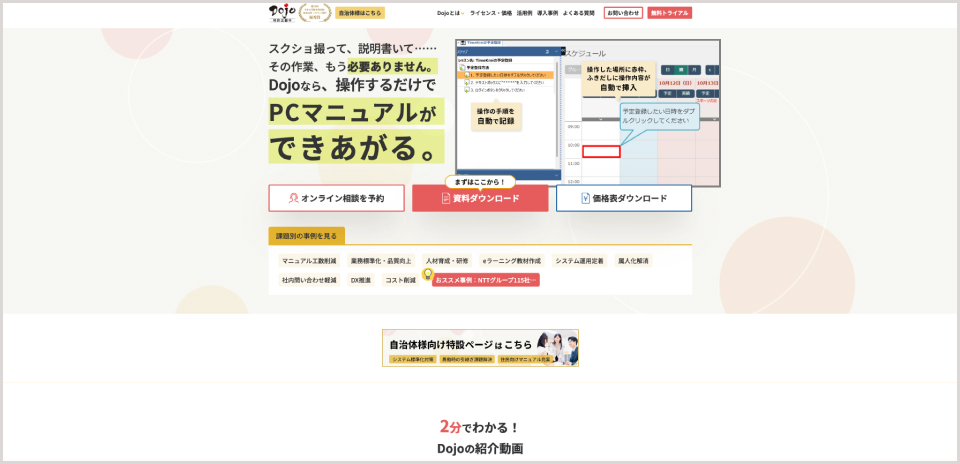
出所:Dojo公式Webサイト
Dojoは、パソコン操作を録画するだけで、スクリーンショットと操作説明文を含む多様な形式のマニュアルを自動生成します。WordやExcelだけでなく、HTML5形式で出力すればeラーニングコンテンツとしても活用できます。
社内システムの操作マニュアルを大量に作成する必要がある情報システム部門におすすめです。料金は問い合わせが必要で、販売形態は買い切りライセンス型です。(2025年9月時点)
iTutor(株式会社Blue Port)

出所:iTutor公式Webサイト
iTutorは、操作画面の自動録画に加え、eラーニング用のテストコンテンツや操作を疑似体験できるシミュレーション作成機能を搭載しています。
マニュアルを作るだけでなく、作成後の従業員の理解度測定や定着までを一貫して行いたい研修担当者におすすめです。料金は380,000円(税抜)からの買い切りライセンス型です。(2025年9月時点)
ManualForce(Orange Moon株式会社)

出所:ManualForce公式Webサイト
ManualForceは、ブラウザやデスクトップ上の操作を自動で記録し、フローチャート形式のマニュアルを生成します。
業務プロセスの可視化も同時に行えるため、ロボットによる業務自動化(RPA:Robotic Process Automation)におすすめです。導入前の業務整理や「どの作業を任せるか」といった要件定義にも活用できます。料金は、1ユーザーあたり月額2,800円(税抜)からです。(2025年9月時点)
【動画マニュアル向け】おすすめマニュアルツール2選
製造ラインの作業や機器のメンテナンスなど、動画マニュアルに適したツールを2つ紹介します。専門知識がなくても直感的に動画を編集できるかが選ぶポイントになります。
tebiki(Tebiki株式会社)
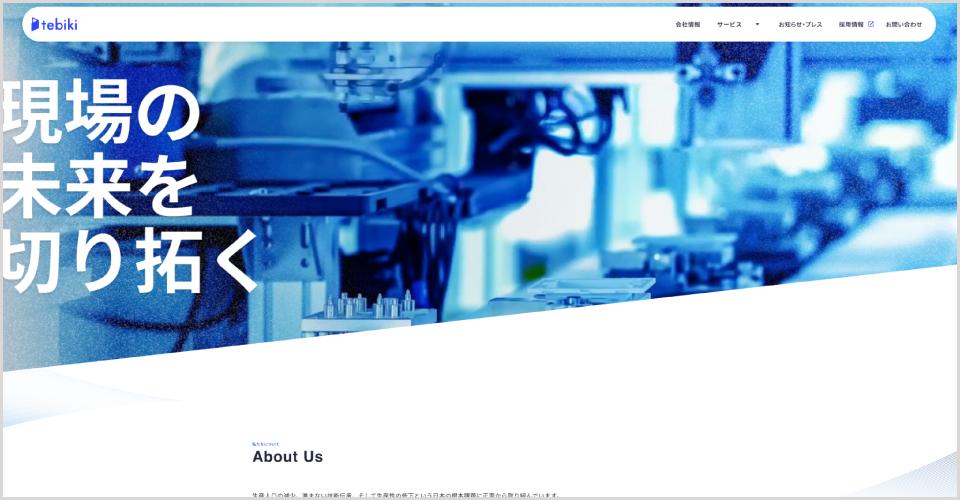
出所:tebiki公式Webサイト
tebikiは、現場作業をスマートフォンで撮影するだけで、AIが音声を認識して100以上の言語に自動翻訳します。技能伝承や安全教育といったテーマに強く、外国人スタッフが多く在籍する製造業や物流業、建設業などにおすすめです。なお、料金は問い合わせが必要です。(2025年9月時点)
VideoStep(株式会社VideoStep)

出所:VideoStep公式Webサイト
VideoStepは、PowerPoint資料をアップロードするだけで、AIがナレーション付きの動画マニュアルを自動生成します。大量のPowerPoint研修資料を活用して動画化したい企業におすすめです。料金は月額60,000円からで、別途初期費用がかかります。(2025年9月時点)
【ナレッジ共有向け】おすすめマニュアルツール2選
マニュアルだけでなく、社内のFAQや議事録、業務ノウハウなどのナレッジ共有に適したツールを2つ紹介します。必要な情報をすぐに見つけ出せる強力な検索機能がポイントです。
NotePM(株式会社プロジェクト・モード)

出所:NotePM公式Webサイト
NotePMはWordやExcelなど添付ファイルの中身まで全文検索できる検索機能を備えています。さらに、柔軟なフォルダ構成とゲストアカウント機能も利用できます。
マニュアルや議事録、日報など、社内に散在する文書情報を一元管理したい企業におすすめです。料金は月額4,800円(税込)で32ユーザーから利用可能です。(2025年9月時点)
Confluence(アトラシアン株式会社)

出所:Confluence公式Webサイト
Confluenceは、プロジェクト管理ツール「Jira」との連携に優れ、開発関連のドキュメント管理に強いです。また、豊富なテンプレートとマクロ(拡張機能)によりカスタマイズ性に優れています。
エンジニアが多く在籍し、アジャイル開発などを進めているIT企業におすすめです。料金は10ユーザーまで無料で利用可能で、有料プランはユーザー数に応じて変動します。
まとめ:AI活用とツール選定で業務の属人化を防ごう
本記事では、マニュアル作成ツールのメリットや目的別の選び方、ツール選定で失敗しないポイントを解説しました。
近年ではAI機能の搭載が進んでおり、文章の下書き作成や動画編集などの自動化により、担当者はより本質的な業務に集中できます。さらに、自社に合ったツールの導入は、単なる工数削減だけでなく、業務品質の標準化や属人化の解消につながります。
メール対応業務の品質を標準化して属人化を解消しよう
メール対応の品質標準化や属人化解消の手段として、マニュアル作成が有効な手段の一つですが、作成後の運用に課題を抱えることがあります。マニュアルは作成して終わりではなく、活用していくことが重要です。
特に、顧客対応では「ファイルを開き、キーワードで検索する」という手間により、対応が遅れることがあります。また、情報が古かったり、担当者によって解釈が異なったりすることで、マニュアルがあるのに対応品質がバラバラになる問題も起こりがちです。
そこで、メール共有・管理ツール「メールディーラー」があれば、AIが過去のやり取りやFAQをもとに回答案を作成してくれるため、担当者はマニュアルを「探す」手間と「回答を作る」手間の両方が不要になります。
その結果、担当者は複数ファイルを探し回る手間や、ゼロから回答文を作成する負担から解放されます。「メールディーラー」は、新人でもベテランと同じ品質の回答を迅速に返せるようになるため、顧客対応の品質標準化と業務効率化を同時に実現する、現実的な選択肢の一つです。
AI搭載の「メールディーラー」でメール業務を効率化

出所:メールディーラー公式Webサイト
「メールディーラー」は、チームのメールを一つの受信箱で一元管理が可能です。これにより、各メールの「対応状況」や「担当者」を全員で可視化することで、対応漏れや二重返信を防ぎます。
さらに「メールディーラー」のAI機能はメール業務の効率化を図り、担当者の負担を軽減します。
主な機能は次の通りです。
- 優先すべきメールをAIが判別して通知する「リスク検知」
- 要点を入力するだけで問い合わせ返信の文を作成する「カスタム生成」
- よくある問い合わせにAIが回答案を提示する「自動生成」
「カスタム生成」の機能を体験できる無料のデモ画面を用意しています。実際にキーワードを入力してどのようなメール文章が作成できるかをぜひお試しください。
「メールディーラー」は、これらの機能でチームのメール対応を強力にサポートし、業務効率化と顧客満足度の向上を実現します。サービスの詳細をまとめた資料を無料でご用意しております。まずは情報収集からという方も、ぜひお気軽にご覧ください。
※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス(以下「当社」といいます)または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。