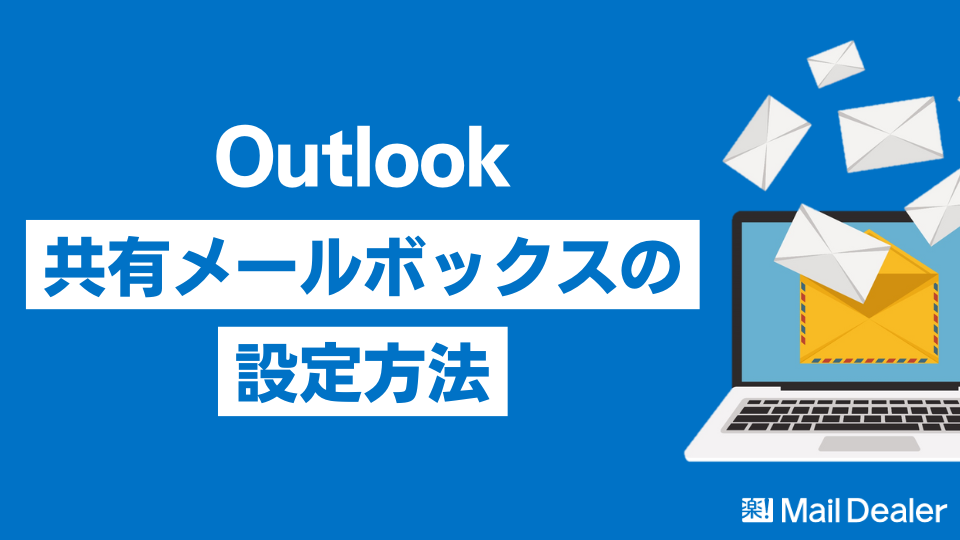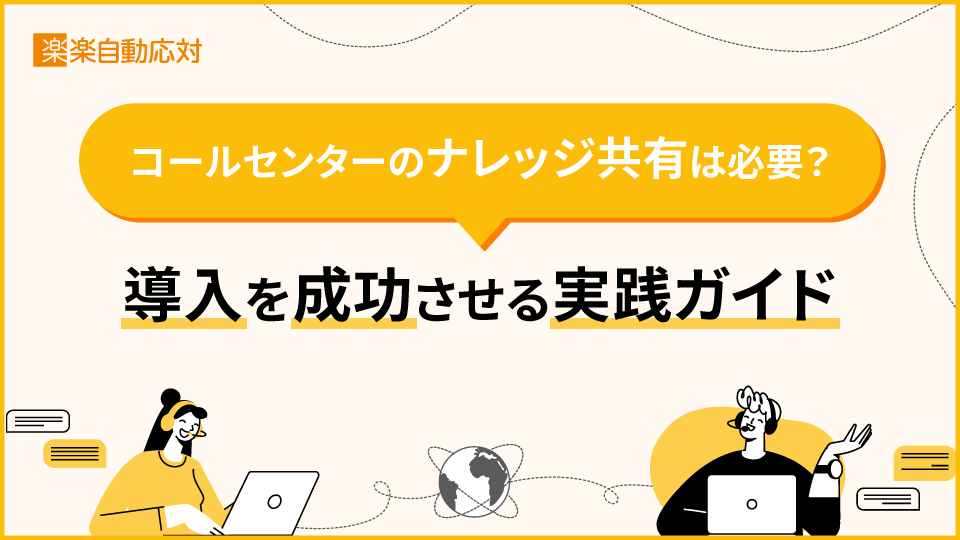
コールセンターでオペレーターの応対品質のばらつきや、質問への応対が滞ることはありませんか?その原因は、個人の知識やノウハウが共有されない「ナレッジの属人化」にあるかもしれません。
本記事では、コールセンターにおけるナレッジ共有の重要性とメリット、共有が進まない原因を解説します。また、ナレッジ共有を成功させる具体的なステップや、業務効率を向上させるツールの選び方も紹介します。本記事を読むことで、顧客満足度の高いコールセンターを構築するための実践的なヒントが得られるのでぜひ、最後までご覧ください。
なぜ今、コールセンターでナレッジ共有が重要視されるのか
コールセンターでナレッジ共有が重要視される理由を4つの課題から解説します。
問い合わせ内容の高度化・複雑化
近年、顧客自身がWebサイトのFAQなどで簡単な疑問を自己解決するようになった結果、コールセンターには、より高度で複雑な問い合わせが集中する傾向にあります。
こうした難易度の高い質問は、一人のオペレーターの知識や経験だけで対応するのは困難であり、回答までに時間がかかったり、不正確な案内をしてしまったりと顧客満足度を大きく損なう原因となります。
この課題を解決し、どんな難しい質問にも組織として質の高い回答を提供するために、個人の知識をチーム全体の資産に変える「ナレッジ共有」の仕組みが、これまで以上に重要視されています。
顧客満足度の向上
顧客満足度を向上させるためにコールセンターに求められるのは「速さ」と「正確さ」です。この2つを両立するには、ナレッジ共有が重要です。「どのオペレーターでも同じレベルの的確な案内ができる」といった応対品質の標準化は顧客の安心感と企業の信頼向上に結びつきます。
業務効率化の促進
コールセンター業務の効率化にナレッジ共有は効果的です。例えば、ナレッジ共有によってオペレーターが回答を探し、上司への確認が減ることで、1件あたりの対応にかかる時間(ATT:Average Talk Time)を短縮できます。
また、よくある質問への回答文をテンプレート化することで、対応後の報告書作成といった後処理業務も効率化できます。
オペレーターの負担軽減と離職率低減
オペレーターの負担軽減に効果的なのは、ナレッジ共有がもたらす「答えがすぐに見つかる」という心理的な安心感です。これにより、難しいクレーム対応時のストレスを和らげ、オペレーターが自信を持って顧客と向き合える環境を作ることができます。
また、整理されたナレッジは、オペレーターが新しい知識を学ぶために役立ちます。自身の成長を実感できることが仕事へのやりがいと定着率の改善につながります。
コールセンターにおけるナレッジ共有のメリット3選
ナレッジ共有はコールセンターの目標値の達成につながる大切な取り組みです。次に、コールセンターにおけるナレッジ共有のメリットを3つ紹介します。
メリット1:応対品質の標準化と属人化の防止
ナレッジ共有によって、応対品質を標準化できるメリットがあります。応対が上手なオペレーターのコツや言い回しを共有することで、チーム全体のサービスレベルを高い水準で安定させます。
さらに、特定の優秀な社員に業務が依存してしまう「属人化」を防ぐ効果もあります。例えば「エース社員のAさんが辞めた途端、顧客からの評判が落ちてしまった」といった属人化がもたらす失敗例があります。ナレッジ共有を行うことで「あの人がいないと分からない」という状態からの脱却が可能です。
メリット2:新人オペレーターの教育コスト削減
整備されたナレッジベースは「24時間いつでも質問に答えてくれる教科書兼トレーナー」として機能するため、ナレッジ共有によって、コールセンターの新人オペレーターの教育コストを削減できるメリットがあります。
従来、新人オペレーターは不明点があるたびに先輩や教育担当者の手を止めて質問する必要がありましたが、ナレッジベースがあればまず自分で調べる習慣が身につきます。
これにより、新人が自ら問題を解決する力が養われ、早期戦力化が実現します。結果として、教育担当者が同じ質問に繰り返し答える手間が省かれ、研修期間全体の短縮とコスト削減につながるのです。
メリット3:顧客の自己解決率を高め、入電数を削減する
コールセンター内に蓄積されたナレッジは、顧客向けのFAQコンテンツとして公開することで、顧客の自己解決を促し、入電数そのものを削減する効果があります。
オペレーターが日々活用している社内向けのナレッジこそが、顧客が本当に知りたいことに対する最も実践的で正確な回答であるため、この情報を社内だけに留めず、顧客に開放することは有効です。
例えば、社内で頻繁に参照される「よくある質問トップ10」を、そのまま顧客向けのFAQページとして公開するだけで、同様の問い合わせ電話を大幅に減らすことが可能です。その結果、オペレーターはより複雑な問題解決に集中でき、コールセンター全体の生産性と顧客満足度を同時に高めることができます。
【課題別】コールセンターのナレッジ共有が進まない4つの原因
コールセンターのナレッジ共有が進まない原因は主に4つありますので、それぞれ解説していきます。
原因1:曖昧な作成・更新ルール
まずは、ナレッジ共有のデータやマニュアルを作成・更新するルールが曖昧なことです。これにより、ファイルの保存場所や名前の付け方がバラバラといった、情報が整理されていない管理体制になります。
その結果「ナレッジはあるはずなのに、誰も見つけられない」という状態に陥り、かえって仕事の効率を下げてしまいます。
原因2:点在するナレッジの保管場所
2つ目の原因は、ナレッジの保管場所が点在することが挙げられます。例えば、共有サーバーやExcel、チャット、個人のパソコン内などにバラバラに保管されている状態です。
その結果、1つの質問に答えるためにあちこち探し回る手間が発生し、顧客を待たせてしまうことにつながります。
原因3:業務量が多く蓄積する時間が不足している
3つ目の原因は、多忙な業務でナレッジを蓄積する時間がないことです。1件の対応が終わるとすぐに次の電話が鳴るといった、忙しいコールセンターでは、ナレッジを記録・整理する時間の確保が困難です。
その結果、現場の「頑張り」や「善意」だけではナレッジの共有を続けるのが難しく、後回しになることで改善が進まなくなります。
原因4:ナレッジ共有の文化が育っていない
最後の原因は、ナレッジ共有の文化が育っていない点です。例えば「自分のコツを共有しても特に評価されない」「失敗談を共有すると怒られるかも」といった、不安やためらいが共有の妨げになります。
その結果、効果的なナレッジが組織全体に共有されず、組織としての学習や成長が滞ります。
ナレッジ共有を成功に導く4つのステップ
ナレッジ共有を「頑張ろう」という気持ちだけでなく、具体的な手順を踏んで進めることが重要です。
ここからは、ナレッジ共有を成功させるための4つのステップを解説します。
ステップ1:目的とゴールを明確化する
まずは、ナレッジ共有の目的とゴールを明確化します。「なんとなく対応がバラバラ」といった曖昧な課題から「上司への確認が1日平均50件発生している」など、具体的な数字で現状の問題を把握することから始めましょう。
その上で「上司への確認件数を半年で30%減らす」といった、誰が見ても達成度がわかる具体的なゴール(目標数値)を設定することが重要です。その結果、設定したゴールを関係者全員で共有することで「なぜ今これに取り組むのか」という目的意識がそろい、みんなで協力しやすくなります。
ステップ2:共有の範囲とルールを策定する
次は、ナレッジ共有の範囲とルールの策定です。まず「どのような情報を共有するか」(よくある質問、メールの返信例、トラブル解決の手順など)の範囲を決めましょう。次に「誰でも迷わず実践できる」ことを優先し、シンプルなルールを作ります。
例えば、タイトルの付け方を「【製品名】〇〇の操作方法」に統一する、登録時には必ずカテゴリを選ぶ、といった具体的なルールを定めます。
その際に、最初から完璧を目指さないことも大切です。まずは問い合わせが多い内容など、効果が出やすいところからのスモールスタートがおすすめです。
ステップ3:蓄積・整理の体制を構築する
次は、ナレッジの蓄積・整理の体制の構築です。まず、ナレッジを管理する「リーダー」やチームを正式に決め、その役割と責任を明確にしましょう。そして、従業員がどれくらいナレッジを使っているかなど、継続的に管理していく具体的な活動内容を共有しましょう。
その際に、現場のオペレーターが「これは良い情報だ」と思った時に、簡単にナレッジとして提案できるような流れを作ります。その結果、現場の生きた情報を集め続けることができます。
ステップ4:定期的な見直しと改善を行う
最後は、ナレッジの定期的な見直しと改善です。ナレッジの仕組みは「作って終わり」ではなく、顧客の変化にあわせて「育てていく」ものであるため、定期的な振り返りが重要になります。
例えば「よく見られているナレッジ」を登録した人の表彰や「検索しても答えが見つからなかった言葉」をヒントに新しいナレッジの追加といった取り組みです。
これにより、貢献が可視化され、社員は「自分の知識がチームの役に立っている」と実感できます。このようなポジティブなフィードバックは、社員のやる気を高め、さらなるナレッジ共有を促進する好循環を生み出します。
コールセンターのナレッジ共有に役立つツールの種類と選び方
ナレッジ共有の成功には、その活動を支える「ツール」選びは重要です。コールセンターという一分一秒を争う現場では、使いにくさや検索性の低さが、ツールの形骸化に直結するからです。 どれだけ優れたナレッジを蓄積しても、オペレーターが通話中に数秒で答えを見つけ出せなければ、そのツールは使われなくなってしまいます。
ここからはコールセンターでよく使われるツールを4つのタイプに分け紹介します。
さらに、自社に本当に合ったツールを選ぶ際に失敗しないための3つのポイントも解説します。
代表的なナレッジ共有・管理ツールの4分類
まずは、コールセンターでよく使われる代表的なツールを「社内wiki」「FAQシステム」「チャットボット」「メール共有・管理システム」の4つのタイプに分け、それぞれの特徴を解説します。
社内wiki
| 概要 | マニュアルや議事録など、文章中心の情報をチームで書き溜めていくツール。 |
|---|---|
| メリット | 部署を横断した情報共有の土台となり、エース社員に頼らない体制を築ける。 |
| デメリット | ルールがないと情報が混乱し、検索しても古い情報しか見つからなくなる。 |
| おすすめ業務 | 全社的な業務マニュアル管理・プロジェクトの議事録共有など。 |
FAQシステム
| 概要 | 「よくある質問と回答」をセットで管理し、必要な答えを素早く見つけ出すためのツール。 |
|---|---|
| メリット | 顧客向けに公開すれば自己解決を促し、電話の数を直接減らす効果が期待できる。 |
| デメリット | 複数の手順が絡む複雑な操作マニュアルなど、長文の管理には不向きな場合がある。 |
| おすすめ業務 | 定型的な質問が多いコールセンター・社内手続きに関するヘルプデスクなど。 |
チャットボット
| 概要 | 夜間や休日も含め、簡単な質問に24時間365日、自動で一次対応するツール。 |
|---|---|
| メリット | オペレーターは人でしか対応できない複雑な質問に集中できる環境を作れる。 |
| デメリット | 導入後の育成が必要で、シナリオ外の質問を有人へつなぐ機能も重要になる。 |
| おすすめ業務 | Webサイトでの問い合わせ一次受付・夜間や休日の定型的な案内など。 |
メール共有・管理システム
| 概要 | 問い合わせ対応とナレッジ活用を1つのツールでスムーズに行える操作性の高いシステム。 |
|---|---|
| メリット | 「先週の〇〇様への回答」といった過去の対応が、担当者情報とともに「生きたナレッジ」となる。 |
| デメリット | 製品によって対応チャネルが異なる場合がある。 |
| おすすめ業務 | メールでの問い合わせ対応・チームでの対応品質の平準化など。 |
そして、メール共有・管理システムの仕組みをさらに高いレベルで実現するのが、「メールディーラー」です。「メールディーラー」は、標準搭載のAIが過去の応対履歴を学習して返信案を自動生成します。過去のやり取りがそのまま生きたナレッジとなるため、ナレッジ管理からその先の返信文の作成まで不要になり、チーム全体で問い合わせ対応の省力化が図れます。
これにより属人化が解消され、対応スキルが標準化されることで、経験の浅い担当者でもベテランのような質の高い応対が可能になります。
自社に適切なツールを選ぶ3つのポイント
ツール選びで失敗しないためには「使いやすさ」が重要です。ここからは、自社に適切なツールを選ぶ3つのポイントを紹介します。
ポイント1:オペレーターの使いやすさ(操作性)
まず1つ目のポイントは「操作性」です。コールセンターではオペレーターが毎日使うツールだからこそ、機能の多さよりも誰でもストレスなく直感的に使えることが重要です。
ツールを選ぶ際は無料試用期間中に、必ず現場のオペレーターに実際に触ってもらいましょう。「マニュアルなしでも、大体の機能を使えるか」といった具体的な基準で評価してもらうためです。また、管理者がナレッジを登録したり、利用状況を確認したりする管理画面の使いやすさも大切です。専門知識がなくても、簡単に情報のメンテナンスができるかどうかも確認しておきましょう。
ポイント2:必要な情報へのアクセス性(検索のしやすさ)
2つ目のポイントは「検索のしやすさ」です。コールセンターでは、緊急を要する顧客への応対時に1秒でも早く答えにたどり着ける強力な検索機能は必須です。キーワード検索だけでなく、カテゴリやタグで絞り込める機能が充実しているかを確認しましょう。
さらに、言葉の揺れや「解約」と「退会」のような同じ意味の言葉を、賢く判断して検索してくれる「あいまい検索」機能があるかどうかでツールの利便性が変わります。
また、WordやPDFなどの添付ファイルの中身まで検索対象となるかどうかも、過去の資料を有効活用する上で重要です。
ポイント3:既存システムとの連携性
最後のポイントは「既存システムとの連携性」です。新しいツールを入れたことで仕事の流れが途切れてしまい、かえって非効率になる事態があります。それを避けるため、現在利用している顧客管理システム(CRM:Customer Relationship Management)などとスムーズに連携できるか確認しましょう。
例えば、電話と同時に顧客情報がパソコン画面に表示されるか、関連する過去のやり取りやナレッジも自動で表示されるかといった点です。
また、一度のログインで様々なシステムを使える仕組み(シングルサインオン)に対応しているかも確認しましょう。この機能は日々の手間を省き、セキュリティを高める上でも重要です。
まとめ:効率的なナレッジ共有でコールセンターの対応力を最大化しよう
本記事では、コールセンターにおけるナレッジ共有の重要性とその具体的な方法について解説しました。顧客からの質問がますます高度化・複雑化する中で、ナレッジ共有はもはや単なる業務改善ではなく、コールセンターが成長し続けるために不可欠です。
さらに、属人化した状態をなくし、組織全体の力で対応品質の安定とコスト削減を実現するためには、以下の3点が欠かせません。
- 明確な目的設定(何のために共有するのか)
- シンプルなルール(誰でも続けられる仕組み)
- 継続的な改善(ナレッジを育てていく意識)
そして、これらの取り組みをスムーズに進めるための適切なツールは、心強いパートナーとなります。それは単なるコストではなく、より良いコールセンターを実現するための重要な投資です。
特に重要な「メール対応」におけるナレッジ活用のポイント
数ある問い合わせチャネルの中でも、ナレッジ活用の効果を特に発揮しやすいのが、メールやチャットといったテキストでのやり取りです。
なぜなら、言葉遣いや説明の順序といった優れたノウハウが、具体的な「文章」としてそのまま残るからです。過去の分かりやすい返信メールや優れた対応履歴を「誰でも」「すぐに」見つけて真似できる仕組みこそが、対応の速さと品質を両立させるための鍵となります。
ナレッジ活用と業務効率化を同時に実現する「メールディーラー」

出所:メールディーラー公式Webサイト
チームでのメール対応におけるナレッジ活用と業務の効率化を、同時に実現するのがメール共有・管理システム「メールディーラー」です。
「メールディーラー」は、まずコールセンターの根本的な課題である「誰がどのメールに対応しているか分からない」「返信漏れや二重対応が起きてしまう」といった問題を解決します。その上で、豊富な検索機能やテンプレート共有機能が、チームのナレッジ活用を力強くサポートします。
さらに「メールディーラー」には、AIがクレームメールを検知する「リスク検知」や、担当者が指示文を入力するだけで自動で文章を生成する「カスタム生成」が搭載されています。さらにこれまでのナレッジをもとに自動で返信文を作成する「自動生成」が搭載予定です(本機能は2025年10月リリース予定)。
すでに9,000社以上で導入されており、17年連続売上シェアNo.1を獲得しています。実際の画面を試せる無料トライアルでご確認ください。
※出典:ITR「ITR Market View:メール/Webマーケティング市場2026」メール処理市場:ベンダー別売上金額推移およびシェア(2009~2025年度予測)
※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス(以下「当社」といいます)または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。