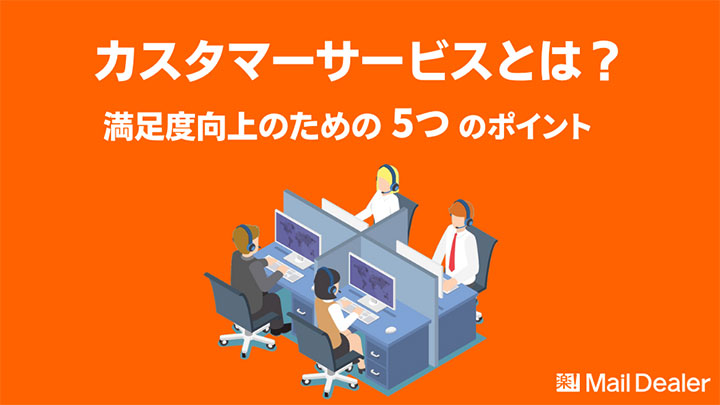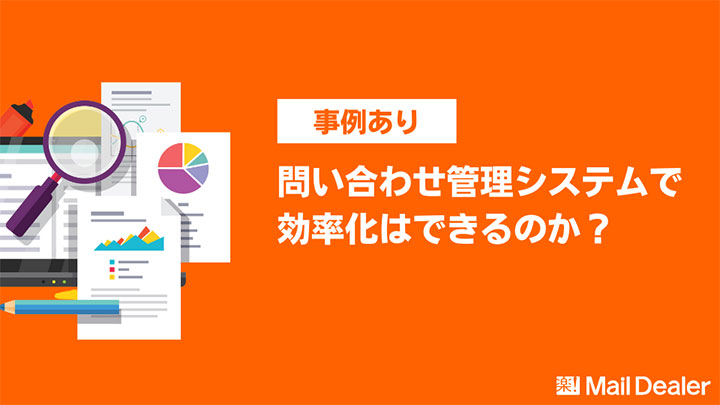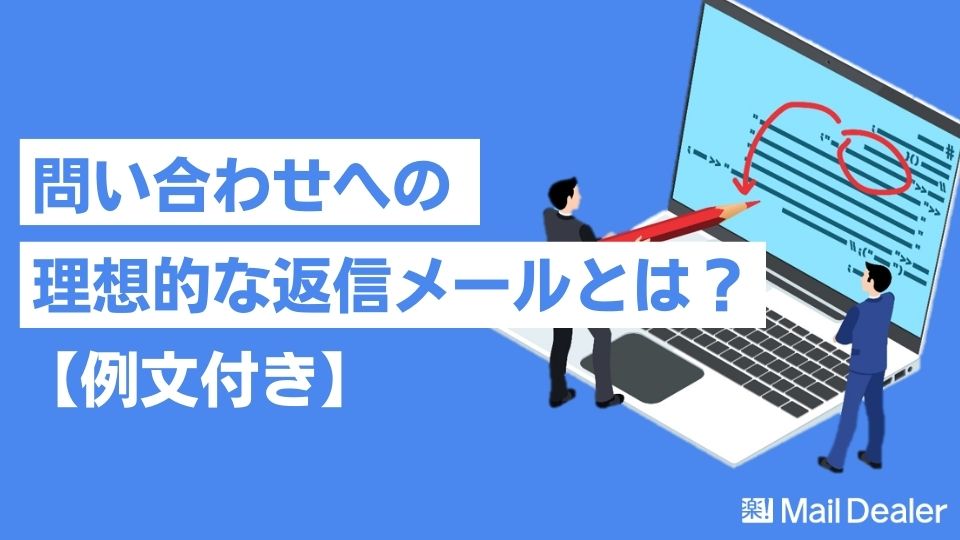毎日発生するメール業務は、労働生産性を大きく左右します。
今一度日頃のメール業務の在り方を振り返り、労働生産性を向上させるメール対応に切り替えることをおすすめします。
今回は、労働生産性を下げるNGメール習慣と改善方法について解説します。

毎日「2時間半」をメール業務に費やしている
ビジネスシーンでは、取引先からの注文など重要なメールから、メールマガジンなどの優先度が高くないメールまで、毎日さまざまなメールを受信しています。
一般社団法人日本ビジネスメール協会が実施した「ビジネスメール実態調査2021」によれば、1人が1日の間にビジネスでやり取りするメールは、平均で受信が51.1通、送信が16.63通という結果が出ています。受信メールを読む時間と送信メールを作成する時間を合計すると1日2時間半にものぼります。
この調査から見ても、メール業務をどのように効率化できるかが、労働生産性を決めるといっても過言ではないでしょう。
労働生産性を低下させる3つのNGメール習慣
具体的に労働生産性を低下させるメール習慣とはどのようなものなのでしょうか。
1.受信の都度メールを確認している
新着メールをすぐに開封している人は、メール受信の度に業務の手を止めることになるため、業務全体の労働生産性を低下させている可能性が高いでしょう。「重要なメールが来たときにすぐに対応できるから」と常にメールチェックをする習慣が、労働生産性を低下させる原因のひとつとなるのです。
2.優先順位をつけていない
優先順位をつけずに全てのメールに手当たり次第に対応するのは、労働生産性の観点から望ましいことではありません。
メールには、顧客からのクレームなどの重要度の高いメールから、対応が不要なメルマガなど、さまざまものがあります。全てのメールを同じ優先順位で受信順に処理していると、重要なメールが後回しになってしまう可能性があります。
3.Cc・Bcc送信を多用している
Cc・Bcc送信で社内の情報共有を行っていると、自分宛のメールと情報共有のメールがメールボックスに混在してしまいます。
顧客や取引先からの「対応が必要なメール」を見落としてしまうリスクが高まるでしょう。
メール業務を効率化して労働生産性を高める方法
ここからは、メール業務を効率化して労働生産性を高める方法をご紹介します。
メールチェックの回数を決める
基本的にメールは緊急性の高い内容を伝えるツールではないため、1営業日以内に返信すれば失礼にはあたらないと考えられています。受信の度にメール業務に取り掛かるのではなく、始業開始直後、昼休憩後、退勤30分前などとメールチェックの回数を決めることで、他の業務に集中することができます。
メールの優先順位を設定する
まずは受信したメールの内容を精査し、メールの優先順位を設定しましょう。
お礼のみのメールや、メールマガジンなどは対応を後回しにし、顧客や取引先とのやり取りなど、重要なメールを先に対応します。
さらに、優先順位別にフォルダやラベルを作成し、受信時に自動で振り分けられるように設定することで、優先順位の管理を簡略化することができます。
テンプレートを登録する
メールには基本的な形式が決まっており、一般的には宛名、本文前の挨拶、本文、締めの挨拶、署名の流れで作成します。そのため、定型文のテンプレートを作成することでメールの作成時間を削減できます。
一般的なメールソフトにはテンプレート機能が搭載されているため、作成頻度の高いメールを登録し、すぐに呼び出せるようにしましょう。
自社に合ったメールソフトを利用する
GmailやOutlookは個人で利用している人多いことから、ビジネスでも利用されていますが、無料プランは個人利用のための仕様であるため、ビジネス用途には機能が不十分である可能性があります。社内の運用ルールで解決できる場合もありますが、ルールが増えることで、労働生産性低下につながるリスクも高まります。
現在、様々なビジネス用メールソフトが提供されており、搭載されている機能も多種多様です。
企業規模や業界、業務内容によって、必要な機能は異なります。自社のメール業務の特性を把握した上で、必要な機能を洗い出し、自社に合ったメールソフトを見極めましょう。
まとめ
現代のビジネスにおいて、メール業務は必要不可欠ですが、使い方によっては労働生産性低下を招く可能性があります。メールはコミュニケーション手段の一つに過ぎないため、丁寧な対応を心掛けつつも、時間をかけ過ぎないことが重要です。
毎日発生する業務だからこそ、少しの工夫が日々の労働生産性を高めます。今回ご紹介したコツも参考にしながら、取り組めそうなものからひとつずつ始めてみましょう。
※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス(以下「当社」といいます)または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。